オーウェル評論集 1 新装版 象を撃つ

もちろん、機はすっかり熟していました。『1Q84』があれほどの現象になり、ハヤカワepi文庫で、高橋和久氏による新訳の『一九八四年』(本サイト、堀和世さんによるレビューを参照)が出たのですから、さあ、もう一声! というわけで、やってくれました、出してくれました。平凡社ライブラリーから『オーウェル評論集』が新装版としてめでたく「復刊」となったわけです。
ジョージ・オーウェルとは、いったい何者か。オーウェルのプロフィールはとてもカンタンに調べることができますが、ざっとご紹介しましょう。
1903年、イギリス・阿片局の役人だったお父さんの赴任地・インドのベンガル州で生まれています。奨学金のおかげで名門のイートン校に学び、19歳から5年間は、大英帝国警察官として、ビルマ(現ミャンマー)に赴任します。「後進国」で威圧的にふるまうヨーロッパの白人警官、という立ち位置は、オーウェルにとってたいへんに厳しいもので、この時の経験が、後の作家、社会主義者、ジャーナリストとしてのオーウェルの基盤を作っていると思われます。つまり、弱者や貧者に向けるまなざし、全体主義への対抗、イデオロギーではなく、自らの観察眼によって、目の前で起きている物事を捉える態度、などです。
警官を辞めたあとは、パリとロンドンで放浪生活を送り、貧乏のどん底も経験して、最初の著作『パリ・ロンドン放浪記』(岩波文庫)を著します。1936年にはスペインの内戦に共和国側の民兵として参加、喉にあやうく致命傷になりそうな傷を負ったりしています。この時の体験をもとに綴ったのが『カタロニア賛歌』で、『1984年』『動物農場』と並んで、一般に最もよく知られたオーウェルの著作といっていいと思います。
その後はBBCでラジオ番組を作ったり、雑誌の編集をしたりして、作家としての名声もどんどん上がっていきます。しかし晩年はスコットランドのジュラ島に移り住んでずっと籠もったままの生活を送り、1950年に結核で亡くなりました。46年という短い生涯でした。
オーウェルはしばしば、社会主義者とか、あるいはヒューマニストなどと言われたりします。その呼称はぜんぜん間違っていないと思いますが、しかし今日、この尊称はむしろ侮蔑的な意味を帯びています。「社会主義者」といえば旧弊な左翼みたいだし、「ヒューマニスト」だなんて、なんだか現実離れした偽善者みたい。まあ、そんな感じでしょう。
ところがオーウェルの書いたものを少しでも読んでみれば、なるほどこの人は言葉の真の意味で社会主義者でヒューマニストかもしれないが、それらの呼称がイメージする、古くさくて嘘くさいものとはおよそかけ離れている人だということがわかります。その知性、行動力、感受性、ユーモア、パッション、すべてにおいて、この人は本物だと思います。
【まず第一に感覚的な記憶――いろいろな音、におい、物の外観。
不思議なことに、スペイン戦争でその後経験したどんなことよりももっともあざやかに思い出されるのは、前線に送り出される前にいわゆる訓練なるものを受けた一週間のことである――バルセロナの巨大な騎兵隊兵舎、そのすきま風の吹き込む廏舎と石を敷いた中庭、顔を洗うときに使うポンプの氷のような冷たさ、ぶどう酒のおかげでなんとかがまんができた不潔な食事、薪を割っているズボンをはいた婦人民兵、そして早朝の点呼、その時はマヌエル・ゴンザレス、ペドロ・アギラール、ラモン・フェネリョーサ、ロケ・バリャステル、ハイメ・ドメネック、セバスチアン・ビルトロン、ラモン・ヌーボ・ボスクといった響きのいいスペイン名のなかで、私の散文的な名は何かこっけいな狂言のような感じだった。】
これは、「スペイン戦争回顧」というエッセイの冒頭部分です。前線より訓練時の記憶が喚起されるところにリアリティを感じます。スペイン戦争を回顧するにあたって、まずオーウェルはこうして五感を開放します。長く引用したのはなんといっても、ここにあらわれるスペイン・ネームの見事な音楽を聴いてほしいから。「私の散文的な名」とは、おそらく、「ジョージ・オーウェル」ではなく、本名の「エリック・アーサー・ブレア」のことでしょう。なるほど、このようにオーウェル自身によって書かれると、それはいかにも「散文的」に思えます。
ジョージ・オーウェルによる二十世紀世界文学の最高傑作『一九八四年 新訳版』の書評も収めていますので、ぜひお楽しみください。
『一九八四年 新訳版』 レビュワー/堀和世 書評を読む
おすすめ本書評・紹介書籍
-
- オーウェル評論集 1 新装版 象を撃つ
平凡社 /平凡社ライブラリー [随筆・エッセイ] 海外
2009.11 版型:文庫
価格:1,365円(税込)
>>詳細を見る
『オーウェル評論集』新装版・全四巻のうちの、第2〜4巻
-
- オーウェル評論集 2 新装版 水晶の精神
平凡社 /平凡社ライブラリー [思想・哲学・評論] 海外
2009.11 版型:文庫
価格:1,365円(税込)
>>詳細を見る
-
- オーウェル評論集 3 新装版 鯨の腹のなかで
平凡社 [文学研究] 海外
2009.12 版型:文庫
価格:1,365円(税込)
>>詳細を見る
-
- オーウェル評論集 4 新装版 ライオンと一角獣
平凡社 /平凡社ライブラリー [随筆・エッセイ] 海外
2009.12 版型:文庫
価格:1,365円(税込)
>>詳細を見る
新着情報
-

- 2013/08/16[新着書評]
『きことわ』朝吹真理子
評者:千三屋
-

- 2013/08/15[新着書評]
『テルマエ・ロマエⅥ』ヤマザキマリ/「1~3巻は大傑作、4~6巻は残念な出来」
評者:新藤純子
-

- 2013/06/19[新着書評]
『高円寺 古本酒場ものがたり』狩野俊
評者:千三屋

- 2013/05/12[新着書評]
『フィフティ・シェイズ・ダーカー(上・下)』ELジェイムズ
評者:日向郁

- 2013/04/04[新着書評]
『クラウド・アトラス』デイヴィッド・ミッチェル
評者:千三屋

- 2013/02/18[新着書評]
『はぶらし』近藤史恵
評者:日向郁

- 2013/01/31[新着書評]
『知的唯仏論』宮崎哲弥・呉智英
評者:千三屋

- 2013/01/18[新着書評]
『秋田寛のグラフィックデザイン』アキタ・デザイン・カン
評者:千三屋

- 2013/01/17[新着書評]
『空白を満たしなさい』平野啓一郎
評者:長坂陽子

- 2013/01/15[新着書評]
『箱根駅伝を歩く』泉麻人
評者:千三屋

- 2013/01/11[新着書評]
『世界が終わるわけではなく』ケイト・アトキンソン
評者:藤井勉

- 2012/12/19[新着書評]
『デザインの本の本』秋田寛
評者:千三屋

- 2012/11/28[新着書評]
『ニール・ヤング自伝I』ニール・ヤング
評者:藤井勉

- 2012/11/22[新着書評]
『日本人はなぜ「黒ブチ丸メガネ」なのか』友利昴
評者:新藤純子

- 2012/11/21[新着書評]
『私にふさわしいホテル』柚木麻子
評者:長坂陽子

- 2012/11/15[新着書評]
『格差と序列の心理学 平等主義のパラドクス』池上知子
評者:新藤純子
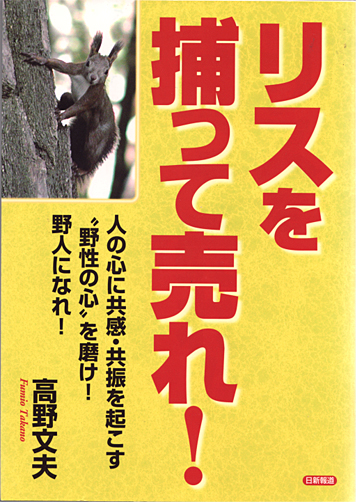
- 2012/11/09[イベントレポ]
兼業古本屋のできるまで。とみさわさん、なにをやってんすか

- 2012/11/08[新着書評]
『機龍警察 暗黒市場』月村了衛
評者:大谷暁生

- 2012/11/02[新着書評]
『なしくずしの死』L-F・セリーヌ
評者:藤田祥平

- 2012/10/31[新着書評]
『エコー・メイカー』リチャード・パワーズ
評者:藤井勉

- 2012/10/30[新着書評]
『文体練習』レーモン・クノー
評者:藤田祥平

- 2012/10/25[新着書評]
『生きのびるための建築』石山修武
評者:千三屋

- 2012/10/24[新着書評]
『占領都市 TOKYO YEAR ZERO Ⅱ』デイヴィッド・ピース
評者:大谷暁生

- 2012/10/19[新着書評]
『最後の授業 ぼくの命があるうちに』ランディ・パウシュ、ジェフリー・ザスロー
評者:日向郁

- 2012/10/18[新着書評]
『イタリア人と日本人、どっちがバカ?』ファブリツィオ・グラッセッリ
評者:相川藍

- 2012/10/17[イベントレポ]
ミステリー酒場スペシャル ローレンス・ブロック酒場Part1

- 2012/10/16[イベントレポ]
ブックレビューLIVE:杉江VS米光のどっちが売れるか!?

- 2012/10/15[イベントレポ]
ミステリ酒場スペシャル ローレンス・ブロック酒場三連発 PART2~泥棒バーニー、殺し屋ケラー編&ブロックおもてなし対策会議~

- 2012/10/15[新着書評]
『犬とハモニカ』江國香織
評者:長坂陽子

- 2012/10/10[新着書評]
『Papa told me cocohana ver.1 丘は花でいっぱい』榛野なな恵
評者:千三屋

- 2012/10/08[イベントレポ]
“その日”が来てからでは遅すぎる! あなたの知らないお葬式のすべて?ボッタクリの秘密から納得のエコ葬儀プランまで

- 2012/10/03[新着書評]
『青い脂』ウラジーミル・ソローキン
評者:藤井勉

- 2012/10/02[イベントレポ]
松本尚久さん、落語の楽しみ方を教えてください!

- 2012/10/01[新着書評]
『ヴァンパイア』岩井俊二
評者:長坂陽子

- 2012/09/25[新着書評]
『鬼談百景』小野不由美
評者:挟名紅治

- 2012/09/24[新着書評]
『ここは退屈迎えに来て』山内マリコ
評者:長坂陽子

- 2012/09/18[新着書評]
『最初の人間』アルベール・カミュ
評者:新藤純子

- 2012/09/14[新着書評]
『その日東京駅五時二十五分発』西川美和
評者:相川藍

- 2012/09/13[新着書評]
『無分別』オラシオ・カステジャーノス・モヤ
評者:藤井勉

- 2012/09/12[新着書評]
『鷲たちの盟約』(上下)アラン・グレン
評者:大谷暁生

- 2012/09/11[新着書評]
『ラブ・イズ・ア・ミックステープ』ロブ・シェフィールド
評者:日向郁

- 2012/09/10[新着書評]
『嵐のピクニック』本谷有希子
評者:長坂陽子

- 2012/09/07[新着書評]
『本当の経済の話をしよう』若田部昌澄、栗原裕一郎
評者:藤井勉

- 2012/09/05[新着書評]
『ひらいて』綿矢りさ
評者:長坂陽子

- 2012/09/04[新着書評]
『失脚/巫女の死 デュレンマット傑作選』フリードリヒ・デュレンマット
評者:藤井勉

- 2012/09/03[新着書評]
『かくも水深き不在』竹本健治
評者:蔓葉信博

- 2012/08/31[新着書評]
『わたしが眠りにつく前に』SJ・ワトソン
評者:長坂陽子

- 2012/08/28[新着書評]
『芸術実行犯』Chim↑Pom(チン↑ポム)
評者:相川藍

- 2012/08/27[新着書評]
『ぼくは勉強ができない』山田詠美
評者:姉崎あきか

- 2012/08/16[新着書評]
『オカルト 現れるモノ、隠れるモノ、見たいモノ』森達也
評者:長坂陽子

- 2012/08/10[新着書評]
『セックスなんか興味ない』きづきあきら サトウナンキ
評者:大谷暁生

- 2012/08/08[新着書評]
『深い疵』ネレ・ノイハウス
評者:挟名紅治

- 2012/08/07[新着書評]
【連載】 蔓葉信博「週末、たまにはビジネス書を」
第4回 小林直樹『ソーシャルリスク』 評者:蔓葉信博

- 2012/08/03[新着書評]
『はまむぎ』レーモン・クノー
評者:藤井勉

- 2012/08/02[新着書評]
『清須会議』三谷幸喜
評者:千三屋

- 2012/07/31[新着書評]
『岡崎京子の仕事集』岡崎京子(著)増渕俊之(編)
評者:相川藍

- 2012/07/28[新着書評]
『ことばの食卓』武田百合子
評者:杉江松恋

- 2012/07/18[新着書評]
『図説 死因百科』マイケル・ラルゴ
評者:大谷暁生

- 2012/07/13[新着書評]
『最果てアーケード』
小川洋子
評者:長坂陽子

- 2012/07/12[新着書評]
『なぜ戒名を自分でつけてもいいのか』橋爪大三郎
評者:千三屋

- 2012/07/05[新着書評]
『少年は残酷な弓を射る』(上・下)
ライオネル・シュライヴァー
評者:長坂陽子

- 2012/07/04[新着書評]
『未解決事件 グリコ・森永事件~捜査員300人の証言』NHKスペシャル取材班
評者:挟名紅治

- 2012/07/02[新着書評]
『女が嘘をつくとき』リュドミラ・ウリツカヤ
評者:藤井勉

- 2012/06/29[新着書評]
連載 蔓葉信博「週末、たまにはビジネス書を」
第3回 三浦展『第四の消費』 蔓葉信博

- 2012/06/27[新着書評]
『シフォン・リボン・シフォン』近藤史恵
評者:相川藍

- 2012/06/26[新着書評]
『湿地』アーナルデュル・インドリダソン
大谷暁生

- 2012/06/20[新着書評]
『彼女の存在、その破片』野中柊
長坂陽子

- 2012/06/15[新着書評]
『新人警官の掟』フェイ・ケラーマン
日向郁

- 2012/06/14[新着書評]
『俳優と超人形』ゴードン・クレイグ
千三屋

- 2012/06/13[新着書評]
『毒婦。 木嶋佳苗100日裁判傍聴記』北原みのり
長坂陽子

- 2012/06/12[新着書評]
『WOMBS』白井弓子
大谷暁生

- 2012/06/11[新着書評]
『21世紀の世界文学30冊を読む』都甲幸治
藤井勉

- 2012/06/08[新着書評]
『愛について』白岩玄
評者:相川藍

- 2012/06/06[新着書評]
『柔らかな犀の角ー山崎努の読書日記』山崎努
挟名紅治

- 2012/06/04[新着書評]
『夜をぶっとばせ』井上荒野
長坂陽子

- 2012/06/01[新着書評]
「七夜物語』川上弘美
長坂陽子

- 2012/05/23[新着書評]
「ピントがボケる音 OUT OF FOCUS, OUT OF SOUND』安田兼一
藤井勉

- 2012/05/21[新着書評]
「飼い慣らすことのできない幻獣たち」
『幻獣辞典』ホルヘ・ルイス・ボルヘス
藤田祥平

- 2012/05/16[新着書評]
連載「長坂陽子 ロマンスの神様願いを叶えて第18回」
「その名は自己満足」 長坂陽子

- 2012/03/30[新着書評]
連載「長坂陽子 ロマンスの神様願いを叶えて第17回」
「そのプライドが邪魔をする」 長坂陽子

- 2012/02/28[新着書評]
連載「長坂陽子 ロマンスの神様願いを叶えて第16回」
「恋のリスクマネジメント」 長坂陽子

- 2012/02/15[新着書評]
連載「長坂陽子 ロマンスの神様願いを叶えて第15回」
「非華奢女子の生きる道」 長坂陽子

- 2012/02/02[新着書評]
連載「長坂陽子 ロマンスの神様願いを叶えて第14回」
「パターン破りの効用」 長坂陽子

- 2012/01/31[新着書評]
『最高に美しい住宅をつくる方法』彦根明
評者:相川藍

- 2012/01/20[新着書評]
『ペット・サウンズ』ジム・フジーリ
評者:藤井勉

- 2012/01/17[新着書評]
連載「長坂陽子 ロマンスの神様願いを叶えて第13回」
胸だけ見ててもモテ期はこない 長坂陽子

- 2012/01/11[新着書評]
連載「長坂陽子 ロマンスの神様願いを叶えて第12回」
「恋で美しくなる」は本当か 長坂陽子

- 2012/01/10[新着書評]
「旧式のプライバシー」
『大阪の宿』水上滝太郎
藤田祥平
Internet Explorerをご利用の場合はバージョン6以上でご覧ください。
















