一九八四年 新訳版
一九八四年は今なお、近未来であり続ける
私はいずれ私自身を失うが、いつ失ったか私には分からないだろう
著 ジョージ・オーウェル 訳 高橋和久 早川書房 /ハヤカワepi文庫 [小説] 海外
2009.07 版型:文庫
>>書籍情報のページへ

なぜかここ数年立て続けに、郷里で中学校の同窓会がある。一年に一度でも、毎年顔を合わせていると元の同級生とも打ち解けてきて、同窓会に出るのが苦にならなくなってきた。
同窓会もいきなり行くと、身の置き場に困ることがある。昔の同級生といっても、顔が変わっていて分からないのも多いし、たまたま残っている面影を手がかりに記憶をたぐり寄せても、場合によっては数十年ぶりに会うわけだから共通の話題がない。
「ゴルフ、しますか」「いえ、しません」「ああ、そうですか」。そんなやりとりがそこここで交わされていたりする。手持ちぶさたを隠すために目の前のビールをあおるのだが、コップのビールがなくなっても、なかなか手酌でやるわけにはいかない。隣に座っている、顔には何となく見覚えがあるが名前が思い出せないこいつが、気を利かせてビールをついでくれればいいのにと思いつつも、その気配はない。
そんな気の抜けたビールのようなテーブルがあるかと思えば、いわゆる「恩師」を囲んで和気あいあいと盛り上がっているテーブルもある。それは間違いなく、学校を出てからも地元に残った人たちである。「先生、私も若い頃はワルをやりました」「そうそう、お前には手を焼いたもんだ」「まあ先生、飲んで飲んで」と、こちらではコップのビールが空くひまもない。学校の先生というのは、驚くほど教え子の当時の行状を覚えているように見える。ベテランの先生ともなれば、その数は1000人や2000人ではきかないと思うのだが、どうやって頭の中に入れているのだろうか。
かねがねそう不思議に思っていたのだが、最近気がついた。教師の頭の中にある「教え子の記憶」は、卒業後に醸成されるのだ。つまり、こういうことである。地元に残った教え子は、学校を卒業しても折に触れて担任の教師や部活動の顧問の先生と会う機会がある。教え子が成人すれば、一緒に酒を飲むこともあるだろう。そういう中で「先生、実は私はあのとき、こんなことをしました」「何! あれをやったのはお前だったのか」なんてやりとりが交わされる。そうすると、先生の頭の中には、「手を焼かされたが、なかなかかわいかった生徒」という記憶がさかのぼって再構成されるのである。
というわけで、教師が教え子を全員ならずともほとんど覚えているというのは「うそ」というか、不可能だと分かったので、あるときの同窓会で試しに私がいたバスケットボール部の顧問をしていた先生に「僕のこと、覚えていらっしゃらないでしょう」と聞いてみた。彼は私たちの学年を受け持った教師の中では群を抜いて人気者で、いわば同窓会のスターなのだが、先生は私の顔をチラと見ると、悪びれもせず「うん、覚えてない」と言った。要するに、卒業後の付き合いがどれだけあるかで、教師と教え子の「記憶のきずな」の強さが決まるのである。
そして、同窓会に出るともう一つ、気づかされることがある。それは自分がクラスのメインストリームから外れていたという事実だ。元同級生の顔を見たとたん、私の頭の中にはクラス内の「序列」がよみがえる。私は2番手グループの辺縁にいた。誰かが決めるわけではない。ただ、そうだと「分かる」のだ。
私の存在など眼中になかったスポーツ万能の元ガキ大将(死語?)がビール瓶片手に回ってきて、私の肩に手を置き「どう、元気にやってる?」と、空のコップを満たしてくれる。私は声が上ずるのをこらえるのに苦労する。誰もが知っている昔話を一つ二つして周りを笑わせ、別のテーブルに去る彼の背中を目で追いながら、私は隣に座る元クラスメートとの会話に戻る。「そうそう、それでね」と、中学時代に話をした覚えもないほど影の薄かったそいつが、私にビジネスでの成功譚を語って聞かせる。別のときに別の場所で聞いたならきっと面白い話だろうが、今はただ時間の無駄に思えて心が焦る。おまえと一緒だなんて、思われたくない。
元ガキ大将は今、確か地元で小学校の教師をやっているはずだ。一方、目の前のこいつは、仕事の内容はよく分からないが、本人の言葉を借りれば「フェラーリが2台、キャッシュで買える」そうだ。稼ぎという意味では、私だって今では元ガキ大将より上だろう。でも、それで少しでも心が落ち着くかといえば、そんなことはない。学歴だとか月給だとか、何かほかの物差しを必要とすることがない絶対的な「序列」が、確かに存在していたと思い知らされるだけだ。
ペーパーテストの成績がよかった分、私はその埋め合わせに時折、道化を演じる必要もあった。教室の床に転がった牛乳パックを踏みつけてクラスメートの顔を白いしずくだらけにし、ガキ大将と取り巻き(一番手グループ)が笑い転げるさまを見て安心した。そのときの自分が上目使いでいたことを私は忘れることはない。
そういう子ども同士によるむき出しの残酷さと、同窓会のいたって平和な雰囲気とのギャップに私はどうも慣れることができないのだ。とはいえ、毎回参加していると「同窓会仲間」とでも言うべき、元クラスメートの枠を超えた新しい(大人同士の)人間関係が生まれる。これは案外と居心地がよく、あるときの集まりで私は、アルコールも手伝って気が大きくなり、昔話のついでに「中3のころは本当につまらなかった。おれは早く卒業して高校に行きたいと思っていた。昔に戻りたいなんて全然思わない」と、ゴミ箱をひっくり返すように早口でまくし立てた。
テーブルが静まり返った。顔面に笑いのしっぽを残したまま、私は固まった。何かひどい失敗をしでかしたらしい。同じバスケ部だったアラフォー女子が、私を凝視していた。悲しいような怒ったようなその顔は「誰だってそう思ってる。そんなことは誰も分かってて、今ここで楽しく飲んでいるんじゃない」とでも言いたげであった。
完全に空気を読み違えた。記憶は書き換えられるものなのだと、ほかでもない私が気づいていたはずではないか。教師は教え子との思い出を都合よく組み立て直すという説を唱え、実験までして得意になっていたではないか。ならば、なぜ私は中学3年時代の干からびた人間関係を後生大事に胸にしまい、古い棘が心を突き刺すままにしておけなかったのか。
記憶は共有してこそ意味がある。自分の記憶が正しいと証明することは困難だ。妄想と区別できない。逆に共有されれば、いかに矛盾をはらんだ記憶でも真実とみなされる。結局、記憶は他覚的な性質を帯び始める。誰もが口をぬぐって過去の「序列」をなかったことにするなら、その記憶はすでに上書きされてしまったのと変わりがないのだ。
新着情報
-

- 2013/08/16[新着書評]
『きことわ』朝吹真理子
評者:千三屋
-

- 2013/08/15[新着書評]
『テルマエ・ロマエⅥ』ヤマザキマリ/「1~3巻は大傑作、4~6巻は残念な出来」
評者:新藤純子
-

- 2013/06/19[新着書評]
『高円寺 古本酒場ものがたり』狩野俊
評者:千三屋

- 2013/05/12[新着書評]
『フィフティ・シェイズ・ダーカー(上・下)』ELジェイムズ
評者:日向郁

- 2013/04/04[新着書評]
『クラウド・アトラス』デイヴィッド・ミッチェル
評者:千三屋

- 2013/02/18[新着書評]
『はぶらし』近藤史恵
評者:日向郁

- 2013/01/31[新着書評]
『知的唯仏論』宮崎哲弥・呉智英
評者:千三屋

- 2013/01/18[新着書評]
『秋田寛のグラフィックデザイン』アキタ・デザイン・カン
評者:千三屋

- 2013/01/17[新着書評]
『空白を満たしなさい』平野啓一郎
評者:長坂陽子

- 2013/01/15[新着書評]
『箱根駅伝を歩く』泉麻人
評者:千三屋

- 2013/01/11[新着書評]
『世界が終わるわけではなく』ケイト・アトキンソン
評者:藤井勉

- 2012/12/19[新着書評]
『デザインの本の本』秋田寛
評者:千三屋

- 2012/11/28[新着書評]
『ニール・ヤング自伝I』ニール・ヤング
評者:藤井勉

- 2012/11/22[新着書評]
『日本人はなぜ「黒ブチ丸メガネ」なのか』友利昴
評者:新藤純子

- 2012/11/21[新着書評]
『私にふさわしいホテル』柚木麻子
評者:長坂陽子

- 2012/11/15[新着書評]
『格差と序列の心理学 平等主義のパラドクス』池上知子
評者:新藤純子
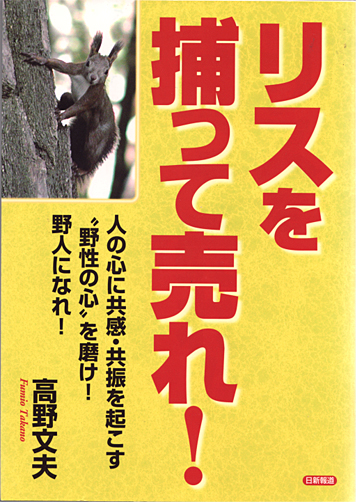
- 2012/11/09[イベントレポ]
兼業古本屋のできるまで。とみさわさん、なにをやってんすか

- 2012/11/08[新着書評]
『機龍警察 暗黒市場』月村了衛
評者:大谷暁生

- 2012/11/02[新着書評]
『なしくずしの死』L-F・セリーヌ
評者:藤田祥平

- 2012/10/31[新着書評]
『エコー・メイカー』リチャード・パワーズ
評者:藤井勉

- 2012/10/30[新着書評]
『文体練習』レーモン・クノー
評者:藤田祥平

- 2012/10/25[新着書評]
『生きのびるための建築』石山修武
評者:千三屋

- 2012/10/24[新着書評]
『占領都市 TOKYO YEAR ZERO Ⅱ』デイヴィッド・ピース
評者:大谷暁生

- 2012/10/19[新着書評]
『最後の授業 ぼくの命があるうちに』ランディ・パウシュ、ジェフリー・ザスロー
評者:日向郁

- 2012/10/18[新着書評]
『イタリア人と日本人、どっちがバカ?』ファブリツィオ・グラッセッリ
評者:相川藍

- 2012/10/17[イベントレポ]
ミステリー酒場スペシャル ローレンス・ブロック酒場Part1

- 2012/10/16[イベントレポ]
ブックレビューLIVE:杉江VS米光のどっちが売れるか!?

- 2012/10/15[イベントレポ]
ミステリ酒場スペシャル ローレンス・ブロック酒場三連発 PART2~泥棒バーニー、殺し屋ケラー編&ブロックおもてなし対策会議~

- 2012/10/15[新着書評]
『犬とハモニカ』江國香織
評者:長坂陽子

- 2012/10/10[新着書評]
『Papa told me cocohana ver.1 丘は花でいっぱい』榛野なな恵
評者:千三屋

- 2012/10/08[イベントレポ]
“その日”が来てからでは遅すぎる! あなたの知らないお葬式のすべて?ボッタクリの秘密から納得のエコ葬儀プランまで

- 2012/10/03[新着書評]
『青い脂』ウラジーミル・ソローキン
評者:藤井勉

- 2012/10/02[イベントレポ]
松本尚久さん、落語の楽しみ方を教えてください!

- 2012/10/01[新着書評]
『ヴァンパイア』岩井俊二
評者:長坂陽子

- 2012/09/25[新着書評]
『鬼談百景』小野不由美
評者:挟名紅治

- 2012/09/24[新着書評]
『ここは退屈迎えに来て』山内マリコ
評者:長坂陽子

- 2012/09/18[新着書評]
『最初の人間』アルベール・カミュ
評者:新藤純子

- 2012/09/14[新着書評]
『その日東京駅五時二十五分発』西川美和
評者:相川藍

- 2012/09/13[新着書評]
『無分別』オラシオ・カステジャーノス・モヤ
評者:藤井勉

- 2012/09/12[新着書評]
『鷲たちの盟約』(上下)アラン・グレン
評者:大谷暁生

- 2012/09/11[新着書評]
『ラブ・イズ・ア・ミックステープ』ロブ・シェフィールド
評者:日向郁

- 2012/09/10[新着書評]
『嵐のピクニック』本谷有希子
評者:長坂陽子

- 2012/09/07[新着書評]
『本当の経済の話をしよう』若田部昌澄、栗原裕一郎
評者:藤井勉

- 2012/09/05[新着書評]
『ひらいて』綿矢りさ
評者:長坂陽子

- 2012/09/04[新着書評]
『失脚/巫女の死 デュレンマット傑作選』フリードリヒ・デュレンマット
評者:藤井勉

- 2012/09/03[新着書評]
『かくも水深き不在』竹本健治
評者:蔓葉信博

- 2012/08/31[新着書評]
『わたしが眠りにつく前に』SJ・ワトソン
評者:長坂陽子

- 2012/08/28[新着書評]
『芸術実行犯』Chim↑Pom(チン↑ポム)
評者:相川藍

- 2012/08/27[新着書評]
『ぼくは勉強ができない』山田詠美
評者:姉崎あきか

- 2012/08/16[新着書評]
『オカルト 現れるモノ、隠れるモノ、見たいモノ』森達也
評者:長坂陽子

- 2012/08/10[新着書評]
『セックスなんか興味ない』きづきあきら サトウナンキ
評者:大谷暁生

- 2012/08/08[新着書評]
『深い疵』ネレ・ノイハウス
評者:挟名紅治

- 2012/08/07[新着書評]
【連載】 蔓葉信博「週末、たまにはビジネス書を」
第4回 小林直樹『ソーシャルリスク』 評者:蔓葉信博

- 2012/08/03[新着書評]
『はまむぎ』レーモン・クノー
評者:藤井勉

- 2012/08/02[新着書評]
『清須会議』三谷幸喜
評者:千三屋

- 2012/07/31[新着書評]
『岡崎京子の仕事集』岡崎京子(著)増渕俊之(編)
評者:相川藍

- 2012/07/28[新着書評]
『ことばの食卓』武田百合子
評者:杉江松恋

- 2012/07/18[新着書評]
『図説 死因百科』マイケル・ラルゴ
評者:大谷暁生

- 2012/07/13[新着書評]
『最果てアーケード』
小川洋子
評者:長坂陽子

- 2012/07/12[新着書評]
『なぜ戒名を自分でつけてもいいのか』橋爪大三郎
評者:千三屋

- 2012/07/05[新着書評]
『少年は残酷な弓を射る』(上・下)
ライオネル・シュライヴァー
評者:長坂陽子

- 2012/07/04[新着書評]
『未解決事件 グリコ・森永事件~捜査員300人の証言』NHKスペシャル取材班
評者:挟名紅治

- 2012/07/02[新着書評]
『女が嘘をつくとき』リュドミラ・ウリツカヤ
評者:藤井勉

- 2012/06/29[新着書評]
連載 蔓葉信博「週末、たまにはビジネス書を」
第3回 三浦展『第四の消費』 蔓葉信博

- 2012/06/27[新着書評]
『シフォン・リボン・シフォン』近藤史恵
評者:相川藍

- 2012/06/26[新着書評]
『湿地』アーナルデュル・インドリダソン
大谷暁生

- 2012/06/20[新着書評]
『彼女の存在、その破片』野中柊
長坂陽子

- 2012/06/15[新着書評]
『新人警官の掟』フェイ・ケラーマン
日向郁

- 2012/06/14[新着書評]
『俳優と超人形』ゴードン・クレイグ
千三屋

- 2012/06/13[新着書評]
『毒婦。 木嶋佳苗100日裁判傍聴記』北原みのり
長坂陽子

- 2012/06/12[新着書評]
『WOMBS』白井弓子
大谷暁生

- 2012/06/11[新着書評]
『21世紀の世界文学30冊を読む』都甲幸治
藤井勉

- 2012/06/08[新着書評]
『愛について』白岩玄
評者:相川藍

- 2012/06/06[新着書評]
『柔らかな犀の角ー山崎努の読書日記』山崎努
挟名紅治

- 2012/06/04[新着書評]
『夜をぶっとばせ』井上荒野
長坂陽子

- 2012/06/01[新着書評]
「七夜物語』川上弘美
長坂陽子

- 2012/05/23[新着書評]
「ピントがボケる音 OUT OF FOCUS, OUT OF SOUND』安田兼一
藤井勉

- 2012/05/21[新着書評]
「飼い慣らすことのできない幻獣たち」
『幻獣辞典』ホルヘ・ルイス・ボルヘス
藤田祥平

- 2012/05/16[新着書評]
連載「長坂陽子 ロマンスの神様願いを叶えて第18回」
「その名は自己満足」 長坂陽子

- 2012/03/30[新着書評]
連載「長坂陽子 ロマンスの神様願いを叶えて第17回」
「そのプライドが邪魔をする」 長坂陽子

- 2012/02/28[新着書評]
連載「長坂陽子 ロマンスの神様願いを叶えて第16回」
「恋のリスクマネジメント」 長坂陽子

- 2012/02/15[新着書評]
連載「長坂陽子 ロマンスの神様願いを叶えて第15回」
「非華奢女子の生きる道」 長坂陽子

- 2012/02/02[新着書評]
連載「長坂陽子 ロマンスの神様願いを叶えて第14回」
「パターン破りの効用」 長坂陽子

- 2012/01/31[新着書評]
『最高に美しい住宅をつくる方法』彦根明
評者:相川藍

- 2012/01/20[新着書評]
『ペット・サウンズ』ジム・フジーリ
評者:藤井勉

- 2012/01/17[新着書評]
連載「長坂陽子 ロマンスの神様願いを叶えて第13回」
胸だけ見ててもモテ期はこない 長坂陽子

- 2012/01/11[新着書評]
連載「長坂陽子 ロマンスの神様願いを叶えて第12回」
「恋で美しくなる」は本当か 長坂陽子

- 2012/01/10[新着書評]
「旧式のプライバシー」
『大阪の宿』水上滝太郎
藤田祥平
Internet Explorerをご利用の場合はバージョン6以上でご覧ください。
















