日本辺境論
「偏狭」じゃないよ、「辺境」だよ
北條一浩 Friday(二日前)新刊チェック 2009/12/2著 内田樹
新潮社 /新潮新書 [思想・哲学・評論] 国内
2009.11 版型:新書
>>書籍情報のページへ

NHKでドラマ『坂の上の雲』が始まりました。秋山兄弟と並ぶ主人公の一人・正岡子規に興味があるのと、子規の妹・律を演じているのが菅野美穂(好きなんです)だったりすることもあり、さっそく、第一回目の放映を見てみました。最初の回というのは、どうしても物語全体の見取り図を視聴者に理解してもらおうという意図が強くなり、また登場人物の紹介もしなければいけないので、説明過多になりがちです。『坂の上の雲』も、まったくもって例外ではありませんが、そうした事情を差し引いても、どうも今のところ、画面の躍動感に乏しく、ロケーションと美術と、あとは俳優の力で、なんとか情感をみなぎらせようと躍起になっているように感じられます。つまり、圧倒的に画が弱い。
しかし、司馬遼太郎原作(文春文庫で全八巻)の『坂の上の雲』への世間の注目度は、なかなかのものではないでしょうか。むろん、NHKがバンバン宣伝しているということもありますが、たぶん、それだけではない。なんというか、日本人全体の、明治という時代への憧れと郷愁がベースにあるような気がします。いま生きている日本人で、明治生まれの方々はだいぶ少なくなってしまい、明治を知らない人ばかりになったわけですが、それでも「無意識の国民的郷愁」ともいうべきものが、漂っているような気がします。
【私は別に「大きな物語」がよくて、専門研究がダメだと言っているのではありません。そうではなくて、トーブさん(注)や司馬さんと同じような「大きな物語」を書くタイプの知識人が近年あまりに少数になってしまったことをいささか心寂しく思っているのです。というわけで、本書では、縦横に奇説怪論を語り、奇中実をとらえ怪中真を掬(きく)して自ら資すという、当今まったく流行らなくなった明治書生の風儀を蘇生させたいと思っております。】
(注)トーブさん 未来学者、ローレンス・トーブ氏のこと。遠からず、中国、南北朝鮮、台湾、日本を統合した「コンフューシア」(儒教圏)の共同体ができる、という「大風呂敷」な議論を展開した著作『3つの原理』(ダイヤモンド社)がある。
「あ、これかな?」と思う言葉を、内田樹著『日本辺境論』の中に見つけました。「大きな物語」です。明治という時代への郷愁を、きっと色々な角度から見ることが可能だと思いますが、「大きな物語への郷愁」としてみると、とてもピッタリします。明治という時代は、西洋列強に追いつき、一刻も早く世界に冠たる近代国家になろうとする、国民全体の「大きな物語」がありました。むろんそれは、西洋諸国からは「猿真似」にしか見えなかったし、ロシアのような大国に戦争で勝ってしまったために、そこからどんどん一流国としての自意識が肥大し、やがて第二次大戦の悲劇につながり、その反動で戦後は「大きな物語」を積極的に駆逐しました。あげく、「最近の日本人は、小粒になった」みたいな物言いが出てきたわけです。郷愁とは、やはり「小」が「大」に思いを馳せる感覚ではないでしょうか。
『日本辺境論』は、その名のとおり、日本をその「辺境」性において見るという試みです。実に「ビッグ・ピクチャー」(大風呂敷)的なタイトルです。日本人は、もちろん自尊心はあるんだけれど(それが無い民族なんかいませんよね)、しかしなんとなく「ほんとうの文化」というのはどこか他所の国や地域にあって、微妙に劣等感を持っている。その劣等感が、あれほど大量の「日本論」「日本文化論」が書かれている(世界中で、日本人ほど自国の文化論が好きな国民はいない)理由で、いま、日本は世界レベルでどのへんにいるのかとか、外国人は日本をどう思っているかとか、思想の輸入に熱心だったりとか、要するに、すごく「きょろきょろ」している。「きょろきょろ」というのは丸山眞男の言葉ですが、およそそんなことがこの本には書いてあります。
これだけで要約してしまうと、すぐに威勢のいいことを言いたがる保守思想の人々を揶揄したような本だと思われるかもしれませんが、ぜんぜんそうじゃありません。だって『日本辺境論』は、「そんな日本、いいじゃん。これでやっていこう」という本なのですから。
【なにしろ、こんな国は歴史上、他に類例を見ないのです。それが歴史に登場し、今まで生き延びてきている以上、そこに固有の召命があると考えることは可能です。日本を「ふつうの国」にしようと空しく努力するより(どうせ無理なんですから)、こんな変わった国の人間にしかできないことがあるとしたら、それは何かを考える方がいい。その方が私たちだって楽しいし、諸国民にとっても有意義でしょう。】
うーん。イイですねえ。これまた実に大雑把な言い放ち方です(そういう箇所ばかり引用しているという話もありますが……)。いったい「ふつうの」学者が、「召命」だとか「楽しい」「有意義」なんて書くでしょうか。とても風通しのいい文章です。
「辺境」という概念はそもそも、中華思想の「中華」に対しての「辺境」ということです。地理的にもアジアの辺境にある日本は、言うまでもなく中国大陸の圧倒的な文化に対し、憧れも劣等感もあり、それらは千数百年の歴史にわたって日本人の中に沁み込んでいる。『日本辺境論』は、そういう「辺境」性を逆手に取るとか、世界の中心の陰に隠れていつのまにか成熟を遂げるとか、そういうセコい戦略性みたいなことは一切書いていなくて、「要するにそういう国なんだし、今後も変わんないと思いますよー」ということを言っています。
たぶん、本書でいちばん難解なのは、第Ⅲ部の「「機」の思想」のところで、これは自らも武道家であり、身体論も多く書いてきた内田氏ならではの展開です。「機」というのは独特の時間概念ですが、とてもここで的確に説明はできないので、申し訳ないですが直接、本書にあたってください。ここで著者は、「辺境」性の、あまり良いとはいえない部分について、ハッとするようなことをたくさん書いています。
【私たちは辺境にいる。中心から遠く隔絶している。だから、ここまで叡智が届くには長い距離を踏破する必要がある。私たちはそう考えます。それはいいのです。(中略)霊的成熟は、どこかの他の土地において、誰か「霊的な先進者」が引き受けるべき仕事であり、私たちはいずれ遠方から到来するであろうその余沢に浴する機会を待っているだけでよい。そういう腰の引け方は無神論者の傲岸や原理主義者の狂信に比べればはるかに穏当なものでありますけれど、その代償として、鋭く、緊張感のある宗教感覚の発達を阻んでしまう。】
確かに、「鋭く、緊張感のある宗教感覚」なんて、私たちは持ち合わせていません。
【日本人はどんな技術でも「道」にしてしまうと言われます。柔道、剣道、華道、茶道、香道……なんにでも「道」が付きます。このような社会は日本の他にはあまり存在しません。この「道」の繁昌は実は「切迫していない」という日本人の辺境的宗教性と深いつながりがあると私は思っています。】
なんというご明察。こんな考え方、初めて知りました。いや、確かに。「道」とは、いつか最終地にたどり着くもの、ですから、とりあえずいまはずいぶん手前にいてもよいということになる。長くけわしい、ロング・アンド・ワインディング・ロードを行く、なんつって、あれって実は「自分はまだ未熟だから、今はできませんけど……」という言い訳の成り立つ場所だったのだな。なんと「道」というのは、エクスキューズのことだったのです。
今までもそうだったし、それってきっと変えられないものだから、だったらそういう国として、できることをやっていこう。ヘンな国でもまあ、いいじゃん。『日本辺境論』は、そういう本です。たしかに「日本はエラい」という「偏狭」より、「辺境」のほうがいい。しかし、ここには「辺境」ゆえの弱さやズルさについても書いてあるし、右翼も左翼も読んで溜飲の下がる本ではまったく無さそうです。
それにしても内田樹さんって、物事を説明するのが抜群にうまいなあ。目からウロコが、バッサバッサ落ちるので、☆☆☆☆☆。
| とてもおすすめ | ☆☆☆☆☆ |
|---|---|
| おすすめ | ☆☆☆☆ |
| まあまあ | ☆☆☆ |
| あまりおすすめできない | ☆☆ |
| これは困った | ☆ |
新着情報
-

- 2013/08/16[新着書評]
『きことわ』朝吹真理子
評者:千三屋
-

- 2013/08/15[新着書評]
『テルマエ・ロマエⅥ』ヤマザキマリ/「1~3巻は大傑作、4~6巻は残念な出来」
評者:新藤純子
-

- 2013/06/19[新着書評]
『高円寺 古本酒場ものがたり』狩野俊
評者:千三屋

- 2013/05/12[新着書評]
『フィフティ・シェイズ・ダーカー(上・下)』ELジェイムズ
評者:日向郁

- 2013/04/04[新着書評]
『クラウド・アトラス』デイヴィッド・ミッチェル
評者:千三屋

- 2013/02/18[新着書評]
『はぶらし』近藤史恵
評者:日向郁

- 2013/01/31[新着書評]
『知的唯仏論』宮崎哲弥・呉智英
評者:千三屋

- 2013/01/18[新着書評]
『秋田寛のグラフィックデザイン』アキタ・デザイン・カン
評者:千三屋

- 2013/01/17[新着書評]
『空白を満たしなさい』平野啓一郎
評者:長坂陽子

- 2013/01/15[新着書評]
『箱根駅伝を歩く』泉麻人
評者:千三屋

- 2013/01/11[新着書評]
『世界が終わるわけではなく』ケイト・アトキンソン
評者:藤井勉

- 2012/12/19[新着書評]
『デザインの本の本』秋田寛
評者:千三屋

- 2012/11/28[新着書評]
『ニール・ヤング自伝I』ニール・ヤング
評者:藤井勉

- 2012/11/22[新着書評]
『日本人はなぜ「黒ブチ丸メガネ」なのか』友利昴
評者:新藤純子

- 2012/11/21[新着書評]
『私にふさわしいホテル』柚木麻子
評者:長坂陽子

- 2012/11/15[新着書評]
『格差と序列の心理学 平等主義のパラドクス』池上知子
評者:新藤純子
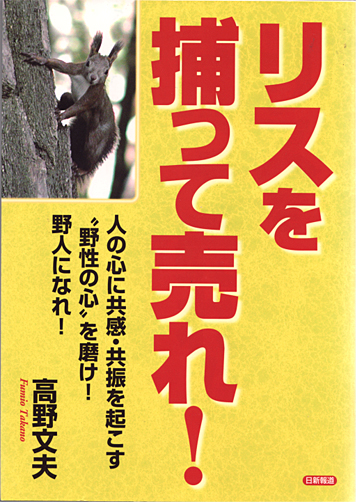
- 2012/11/09[イベントレポ]
兼業古本屋のできるまで。とみさわさん、なにをやってんすか

- 2012/11/08[新着書評]
『機龍警察 暗黒市場』月村了衛
評者:大谷暁生

- 2012/11/02[新着書評]
『なしくずしの死』L-F・セリーヌ
評者:藤田祥平

- 2012/10/31[新着書評]
『エコー・メイカー』リチャード・パワーズ
評者:藤井勉

- 2012/10/30[新着書評]
『文体練習』レーモン・クノー
評者:藤田祥平

- 2012/10/25[新着書評]
『生きのびるための建築』石山修武
評者:千三屋

- 2012/10/24[新着書評]
『占領都市 TOKYO YEAR ZERO Ⅱ』デイヴィッド・ピース
評者:大谷暁生

- 2012/10/19[新着書評]
『最後の授業 ぼくの命があるうちに』ランディ・パウシュ、ジェフリー・ザスロー
評者:日向郁

- 2012/10/18[新着書評]
『イタリア人と日本人、どっちがバカ?』ファブリツィオ・グラッセッリ
評者:相川藍

- 2012/10/17[イベントレポ]
ミステリー酒場スペシャル ローレンス・ブロック酒場Part1

- 2012/10/16[イベントレポ]
ブックレビューLIVE:杉江VS米光のどっちが売れるか!?

- 2012/10/15[イベントレポ]
ミステリ酒場スペシャル ローレンス・ブロック酒場三連発 PART2~泥棒バーニー、殺し屋ケラー編&ブロックおもてなし対策会議~

- 2012/10/15[新着書評]
『犬とハモニカ』江國香織
評者:長坂陽子

- 2012/10/10[新着書評]
『Papa told me cocohana ver.1 丘は花でいっぱい』榛野なな恵
評者:千三屋

- 2012/10/08[イベントレポ]
“その日”が来てからでは遅すぎる! あなたの知らないお葬式のすべて?ボッタクリの秘密から納得のエコ葬儀プランまで

- 2012/10/03[新着書評]
『青い脂』ウラジーミル・ソローキン
評者:藤井勉

- 2012/10/02[イベントレポ]
松本尚久さん、落語の楽しみ方を教えてください!

- 2012/10/01[新着書評]
『ヴァンパイア』岩井俊二
評者:長坂陽子

- 2012/09/25[新着書評]
『鬼談百景』小野不由美
評者:挟名紅治

- 2012/09/24[新着書評]
『ここは退屈迎えに来て』山内マリコ
評者:長坂陽子

- 2012/09/18[新着書評]
『最初の人間』アルベール・カミュ
評者:新藤純子

- 2012/09/14[新着書評]
『その日東京駅五時二十五分発』西川美和
評者:相川藍

- 2012/09/13[新着書評]
『無分別』オラシオ・カステジャーノス・モヤ
評者:藤井勉

- 2012/09/12[新着書評]
『鷲たちの盟約』(上下)アラン・グレン
評者:大谷暁生

- 2012/09/11[新着書評]
『ラブ・イズ・ア・ミックステープ』ロブ・シェフィールド
評者:日向郁

- 2012/09/10[新着書評]
『嵐のピクニック』本谷有希子
評者:長坂陽子

- 2012/09/07[新着書評]
『本当の経済の話をしよう』若田部昌澄、栗原裕一郎
評者:藤井勉

- 2012/09/05[新着書評]
『ひらいて』綿矢りさ
評者:長坂陽子

- 2012/09/04[新着書評]
『失脚/巫女の死 デュレンマット傑作選』フリードリヒ・デュレンマット
評者:藤井勉

- 2012/09/03[新着書評]
『かくも水深き不在』竹本健治
評者:蔓葉信博

- 2012/08/31[新着書評]
『わたしが眠りにつく前に』SJ・ワトソン
評者:長坂陽子

- 2012/08/28[新着書評]
『芸術実行犯』Chim↑Pom(チン↑ポム)
評者:相川藍

- 2012/08/27[新着書評]
『ぼくは勉強ができない』山田詠美
評者:姉崎あきか

- 2012/08/16[新着書評]
『オカルト 現れるモノ、隠れるモノ、見たいモノ』森達也
評者:長坂陽子

- 2012/08/10[新着書評]
『セックスなんか興味ない』きづきあきら サトウナンキ
評者:大谷暁生

- 2012/08/08[新着書評]
『深い疵』ネレ・ノイハウス
評者:挟名紅治

- 2012/08/07[新着書評]
【連載】 蔓葉信博「週末、たまにはビジネス書を」
第4回 小林直樹『ソーシャルリスク』 評者:蔓葉信博

- 2012/08/03[新着書評]
『はまむぎ』レーモン・クノー
評者:藤井勉

- 2012/08/02[新着書評]
『清須会議』三谷幸喜
評者:千三屋

- 2012/07/31[新着書評]
『岡崎京子の仕事集』岡崎京子(著)増渕俊之(編)
評者:相川藍

- 2012/07/28[新着書評]
『ことばの食卓』武田百合子
評者:杉江松恋

- 2012/07/18[新着書評]
『図説 死因百科』マイケル・ラルゴ
評者:大谷暁生

- 2012/07/13[新着書評]
『最果てアーケード』
小川洋子
評者:長坂陽子

- 2012/07/12[新着書評]
『なぜ戒名を自分でつけてもいいのか』橋爪大三郎
評者:千三屋

- 2012/07/05[新着書評]
『少年は残酷な弓を射る』(上・下)
ライオネル・シュライヴァー
評者:長坂陽子

- 2012/07/04[新着書評]
『未解決事件 グリコ・森永事件~捜査員300人の証言』NHKスペシャル取材班
評者:挟名紅治

- 2012/07/02[新着書評]
『女が嘘をつくとき』リュドミラ・ウリツカヤ
評者:藤井勉

- 2012/06/29[新着書評]
連載 蔓葉信博「週末、たまにはビジネス書を」
第3回 三浦展『第四の消費』 蔓葉信博

- 2012/06/27[新着書評]
『シフォン・リボン・シフォン』近藤史恵
評者:相川藍

- 2012/06/26[新着書評]
『湿地』アーナルデュル・インドリダソン
大谷暁生

- 2012/06/20[新着書評]
『彼女の存在、その破片』野中柊
長坂陽子

- 2012/06/15[新着書評]
『新人警官の掟』フェイ・ケラーマン
日向郁

- 2012/06/14[新着書評]
『俳優と超人形』ゴードン・クレイグ
千三屋

- 2012/06/13[新着書評]
『毒婦。 木嶋佳苗100日裁判傍聴記』北原みのり
長坂陽子

- 2012/06/12[新着書評]
『WOMBS』白井弓子
大谷暁生

- 2012/06/11[新着書評]
『21世紀の世界文学30冊を読む』都甲幸治
藤井勉

- 2012/06/08[新着書評]
『愛について』白岩玄
評者:相川藍

- 2012/06/06[新着書評]
『柔らかな犀の角ー山崎努の読書日記』山崎努
挟名紅治

- 2012/06/04[新着書評]
『夜をぶっとばせ』井上荒野
長坂陽子

- 2012/06/01[新着書評]
「七夜物語』川上弘美
長坂陽子

- 2012/05/23[新着書評]
「ピントがボケる音 OUT OF FOCUS, OUT OF SOUND』安田兼一
藤井勉

- 2012/05/21[新着書評]
「飼い慣らすことのできない幻獣たち」
『幻獣辞典』ホルヘ・ルイス・ボルヘス
藤田祥平

- 2012/05/16[新着書評]
連載「長坂陽子 ロマンスの神様願いを叶えて第18回」
「その名は自己満足」 長坂陽子

- 2012/03/30[新着書評]
連載「長坂陽子 ロマンスの神様願いを叶えて第17回」
「そのプライドが邪魔をする」 長坂陽子

- 2012/02/28[新着書評]
連載「長坂陽子 ロマンスの神様願いを叶えて第16回」
「恋のリスクマネジメント」 長坂陽子

- 2012/02/15[新着書評]
連載「長坂陽子 ロマンスの神様願いを叶えて第15回」
「非華奢女子の生きる道」 長坂陽子

- 2012/02/02[新着書評]
連載「長坂陽子 ロマンスの神様願いを叶えて第14回」
「パターン破りの効用」 長坂陽子

- 2012/01/31[新着書評]
『最高に美しい住宅をつくる方法』彦根明
評者:相川藍

- 2012/01/20[新着書評]
『ペット・サウンズ』ジム・フジーリ
評者:藤井勉

- 2012/01/17[新着書評]
連載「長坂陽子 ロマンスの神様願いを叶えて第13回」
胸だけ見ててもモテ期はこない 長坂陽子

- 2012/01/11[新着書評]
連載「長坂陽子 ロマンスの神様願いを叶えて第12回」
「恋で美しくなる」は本当か 長坂陽子

- 2012/01/10[新着書評]
「旧式のプライバシー」
『大阪の宿』水上滝太郎
藤田祥平
Internet Explorerをご利用の場合はバージョン6以上でご覧ください。
















