1994年の猛暑の夏、涼を求めてドトールやカフェ・ベローチェをハシゴしながら、私が夢中になって読んでいた1冊の分厚い洋書があった。大判で600ページにもおよぶその本は、デヴィッド・C・キャシディというアメリカの物理学者が書いた『Uncertainty: The Life and Science of Werner Heisenberg』(1992年出版)――1920年代、量子力学という新しい分野で不確定性原理という理論を生み出したドイツの天才物理学者ヴェルナー・ハイゼンベルクの伝記である(翻訳は4年後の1998年に『不確定性――ハイゼンベルクの科学と生涯』として出版された)。
それはまるで小説のように面白い本だった。20世紀のはじめにドイツに生まれた若き天才が、コペンハーゲンの物理学者ニルス・ボーアのもとに集まった同世代の若い科学者たちと量子力学を研究し、画期的な理論を打ち立て、ノーベル賞を受賞。しかし、ナチスが台頭した30年代には、仲間のユダヤ人科学者たちは次々と亡命、反ナチのハイゼンベルクも亡命をすすめられたが、彼はドイツに残り、やがて、ナチスのもとで研究者としての地位を得る。
ハイゼンベルクのこのような生涯は、『部分と全体』という自伝もあり、すでに知られたことではあったが、キャシディの本はハイゼンベルクをまるで小説の主人公のように描いていた。特に、ボーアや仲間たちとの研究からすばらしい成果を上げた光り輝く青春時代が、やがてナチスの台頭によって悲劇の時代となり、純粋な学問だった原子物理学が原爆という最悪の結果をもたらすという史実は、楽園喪失のドラマそのものだった。若き日のハイゼンベルクを物理学の英雄として崇拝するキャシディは、ナチスの時代に亡命もせず、反ナチ活動もしなかった彼を許せなかった。キャシディにとって、ナチス時代のハイゼンベルクは堕ちた英雄である。伝記の後半はハイゼンベルクへの批判の言葉が多くなり、前半のわくわくするような筆致は影をひそめてしまう。
理系が苦手な私が、この本を――ハイゼンベルクの生涯だけでなく、量子力学の難解な解説や数式も多数含むこの長大な本をわざわざ原書で読もうと思ったのは、94年春に翻訳が出版されたトマス・パワーズ著『なぜ、ナチスは原爆製造に失敗したか――連合国が最も恐れた男 天才ハイゼンベルクの闘い』を読んだためである。アメリカのジャーナリスト、パワーズは、ナチスのもとで原爆製造にかかわっていたのではないかと疑われたハイゼンベルクについて、実は彼は、ナチスの原爆製造を阻止するためにドイツにとどまり、原爆製造は無理であると上層部に思い込ませることで、ナチスが原爆を手に入れることを防いだのだと主張する。ハイゼンベルクがドイツで原爆の研究をしていなかったことはすでに証明されているが、それは単に、ドイツの科学が遅れていたからだというそれまでの定説に対し、パワーズはハイゼンベルクが積極的に原爆製造を阻止したのだと論じる。そして、返す刀で、ロス・アラモスで原爆製造を成し遂げ、広島と長崎に投下してしまったアメリカを批判している(アメリカではいまだに、原爆投下は終戦を早め、犠牲者を減らしたという論が主流であることを考えると、アメリカ人のパワーズによるこの本の異端ぶりがわかるだろう。当時、スミソニアン博物館が原爆投下の被害に関する展示を行なおうとしていたが、国内の強い反発にあい、規模の縮小を余儀なくされるということがあった)。
パワーズの本はミステリーのように面白いノンフィクションで、翻訳もこなれて読みやすかった。ただ、翻訳を読んだだけで誤訳や訳抜けがわかる箇所があり、気になった私は原書『Heisenberg's War』(1993年出版)を購入、本を開いてみて、驚いた。原書には膨大な注がついていて、しかも注の文章が非常に長い。これほど長い注はもはや注ではなく、本文の一部であり、ここがあるかないかで本の内容が違ってくるとさえ思えた。また、結末の部分が原書と翻訳では内容が大きく違っていたが、これは著者がどこかで本文を差し替えたのかもしれない(翻訳の方が原爆投下を非難するトーンが強い)。
そして、翻訳では省略された注の部分から、このパワーズの本が前述のキャシディのハイゼンベルクの伝記に対する反論であることがわかったのである。キャシディは、ハイゼンベルクが基本的に反ナチであること、ユダヤ人科学者の亡命に尽力したことは認めたが、積極的に反ナチ活動をしなかったという点で、彼を強く非難していた。それに対し、パワーズは、ハイゼンベルクは積極的にナチスの原爆製造を阻止したのだ、という反論を展開したわけである。
前説が長くなったが、マイケル・フレインの劇『コペンハーゲン』(初演1998年、ロンドン)は、「作者あとがき」にもあるように、1992年と93年に相次いで出版されたキャシディの伝記とパワーズのノンフィクションの影響を強く受けている。特にパワーズの『なぜ、ナチスは原爆製造に失敗したか』から多大なインスピレーションを受けたことは明らかで、フレインは「私はこの本を、特に他の劇作家や映画の脚本家に推薦します。ここにはさらに何本かの戯曲や映画を作る材料が揃っているからです」と述べている。
ハイゼンベルクは原爆の研究に対し、どのような態度をとっていたのか。その疑問は、1941年、ハイゼンベルクがドイツ占領下のデンマーク、コペンハーゲンへ行き、かつての恩師ボーアの家を訪ねた1日に集約される。その日、ハイゼンベルクがボーアを訪ねたのは事実であり、そこでハイゼンベルクはボーアにあることを告げ、それが2人を決裂させたことも事実である。その日を境に、ハイゼンベルクはボーアをはじめとするかつての仲間たちから完全に敵とみなされ、戦後も彼らから許されることはなかった。
あのとき、ハイゼンベルクがボーアに何を言ったのかは明らかになっていない。戦後になって、ハイゼンベルクは「一物理学者に、原子力エネルギーの実践的活用を研究する道徳上の権利はあるのでしょうか」と言ったのだと語ったが、ボーアはそれを否定。数年たつ間に記憶が変容することを考えると、事実は闇の中である。
フレインはこの問題の1日を、ボーアと夫人のマルグレーテ、そしてハイゼンベルクの3人の台詞で構成していく。時代は現代で、3人はすでに幽霊になっているが、その語りの中で、彼らは1941年のあの日に帰る。ハイゼンベルクがボーアの家へやってきて、扉をたたく。ボーアが彼を迎える。
ボーア やあ、ハイゼンベルク君!
ハイゼンベルク こんにちは、ボーア先生!
ボーア さあ、入った、入った……
このやりとりは劇中、何度も繰り返される。ボーアの家には盗聴器が仕掛けられていたので、2人は外へ散歩に出る。そこで何が語られたのか。ボーアとハイゼンベルクとマルグレーテは記憶をたどりながら、さまざまなことを語る。全2幕の劇のうち、第1幕はおもに、パワーズが『なぜ、ナチスは原爆製造に失敗したか』で主張したことがドラマの基本となっている。すなわち、ハイゼンベルクはナチスが原爆を持つことを防ぐためにドイツに残り、研究者としての地位を得て、原爆製造が不可能であると上層部に思わせ続けたのだということ。それに対し、アメリカへ亡命した科学者たちはドイツが原爆を持つことを恐れて原爆製造に全力を注いだこと。そして、ハイゼンベルクがボーアに言いたかったのは、自分たちがドイツで原爆製造を阻止するから、連合国の科学者たちにもそうしてほしいということだったのだということ。
第2幕になると、時代は1920年代にさかのぼり、コペンハーゲンのボーアの研究所に集まった若き科学者たちが原子物理学について喧々諤々の議論をした日々が回想される。ボーアとハイゼンベルクとの間には父と息子のような絆が生まれ、それはまさに黄金時代だった。第2幕の後半では、原子爆弾の実現にはどれだけのウランが必要であるかについての議論がかわされる。ハイゼンベルクをはじめ、科学者たちは大量のウランが必要なので原爆製造は無理だと思っていた。しかし、連合国側の2人の科学者がやがて正しい計算をし、原爆製造にはそれほど多くのウランは必要ないことがわかる。ハイゼンベルクほどの天才がなぜ、そのことに気づかなかったのか。気づいていたけれど、ナチスに原爆を作らせないために隠していたのか。あるいは、原爆を作りたくないという無意識が、彼が正しい計算をするのを邪魔したのか。
ふたたび、前説に戻ろう。パワーズのノンフィクションを読んだとき、私が感じたのは、ハイゼンベルクが積極的にナチスの原爆製造を阻止したというのはいくらなんでも話ができすぎているということだった。かといって、キャシディの伝記に代表されるハイゼンベルク非難――彼は時代に流されてナチスに協力する形になったが、原爆の研究に関してはまったく無能であり、それゆえにナチスは原爆製造を断念したのだという考え方も納得できなかった。真相はおそらくその中間にあると思った。ハイゼンベルクは積極的に原爆製造を阻止したわけではなかったが、原爆を作りたくないという消極的な気持ちが結果的にナチスの原爆製造を阻止したのだろう、ということである。
『コペンハーゲン』もこの結論(おそらくは世界中の読者の結論)を基本にしている。ハイゼンベルクは無意識のうちに原爆を拒否する行動をとったが、彼自身はそのことがわかっていないので、戦後、不可解な発言をし、真相は闇の中になっているという考え方を打ち出している。そしてフレインは、ハイゼンベルクのこのような状態を、ハイゼンベルク自身の不確定性原理のたとえで説明していく。すなわち、量子には粒子と波動の両方の特性があり、どちらになるかは観察者の状態によって決まる。言い換えれば、ある事柄を完全に客観的に見ることは不可能で、それは見る人によって違うということ。
ハイゼンベルクの行動が見る人によって違って見えるということ、そしてなにより、本人も自分のことがよくわかっていないということを描くために、フレインは3人の登場人物を極力、本物に近づけたようだ。3人がどのような話し方をするかを調べ、台詞も実際に発言したことをもとにしている。恣意的な創作といえる部分は、こうした事柄をいかに組み合わせて並べるかというところだが、そこも、簡単に作者の意図が読めるような構成はしていない。むしろ、台詞は量子のようにいくつものスリットをすり抜け、姿を変え、読者を翻弄する。中心となる物語の合間に何度も繰り返される、水死したボーアの息子、人間の魂の闇だというハムレットの居城エルシノア、ポーカーの想像上のストレートといったイメージが、しだいに物語の核に結びついていく。
『コペンハーゲン』の結末は、ハイゼンベルクとボーアが”話し合わなかった”ことの重要性を語っている。ハイゼンベルクが原爆の可能性を口にしたとき、ボーアがそれ以上の話し合いを拒否し、2人が決裂したことで、世界が救われたという可能性を、この劇はほのめかしている。この劇は多くの資料から成り立っているが、フレインの言うように、この部分だけは彼の創作だろう。今書いたことはある種のネタバレなのだが、この劇はネタバレによって失われるものは少ない。私はこの文章を書くために都合、3回、劇を読んだが、何度読んでも言葉の波に翻弄され、新たな体験をする。結末は必ずしも重要ではない。
最後に、不確定性原理を量子以外の世界に適応する是非について、書いておかねばならない。私が不確定性原理を知ったのは1970年代末だったが、当時は文学の世界ではロラン・バルトなどの構造主義のすぐ後ろに脱構築の足音が迫っているという時代だった。その頃、英文学を研究していた私は、「量子のふるまいは観察者の状態によって決まる」という不確定性原理に、文学のテクストは読まれることによって初めて意味を持つという当時の文学論との共通点を感じた。それからハイゼンベルクの自伝『部分と全体』を読み、その哲学的思索に魅せられるようになったのだが、その一方で、理系の人々が、不確定性原理は文系の人が考えるようなものではないと主張していることもわかった。
『コペンハーゲン』は不確定性原理を人間にあてはめているという点で、すでに理系を離れ、文系人間の不確定性原理になっているが、フレインは「作者あとがき」で次のように述べている、「不確定性という概念が、日常語に転化した科学的発想の一つであり、もともとの意味を失ってしまうほどに一般化していることは事実です」。『コペンハーゲン』に登場するハイゼンベルクは、天才でありながら、自分が見えていない子供のような人物でもある。その不確定性は、物語を愛する文系人間を永遠に魅了してやまないだろう。
追記 『コペンハーゲン』は日本でも舞台で上演されているが、私は見ていない。また、この劇は2002年にイギリスでドラマ化され、ダニエル・クレイグがハイゼンベルクを演じている。
-
(画像はAmazonへのリンク) -
『マイケル・フレイン(1) コペンハーゲン』
早川書房 /ハヤカワ演劇文庫 [戯曲] [サイエンス] 海外
2010.11 版型:文庫 ISBN:4151400281
価格:945円(税込)
書評書籍
新着情報
-

- 2013/08/16[新着書評]
『きことわ』朝吹真理子
評者:千三屋
-

- 2013/08/15[新着書評]
『テルマエ・ロマエⅥ』ヤマザキマリ/「1~3巻は大傑作、4~6巻は残念な出来」
評者:新藤純子
-

- 2013/06/19[新着書評]
『高円寺 古本酒場ものがたり』狩野俊
評者:千三屋

- 2013/05/12[新着書評]
『フィフティ・シェイズ・ダーカー(上・下)』ELジェイムズ
評者:日向郁

- 2013/04/04[新着書評]
『クラウド・アトラス』デイヴィッド・ミッチェル
評者:千三屋

- 2013/02/18[新着書評]
『はぶらし』近藤史恵
評者:日向郁

- 2013/01/31[新着書評]
『知的唯仏論』宮崎哲弥・呉智英
評者:千三屋

- 2013/01/18[新着書評]
『秋田寛のグラフィックデザイン』アキタ・デザイン・カン
評者:千三屋

- 2013/01/17[新着書評]
『空白を満たしなさい』平野啓一郎
評者:長坂陽子

- 2013/01/15[新着書評]
『箱根駅伝を歩く』泉麻人
評者:千三屋

- 2013/01/11[新着書評]
『世界が終わるわけではなく』ケイト・アトキンソン
評者:藤井勉

- 2012/12/19[新着書評]
『デザインの本の本』秋田寛
評者:千三屋

- 2012/11/28[新着書評]
『ニール・ヤング自伝I』ニール・ヤング
評者:藤井勉

- 2012/11/22[新着書評]
『日本人はなぜ「黒ブチ丸メガネ」なのか』友利昴
評者:新藤純子

- 2012/11/21[新着書評]
『私にふさわしいホテル』柚木麻子
評者:長坂陽子

- 2012/11/15[新着書評]
『格差と序列の心理学 平等主義のパラドクス』池上知子
評者:新藤純子
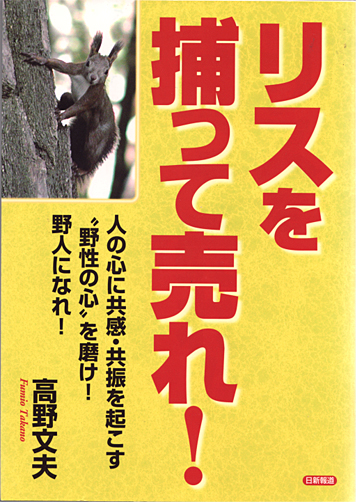
- 2012/11/09[イベントレポ]
兼業古本屋のできるまで。とみさわさん、なにをやってんすか

- 2012/11/08[新着書評]
『機龍警察 暗黒市場』月村了衛
評者:大谷暁生

- 2012/11/02[新着書評]
『なしくずしの死』L-F・セリーヌ
評者:藤田祥平

- 2012/10/31[新着書評]
『エコー・メイカー』リチャード・パワーズ
評者:藤井勉

- 2012/10/30[新着書評]
『文体練習』レーモン・クノー
評者:藤田祥平

- 2012/10/25[新着書評]
『生きのびるための建築』石山修武
評者:千三屋

- 2012/10/24[新着書評]
『占領都市 TOKYO YEAR ZERO Ⅱ』デイヴィッド・ピース
評者:大谷暁生

- 2012/10/19[新着書評]
『最後の授業 ぼくの命があるうちに』ランディ・パウシュ、ジェフリー・ザスロー
評者:日向郁

- 2012/10/18[新着書評]
『イタリア人と日本人、どっちがバカ?』ファブリツィオ・グラッセッリ
評者:相川藍

- 2012/10/17[イベントレポ]
ミステリー酒場スペシャル ローレンス・ブロック酒場Part1

- 2012/10/16[イベントレポ]
ブックレビューLIVE:杉江VS米光のどっちが売れるか!?

- 2012/10/15[イベントレポ]
ミステリ酒場スペシャル ローレンス・ブロック酒場三連発 PART2~泥棒バーニー、殺し屋ケラー編&ブロックおもてなし対策会議~

- 2012/10/15[新着書評]
『犬とハモニカ』江國香織
評者:長坂陽子

- 2012/10/10[新着書評]
『Papa told me cocohana ver.1 丘は花でいっぱい』榛野なな恵
評者:千三屋

- 2012/10/08[イベントレポ]
“その日”が来てからでは遅すぎる! あなたの知らないお葬式のすべて?ボッタクリの秘密から納得のエコ葬儀プランまで

- 2012/10/03[新着書評]
『青い脂』ウラジーミル・ソローキン
評者:藤井勉

- 2012/10/02[イベントレポ]
松本尚久さん、落語の楽しみ方を教えてください!

- 2012/10/01[新着書評]
『ヴァンパイア』岩井俊二
評者:長坂陽子

- 2012/09/25[新着書評]
『鬼談百景』小野不由美
評者:挟名紅治

- 2012/09/24[新着書評]
『ここは退屈迎えに来て』山内マリコ
評者:長坂陽子

- 2012/09/18[新着書評]
『最初の人間』アルベール・カミュ
評者:新藤純子

- 2012/09/14[新着書評]
『その日東京駅五時二十五分発』西川美和
評者:相川藍

- 2012/09/13[新着書評]
『無分別』オラシオ・カステジャーノス・モヤ
評者:藤井勉

- 2012/09/12[新着書評]
『鷲たちの盟約』(上下)アラン・グレン
評者:大谷暁生

- 2012/09/11[新着書評]
『ラブ・イズ・ア・ミックステープ』ロブ・シェフィールド
評者:日向郁

- 2012/09/10[新着書評]
『嵐のピクニック』本谷有希子
評者:長坂陽子

- 2012/09/07[新着書評]
『本当の経済の話をしよう』若田部昌澄、栗原裕一郎
評者:藤井勉

- 2012/09/05[新着書評]
『ひらいて』綿矢りさ
評者:長坂陽子

- 2012/09/04[新着書評]
『失脚/巫女の死 デュレンマット傑作選』フリードリヒ・デュレンマット
評者:藤井勉

- 2012/09/03[新着書評]
『かくも水深き不在』竹本健治
評者:蔓葉信博

- 2012/08/31[新着書評]
『わたしが眠りにつく前に』SJ・ワトソン
評者:長坂陽子

- 2012/08/28[新着書評]
『芸術実行犯』Chim↑Pom(チン↑ポム)
評者:相川藍

- 2012/08/27[新着書評]
『ぼくは勉強ができない』山田詠美
評者:姉崎あきか

- 2012/08/16[新着書評]
『オカルト 現れるモノ、隠れるモノ、見たいモノ』森達也
評者:長坂陽子

- 2012/08/10[新着書評]
『セックスなんか興味ない』きづきあきら サトウナンキ
評者:大谷暁生

- 2012/08/08[新着書評]
『深い疵』ネレ・ノイハウス
評者:挟名紅治

- 2012/08/07[新着書評]
【連載】 蔓葉信博「週末、たまにはビジネス書を」
第4回 小林直樹『ソーシャルリスク』 評者:蔓葉信博

- 2012/08/03[新着書評]
『はまむぎ』レーモン・クノー
評者:藤井勉

- 2012/08/02[新着書評]
『清須会議』三谷幸喜
評者:千三屋

- 2012/07/31[新着書評]
『岡崎京子の仕事集』岡崎京子(著)増渕俊之(編)
評者:相川藍

- 2012/07/28[新着書評]
『ことばの食卓』武田百合子
評者:杉江松恋

- 2012/07/18[新着書評]
『図説 死因百科』マイケル・ラルゴ
評者:大谷暁生

- 2012/07/13[新着書評]
『最果てアーケード』
小川洋子
評者:長坂陽子

- 2012/07/12[新着書評]
『なぜ戒名を自分でつけてもいいのか』橋爪大三郎
評者:千三屋

- 2012/07/05[新着書評]
『少年は残酷な弓を射る』(上・下)
ライオネル・シュライヴァー
評者:長坂陽子

- 2012/07/04[新着書評]
『未解決事件 グリコ・森永事件~捜査員300人の証言』NHKスペシャル取材班
評者:挟名紅治

- 2012/07/02[新着書評]
『女が嘘をつくとき』リュドミラ・ウリツカヤ
評者:藤井勉

- 2012/06/29[新着書評]
連載 蔓葉信博「週末、たまにはビジネス書を」
第3回 三浦展『第四の消費』 蔓葉信博

- 2012/06/27[新着書評]
『シフォン・リボン・シフォン』近藤史恵
評者:相川藍

- 2012/06/26[新着書評]
『湿地』アーナルデュル・インドリダソン
大谷暁生

- 2012/06/20[新着書評]
『彼女の存在、その破片』野中柊
長坂陽子

- 2012/06/15[新着書評]
『新人警官の掟』フェイ・ケラーマン
日向郁

- 2012/06/14[新着書評]
『俳優と超人形』ゴードン・クレイグ
千三屋

- 2012/06/13[新着書評]
『毒婦。 木嶋佳苗100日裁判傍聴記』北原みのり
長坂陽子

- 2012/06/12[新着書評]
『WOMBS』白井弓子
大谷暁生

- 2012/06/11[新着書評]
『21世紀の世界文学30冊を読む』都甲幸治
藤井勉

- 2012/06/08[新着書評]
『愛について』白岩玄
評者:相川藍

- 2012/06/06[新着書評]
『柔らかな犀の角ー山崎努の読書日記』山崎努
挟名紅治

- 2012/06/04[新着書評]
『夜をぶっとばせ』井上荒野
長坂陽子

- 2012/06/01[新着書評]
「七夜物語』川上弘美
長坂陽子

- 2012/05/23[新着書評]
「ピントがボケる音 OUT OF FOCUS, OUT OF SOUND』安田兼一
藤井勉

- 2012/05/21[新着書評]
「飼い慣らすことのできない幻獣たち」
『幻獣辞典』ホルヘ・ルイス・ボルヘス
藤田祥平

- 2012/05/16[新着書評]
連載「長坂陽子 ロマンスの神様願いを叶えて第18回」
「その名は自己満足」 長坂陽子

- 2012/03/30[新着書評]
連載「長坂陽子 ロマンスの神様願いを叶えて第17回」
「そのプライドが邪魔をする」 長坂陽子

- 2012/02/28[新着書評]
連載「長坂陽子 ロマンスの神様願いを叶えて第16回」
「恋のリスクマネジメント」 長坂陽子

- 2012/02/15[新着書評]
連載「長坂陽子 ロマンスの神様願いを叶えて第15回」
「非華奢女子の生きる道」 長坂陽子

- 2012/02/02[新着書評]
連載「長坂陽子 ロマンスの神様願いを叶えて第14回」
「パターン破りの効用」 長坂陽子

- 2012/01/31[新着書評]
『最高に美しい住宅をつくる方法』彦根明
評者:相川藍

- 2012/01/20[新着書評]
『ペット・サウンズ』ジム・フジーリ
評者:藤井勉

- 2012/01/17[新着書評]
連載「長坂陽子 ロマンスの神様願いを叶えて第13回」
胸だけ見ててもモテ期はこない 長坂陽子

- 2012/01/11[新着書評]
連載「長坂陽子 ロマンスの神様願いを叶えて第12回」
「恋で美しくなる」は本当か 長坂陽子

- 2012/01/10[新着書評]
「旧式のプライバシー」
『大阪の宿』水上滝太郎
藤田祥平
Internet Explorerをご利用の場合はバージョン6以上でご覧ください。

















