トーベ・ヤンソン短篇集

フィンランドの作家、トーベ・ヤンソンに「往復書簡」という作品がある。その名のとおり書簡体の小説だが、題名とは異なって「往復」はしない。小説は、十三歳の少女タミコ・アツミがヤンソンに出した手紙が(おそらくは)年代順に並べられた形で構成されており、ヤンソンが出した返信の内容はタミコが綴った文面から察する以外にないのである。
作家に憧れ、いつかその家を訪れたいと願うタミコに、ヤンソンが贈った言葉も。
――ヤンソンさん
すばらしい手紙をありがとうございました。
フィンランドでは、森は大きく、海も大きいけれども、
あなたの家はとても小さいこと、よくわかりました。
作家の書いた本のなかでこそ作家と出会うべきだ、
というのはすてきな考えです。
一日じゅう、勉強をしています。
元気で、長生きしてください。
あなたのタミコ
タミコ・アツミが実在するか、この逸話が現実にあったものかどうか、といったことはひとまず関心の埒外です。ヤンソンがそのとても小さい家の中で(一九六〇年代以降の彼女は、フィンランド湾の沖合いに浮かぶ孤島で暮らしていた)、どのように大きな世界を作り上げていたのか。そのことに私は興味を引かれるのである。
この「往復書簡」はちくま文庫『トーベ・ヤンソン短篇集』に収録されているので簡単に読むことができる。いや、言いなおしましょう。簡単に手に取ることができる。読むのはあまり簡単ではないかもしれない。ヤンソンの小説はぎりぎりまで言葉が切り詰められた文体で書かれており(だから読者は、かなりの部分を自分の想像で補って読むことを求められる。それが心地よいのだが)、あらすじを追いかけられないと不安になるタイプの読者にはややとっつきにくい印象があるからだ。訳者あとがきにあるとおり、〈子ども時代〉〈創作〉〈奇妙な体験〉〈旅〉〈老いと死の予感〉という五つの主題に沿って各作品は分類することができ、それらがグラデーションを描くように配列されている。
もっともとっつきやすいのは〈旅〉の主題を振り当てられた作品群だろう。物品の取り違えや、些細な感情のもつれから紛糾する事態を描いたものが多いのだが、「見知らぬ旅」「軽い手荷物の旅」の二篇は故・浅倉久志の〈ユーモア・スケッチ傑作選〉に採ってもいいような作品だ。「汽車の旅」は、二十年前の学生時代に級友のヒーローだった男と主人公が車内で偶然の再会を果たす話で、後半にいくにしたがってヤンソンの筆は「巻き」を入れ始め、最後はゼンマイの切れたからくり細工のようにぱたりと終わる。あまりにもあっさりした落ちなので作者の意図を汲み取りにくいのだが、話の前半で主人公が、その級友を崇拝するあまり彼と自分を登場させたロマン小説を書いていた、というエピソードが書かれていたことを思い出すと、なんとなく察せられる(ような気がします)。ちなみに主人公は、その小説を書き進めることができず、草稿の処分に困った挙句、ついにスーツケースに入れて海に投じることを選択するのである。
――スーツケースは海の底まで沈み、ゆっくりと時間をかけて縫い目がゆるんでいく。戦時中の品で革を模した厚紙製だから。やがて表表紙から裏表紙までびっしりと埋められたノートが、一冊また一冊と港の外に流れていく。うまく風向きが変われば、ノートはれヴァルまで、あるいはさらに遠くまで運ばれていくかもしれない。
海中のスーツケースという奇矯なイメージもさることながら、ノートに記された物語が流れ去っていくという結果にも興味を惹かれる。紙の上に定着された物語が本として世間に広まっていく中で、作者自身からは切り離され遠い存在になっていくということの隠喩に感じられるからだ。
少し脱線するが、私は最近「ハヤカワ・ミステリマガジン」二〇一〇年十一月号の北欧ミステリ特集に「トーベ・ヤンソンの半分は不安でできている」という文章を寄稿した(誰にも指摘されなかったが、この題名は某医薬品のセールスコピーのパロディです)。童話として読まれることが多い〈ムーミン谷〉の物語に、実は彗星が接近して世界が滅亡しかけるなど、〈災害小説〉の側面が備わっていることを紹介したもので、シリーズ後期の作品『ムーミンパパ海へ行く』(講談社文庫他)がサスペンス小説として如何に優れているか、を読者に伝えたくて書いた。その際に字数が足りず、シリーズの実質的な最終作『ムーミン谷の十一月』(同)に触れることができなかったのである。ちょっとそれについて書かせてもらいたい。
前作『海へ行く』でムーミントロールの一家は灯台がある孤島へと移住してしまった。『十一月』は、そうした理由で主が不在になったムーミン家に、ひとびとが集まってくるという話だ。象徴的なのはホムサ・トフトで、彼はしあわせなムーミン一家の登場する物語を自分で作って自分にしてきかせるのが大好きなのである。だが彼は、空想の中でムーミン家に近づくことはできても、肝心の屋内にまで入り込めたことがない。本当に戸口のところまで接近しながら、どうしてもその先に踏み込むことができなかったのだ。ついにホムサは決心をして、実際にムーミン家を訪ねようと旅に出る。このように、ムーミン家にやってくるのは、そこに来れば何かが解決する、ムーミン一家に会えば自分の人生がなんとかなる、といった思い込みを抱えた者ばかりなのである。目的地で顔を合わせた〈ムーミン・ファン〉たちは、なんと不在の一家の代わりにそこで暮らし始める。あたかも、自分たちが新たなムーミン一家であるかのように。
物語を未読の方のために結末を書くのは控える。しかし私は、この小説をヤンソンにとっての〈解放〉の作品だと思って読んだ。ムーミン一家をヤンソンから解放してやったのであり、逆にヤンソンがムーミン一家から解放されたということでもある。
訳者あとがきに頼って書くが、『トーベ・ヤンソン短篇集』に収録された作品は、ほとんどが〈アフター・ムーミン〉の時期に属するものだ。実は、原稿を書かせてくれた「ハヤカワ・ミステリマガジン」には申し訳ないのだが、「ミステリー好きの読者をヤンソンに誘導する」意図で原稿を書くべくしてこの短篇集の再読を始めたにも関わらず、本を読みながら私は自分の心が「ミステリーから離れていく」のを感じた。いや、その言い方はミステリーに失礼か。もっと正確にいえば、小説ではなく、小説の外側に広がっている、もしくは広がっていると見做されている、小説自体ではない小説の要素から、である。そこから離れ、これをなんのために読んでいるか、という当初の読書の目的からも離れ、私はヤンソンの短篇の一つ一つに没頭していった。もっとエロチックな表現を使えば、悩殺された、と言ってもいいかもしれない。先に挙げた、訳者が設定した五つの主題も、もちろん作品世界のドアをノックするための便宜的なものだろう。ヤンソンの小説を読んでいる、ということ自体に淫することができれば、この上ない快楽を本書は与えてくれる。
いくつかお気に入りの短篇を挙げておきたい。まず、文句なくお薦めしたいのが「ショッピング」である。謎の原因によって荒廃し、人気の絶えた街でバリケードを築いて暮らす夫婦の短い物語だ。彼らのほかに〈あいつら〉と呼ばれる者たちが街にはいるらしいのだが、その正体は一切明かされない。読んでいて、猛烈な不安感を掻き立てられる作品なのである。そうだ、この宙吊りにされる感覚だ。この不安感を味わいたいがために、私はおそらくヤンソンの小説を読むのである。「嵐」というのも大好きな作品で、ある女性が壮絶な嵐の中で一人夜を過ごす、というだけの物語である。これも省略の技法ゆえに、最後が意外極まりない落ちになっている。吹きすさぶ嵐の後に訪れたのは、こんな光景だったのだ。
――翌朝の七時頃、風がやんで雪が街に落ちてきて、街路にも屋根にも彼女の寝室にも降りつもる。彼女がめざめると、寝室はどこまでも白く、すばらしく美しかった。
ヤンソンが自身の芸術観を表わしたものか、または芸術家の典型についての皮肉を示したものか、その判断は私にはできないのだが、〈創作〉もしくは〈創作者〉を主題に据えた作品もある。「自然のなかの芸術」はモダンアートの開かれた解釈可能性について楽しく(美術館の庭園内に違法侵入した夫婦と警備員の会話の形で)書いたものだ。また、留学中の創作者の孤独な生活を描く「絵」は、画家が父の元から旅立ち、またその父の元に帰り着くまでを早回しのフィルムのように描いた、緊張と緩和のテンポが素晴らしい作品である。子供時代のことを書いたと思われる「森」も、創作という行為によって始原的なイメージの広がりを限定的に切り取り、作品として定着させることへの畏れを描いた作品として私は読んだ。また、偏執狂的な熱情を書いたいくつかの作品も〈創作〉に関するものとして読むことはできるだろう。「聴く女」は、人生の終焉を意識するようになった女性が、一族郎党を中心とした壮大な人間地図を書く話だ。
どこを切っても創作という行為についての狂おしいまでの熱情を感じる。冷え冷えとした空気の中に、あたりを制圧するような威厳を漂わせながら、そうした意志が流れていくことを思う。凛とした言葉の数々に触れ、世界の広がりを感じるのだ。
冒頭に挙げた「往復書簡」もまた、ヤンソンらしき飛躍と断絶を伴って終了する。最後にヤンソンの下に届けられたタミコの手紙は、こんな書き出しで始まっている。
――ヤンソンさん
一日じゅう、雪がふりました。
雪について書けるようになるでしょう――
新着情報
-

- 2013/08/16[新着書評]
『きことわ』朝吹真理子
評者:千三屋
-

- 2013/08/15[新着書評]
『テルマエ・ロマエⅥ』ヤマザキマリ/「1~3巻は大傑作、4~6巻は残念な出来」
評者:新藤純子
-

- 2013/06/19[新着書評]
『高円寺 古本酒場ものがたり』狩野俊
評者:千三屋

- 2013/05/12[新着書評]
『フィフティ・シェイズ・ダーカー(上・下)』ELジェイムズ
評者:日向郁

- 2013/04/04[新着書評]
『クラウド・アトラス』デイヴィッド・ミッチェル
評者:千三屋

- 2013/02/18[新着書評]
『はぶらし』近藤史恵
評者:日向郁

- 2013/01/31[新着書評]
『知的唯仏論』宮崎哲弥・呉智英
評者:千三屋

- 2013/01/18[新着書評]
『秋田寛のグラフィックデザイン』アキタ・デザイン・カン
評者:千三屋

- 2013/01/17[新着書評]
『空白を満たしなさい』平野啓一郎
評者:長坂陽子

- 2013/01/15[新着書評]
『箱根駅伝を歩く』泉麻人
評者:千三屋

- 2013/01/11[新着書評]
『世界が終わるわけではなく』ケイト・アトキンソン
評者:藤井勉

- 2012/12/19[新着書評]
『デザインの本の本』秋田寛
評者:千三屋

- 2012/11/28[新着書評]
『ニール・ヤング自伝I』ニール・ヤング
評者:藤井勉

- 2012/11/22[新着書評]
『日本人はなぜ「黒ブチ丸メガネ」なのか』友利昴
評者:新藤純子

- 2012/11/21[新着書評]
『私にふさわしいホテル』柚木麻子
評者:長坂陽子

- 2012/11/15[新着書評]
『格差と序列の心理学 平等主義のパラドクス』池上知子
評者:新藤純子
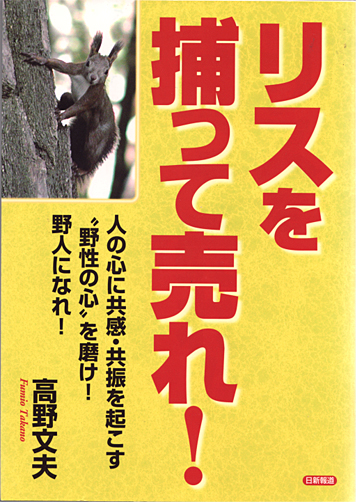
- 2012/11/09[イベントレポ]
兼業古本屋のできるまで。とみさわさん、なにをやってんすか

- 2012/11/08[新着書評]
『機龍警察 暗黒市場』月村了衛
評者:大谷暁生

- 2012/11/02[新着書評]
『なしくずしの死』L-F・セリーヌ
評者:藤田祥平

- 2012/10/31[新着書評]
『エコー・メイカー』リチャード・パワーズ
評者:藤井勉

- 2012/10/30[新着書評]
『文体練習』レーモン・クノー
評者:藤田祥平

- 2012/10/25[新着書評]
『生きのびるための建築』石山修武
評者:千三屋

- 2012/10/24[新着書評]
『占領都市 TOKYO YEAR ZERO Ⅱ』デイヴィッド・ピース
評者:大谷暁生

- 2012/10/19[新着書評]
『最後の授業 ぼくの命があるうちに』ランディ・パウシュ、ジェフリー・ザスロー
評者:日向郁

- 2012/10/18[新着書評]
『イタリア人と日本人、どっちがバカ?』ファブリツィオ・グラッセッリ
評者:相川藍

- 2012/10/17[イベントレポ]
ミステリー酒場スペシャル ローレンス・ブロック酒場Part1

- 2012/10/16[イベントレポ]
ブックレビューLIVE:杉江VS米光のどっちが売れるか!?

- 2012/10/15[イベントレポ]
ミステリ酒場スペシャル ローレンス・ブロック酒場三連発 PART2~泥棒バーニー、殺し屋ケラー編&ブロックおもてなし対策会議~

- 2012/10/15[新着書評]
『犬とハモニカ』江國香織
評者:長坂陽子

- 2012/10/10[新着書評]
『Papa told me cocohana ver.1 丘は花でいっぱい』榛野なな恵
評者:千三屋

- 2012/10/08[イベントレポ]
“その日”が来てからでは遅すぎる! あなたの知らないお葬式のすべて?ボッタクリの秘密から納得のエコ葬儀プランまで

- 2012/10/03[新着書評]
『青い脂』ウラジーミル・ソローキン
評者:藤井勉

- 2012/10/02[イベントレポ]
松本尚久さん、落語の楽しみ方を教えてください!

- 2012/10/01[新着書評]
『ヴァンパイア』岩井俊二
評者:長坂陽子

- 2012/09/25[新着書評]
『鬼談百景』小野不由美
評者:挟名紅治

- 2012/09/24[新着書評]
『ここは退屈迎えに来て』山内マリコ
評者:長坂陽子

- 2012/09/18[新着書評]
『最初の人間』アルベール・カミュ
評者:新藤純子

- 2012/09/14[新着書評]
『その日東京駅五時二十五分発』西川美和
評者:相川藍

- 2012/09/13[新着書評]
『無分別』オラシオ・カステジャーノス・モヤ
評者:藤井勉

- 2012/09/12[新着書評]
『鷲たちの盟約』(上下)アラン・グレン
評者:大谷暁生

- 2012/09/11[新着書評]
『ラブ・イズ・ア・ミックステープ』ロブ・シェフィールド
評者:日向郁

- 2012/09/10[新着書評]
『嵐のピクニック』本谷有希子
評者:長坂陽子

- 2012/09/07[新着書評]
『本当の経済の話をしよう』若田部昌澄、栗原裕一郎
評者:藤井勉

- 2012/09/05[新着書評]
『ひらいて』綿矢りさ
評者:長坂陽子

- 2012/09/04[新着書評]
『失脚/巫女の死 デュレンマット傑作選』フリードリヒ・デュレンマット
評者:藤井勉

- 2012/09/03[新着書評]
『かくも水深き不在』竹本健治
評者:蔓葉信博

- 2012/08/31[新着書評]
『わたしが眠りにつく前に』SJ・ワトソン
評者:長坂陽子

- 2012/08/28[新着書評]
『芸術実行犯』Chim↑Pom(チン↑ポム)
評者:相川藍

- 2012/08/27[新着書評]
『ぼくは勉強ができない』山田詠美
評者:姉崎あきか

- 2012/08/16[新着書評]
『オカルト 現れるモノ、隠れるモノ、見たいモノ』森達也
評者:長坂陽子

- 2012/08/10[新着書評]
『セックスなんか興味ない』きづきあきら サトウナンキ
評者:大谷暁生

- 2012/08/08[新着書評]
『深い疵』ネレ・ノイハウス
評者:挟名紅治

- 2012/08/07[新着書評]
【連載】 蔓葉信博「週末、たまにはビジネス書を」
第4回 小林直樹『ソーシャルリスク』 評者:蔓葉信博

- 2012/08/03[新着書評]
『はまむぎ』レーモン・クノー
評者:藤井勉

- 2012/08/02[新着書評]
『清須会議』三谷幸喜
評者:千三屋

- 2012/07/31[新着書評]
『岡崎京子の仕事集』岡崎京子(著)増渕俊之(編)
評者:相川藍

- 2012/07/28[新着書評]
『ことばの食卓』武田百合子
評者:杉江松恋

- 2012/07/18[新着書評]
『図説 死因百科』マイケル・ラルゴ
評者:大谷暁生

- 2012/07/13[新着書評]
『最果てアーケード』
小川洋子
評者:長坂陽子

- 2012/07/12[新着書評]
『なぜ戒名を自分でつけてもいいのか』橋爪大三郎
評者:千三屋

- 2012/07/05[新着書評]
『少年は残酷な弓を射る』(上・下)
ライオネル・シュライヴァー
評者:長坂陽子

- 2012/07/04[新着書評]
『未解決事件 グリコ・森永事件~捜査員300人の証言』NHKスペシャル取材班
評者:挟名紅治

- 2012/07/02[新着書評]
『女が嘘をつくとき』リュドミラ・ウリツカヤ
評者:藤井勉

- 2012/06/29[新着書評]
連載 蔓葉信博「週末、たまにはビジネス書を」
第3回 三浦展『第四の消費』 蔓葉信博

- 2012/06/27[新着書評]
『シフォン・リボン・シフォン』近藤史恵
評者:相川藍

- 2012/06/26[新着書評]
『湿地』アーナルデュル・インドリダソン
大谷暁生

- 2012/06/20[新着書評]
『彼女の存在、その破片』野中柊
長坂陽子

- 2012/06/15[新着書評]
『新人警官の掟』フェイ・ケラーマン
日向郁

- 2012/06/14[新着書評]
『俳優と超人形』ゴードン・クレイグ
千三屋

- 2012/06/13[新着書評]
『毒婦。 木嶋佳苗100日裁判傍聴記』北原みのり
長坂陽子

- 2012/06/12[新着書評]
『WOMBS』白井弓子
大谷暁生

- 2012/06/11[新着書評]
『21世紀の世界文学30冊を読む』都甲幸治
藤井勉

- 2012/06/08[新着書評]
『愛について』白岩玄
評者:相川藍

- 2012/06/06[新着書評]
『柔らかな犀の角ー山崎努の読書日記』山崎努
挟名紅治

- 2012/06/04[新着書評]
『夜をぶっとばせ』井上荒野
長坂陽子

- 2012/06/01[新着書評]
「七夜物語』川上弘美
長坂陽子

- 2012/05/23[新着書評]
「ピントがボケる音 OUT OF FOCUS, OUT OF SOUND』安田兼一
藤井勉

- 2012/05/21[新着書評]
「飼い慣らすことのできない幻獣たち」
『幻獣辞典』ホルヘ・ルイス・ボルヘス
藤田祥平

- 2012/05/16[新着書評]
連載「長坂陽子 ロマンスの神様願いを叶えて第18回」
「その名は自己満足」 長坂陽子

- 2012/03/30[新着書評]
連載「長坂陽子 ロマンスの神様願いを叶えて第17回」
「そのプライドが邪魔をする」 長坂陽子

- 2012/02/28[新着書評]
連載「長坂陽子 ロマンスの神様願いを叶えて第16回」
「恋のリスクマネジメント」 長坂陽子

- 2012/02/15[新着書評]
連載「長坂陽子 ロマンスの神様願いを叶えて第15回」
「非華奢女子の生きる道」 長坂陽子

- 2012/02/02[新着書評]
連載「長坂陽子 ロマンスの神様願いを叶えて第14回」
「パターン破りの効用」 長坂陽子

- 2012/01/31[新着書評]
『最高に美しい住宅をつくる方法』彦根明
評者:相川藍

- 2012/01/20[新着書評]
『ペット・サウンズ』ジム・フジーリ
評者:藤井勉

- 2012/01/17[新着書評]
連載「長坂陽子 ロマンスの神様願いを叶えて第13回」
胸だけ見ててもモテ期はこない 長坂陽子

- 2012/01/11[新着書評]
連載「長坂陽子 ロマンスの神様願いを叶えて第12回」
「恋で美しくなる」は本当か 長坂陽子

- 2012/01/10[新着書評]
「旧式のプライバシー」
『大阪の宿』水上滝太郎
藤田祥平
Internet Explorerをご利用の場合はバージョン6以上でご覧ください。
















