本の読み方─墓場の書斎に閉じこもる

帯に大きく「本は崩れず。」とある。草森紳一は、2008年に逝去、残された多くの蔵書は主人を失い、途方にくれ、崩れようもないのか。
本書『本の読み方』は、雑誌「ノーサイド」に連載されたもので、タイトルもそのまま使われている。「ノーサイド」は1991年から96年にかけて文藝春秋社から出ていた雑誌で、「黄金の読書」「読書名人伝」「キネマの美女」「ビートルズ同時代」など、数々の傑作を残した伝説の雑誌で、今でもその内容のすばらしさが語り継がれている。連載は、他に、武藤康史の「文学鶴亀」、川本三郎の「君美わしく」などがあった。
草森紳一は本書では、読書そのものというのではなく、読む場所、読む姿勢などを、色々な読書名人を例にあげて、紹介し解説している。そのなかで最も印象的だったのは、経済学者、河上肇の読書生活。河上肇は、書斎の中での優雅な読書生活(私の想像)から一転、獄中での限られた読書生活を経験する。獄中では昼も夜も作業があるので、読書時間は一時間二十分ほどではなかったか、と草森氏は考える。
河上肇は獄中で本を読む場所を選べない。彼は毎日便器の上に胡座して読んだという。作業がきつくて、せっかく借り出した『八宗綱要講義』や、富士川游の『真実の宗教』だけど、なかなか読む気にならないというのだ。それで『陶淵明集』や『老子』などの方に読書が傾いていったという。奥さんが差し入れのため、神田の古本屋街に出入りする様子も紹介されているが、河上肇を支える姿が美しい。
草森紳一は、読書についても、彼らしい考えを持っている。読書は中断が面白いという。読書は、中断の連続であり、別な所へ引きずりこまれたり、考え込んだりする、そこのところがいいのだというのだ。草森氏にとっては、これこそが一日たりとも本を手から離せない大きな理由なのだそうだ。
机の上に本をひろげて読むのと、寝転んで読むのとでは、どちらが疲れるか、という一見どうでもいいようなことにも草森氏はこだわっている。本を手で支えないでいい、本を机にひろげる方が楽なように思えるが、実際は寝転んで読む方が楽なのだと述べる。草森氏は家で本を読む場合、百パーセント寝転んで読んでいるのだそうだ。
このところでは、坂口安吾の読書姿勢に触れている。ちょっと分かりにくいのは、寝転んで読むのは自分の経験からも事実疲れないと書きながらも、安吾が浴衣がけで寝転び仰向けで読んでいるのを、もっとも疲れるスタイルだと書いているところだ。ということは、草森紳一は、うつ伏せになって読んでいたということなのだろう。読むときの様々なスタイルが伺えて面白い。
坂口安吾の本を読むスタイルについて、草森紳一の観察は鋭く細かい。
【この時の安吾の本(雑誌)のもちかたが、なんとも面白い。右の手は、ヒョンと雑誌を上から洗濯バサミで挟むかたちで、残りの左手は、雑誌の中央へ当てがっている。絵からでは見えないが、その五本の指はみな開いているはずだ。もちろん、雑誌を安定させるためで、頁をめくる時は、この文鎮がわりに中央へ置かれた手の「指」の一本か二本かが、ごそごそとうごめくはずである。】
この引用文はよく草森紳一を表していると思う。本を読むことに関係するあらゆることへの草森紳一の眼差しが感じ取れるではないか。本の重量を支えもってくれる人間の「手」、その動き。読書とは手の運動なのである、というのも草森紳一の言葉である。
この『本の読み方』には、他にも魅力ある読書生活が紹介されているが、読んでいるうち、読みたい本、読み返したい本が、次から次へと思い浮かび楽しむことができた。例えば、寺田寅彦のエッセイ。岩波文庫(ワイド版が読みやすい)の『柿の種』でもいいし、「ちくま日本文学」でもいいのだが、読み返したい。河上肇の『自叙伝』も快著だ。波瀾万丈であった生涯を語りつくしたもので、むさぼるように読んだ思い出がある。本書で、内田魯庵に触れた所があったが、『貘の舌』も、ウェッジ文庫で読み返そう。
私がまだ読んでいない本で興味深く思ったのは、木村荘八の日記だ。全集の八巻に収録されているらしい。木村荘八は一年中、本の片付けばかりしていたというが、それも面白そうだ。あと、伏見冲敬訳の中国の古い小説『肉蒲団』。
装幀と挿絵が武井武雄だという。内容が内容なので、どのような挿絵を描いたのか、とても興味があります。
おすすめ本書評・紹介書籍
-
- 本の読み方─墓場の書斎に閉じこもる
河出書房新社 [書評・ブックガイド・読書論] 国内
2009.08 版型:B6
価格:1,680円(税込)
>>詳細を見る
『本の読み方』を読んでいるうちに連想される…寺田寅彦・河上肇・内田魯庵
-
- ちくま日本文学 34 寺田寅彦
筑摩書房 [随筆・エッセイ] 国内
2009.04 版型:文庫
価格:924円(税込)
>>詳細を見る
新着情報
-

- 2013/08/16[新着書評]
『きことわ』朝吹真理子
評者:千三屋
-

- 2013/08/15[新着書評]
『テルマエ・ロマエⅥ』ヤマザキマリ/「1~3巻は大傑作、4~6巻は残念な出来」
評者:新藤純子
-

- 2013/06/19[新着書評]
『高円寺 古本酒場ものがたり』狩野俊
評者:千三屋

- 2013/05/12[新着書評]
『フィフティ・シェイズ・ダーカー(上・下)』ELジェイムズ
評者:日向郁

- 2013/04/04[新着書評]
『クラウド・アトラス』デイヴィッド・ミッチェル
評者:千三屋

- 2013/02/18[新着書評]
『はぶらし』近藤史恵
評者:日向郁

- 2013/01/31[新着書評]
『知的唯仏論』宮崎哲弥・呉智英
評者:千三屋

- 2013/01/18[新着書評]
『秋田寛のグラフィックデザイン』アキタ・デザイン・カン
評者:千三屋

- 2013/01/17[新着書評]
『空白を満たしなさい』平野啓一郎
評者:長坂陽子

- 2013/01/15[新着書評]
『箱根駅伝を歩く』泉麻人
評者:千三屋

- 2013/01/11[新着書評]
『世界が終わるわけではなく』ケイト・アトキンソン
評者:藤井勉

- 2012/12/19[新着書評]
『デザインの本の本』秋田寛
評者:千三屋

- 2012/11/28[新着書評]
『ニール・ヤング自伝I』ニール・ヤング
評者:藤井勉

- 2012/11/22[新着書評]
『日本人はなぜ「黒ブチ丸メガネ」なのか』友利昴
評者:新藤純子

- 2012/11/21[新着書評]
『私にふさわしいホテル』柚木麻子
評者:長坂陽子

- 2012/11/15[新着書評]
『格差と序列の心理学 平等主義のパラドクス』池上知子
評者:新藤純子
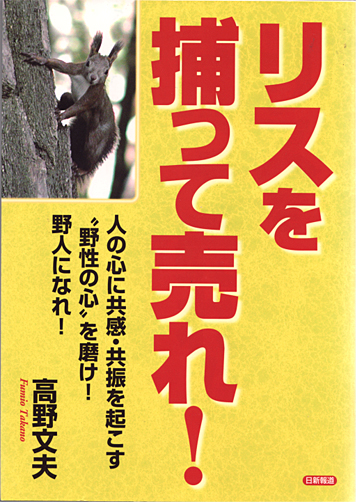
- 2012/11/09[イベントレポ]
兼業古本屋のできるまで。とみさわさん、なにをやってんすか

- 2012/11/08[新着書評]
『機龍警察 暗黒市場』月村了衛
評者:大谷暁生

- 2012/11/02[新着書評]
『なしくずしの死』L-F・セリーヌ
評者:藤田祥平

- 2012/10/31[新着書評]
『エコー・メイカー』リチャード・パワーズ
評者:藤井勉

- 2012/10/30[新着書評]
『文体練習』レーモン・クノー
評者:藤田祥平

- 2012/10/25[新着書評]
『生きのびるための建築』石山修武
評者:千三屋

- 2012/10/24[新着書評]
『占領都市 TOKYO YEAR ZERO Ⅱ』デイヴィッド・ピース
評者:大谷暁生

- 2012/10/19[新着書評]
『最後の授業 ぼくの命があるうちに』ランディ・パウシュ、ジェフリー・ザスロー
評者:日向郁

- 2012/10/18[新着書評]
『イタリア人と日本人、どっちがバカ?』ファブリツィオ・グラッセッリ
評者:相川藍

- 2012/10/17[イベントレポ]
ミステリー酒場スペシャル ローレンス・ブロック酒場Part1

- 2012/10/16[イベントレポ]
ブックレビューLIVE:杉江VS米光のどっちが売れるか!?

- 2012/10/15[イベントレポ]
ミステリ酒場スペシャル ローレンス・ブロック酒場三連発 PART2~泥棒バーニー、殺し屋ケラー編&ブロックおもてなし対策会議~

- 2012/10/15[新着書評]
『犬とハモニカ』江國香織
評者:長坂陽子

- 2012/10/10[新着書評]
『Papa told me cocohana ver.1 丘は花でいっぱい』榛野なな恵
評者:千三屋

- 2012/10/08[イベントレポ]
“その日”が来てからでは遅すぎる! あなたの知らないお葬式のすべて?ボッタクリの秘密から納得のエコ葬儀プランまで

- 2012/10/03[新着書評]
『青い脂』ウラジーミル・ソローキン
評者:藤井勉

- 2012/10/02[イベントレポ]
松本尚久さん、落語の楽しみ方を教えてください!

- 2012/10/01[新着書評]
『ヴァンパイア』岩井俊二
評者:長坂陽子

- 2012/09/25[新着書評]
『鬼談百景』小野不由美
評者:挟名紅治

- 2012/09/24[新着書評]
『ここは退屈迎えに来て』山内マリコ
評者:長坂陽子

- 2012/09/18[新着書評]
『最初の人間』アルベール・カミュ
評者:新藤純子

- 2012/09/14[新着書評]
『その日東京駅五時二十五分発』西川美和
評者:相川藍

- 2012/09/13[新着書評]
『無分別』オラシオ・カステジャーノス・モヤ
評者:藤井勉

- 2012/09/12[新着書評]
『鷲たちの盟約』(上下)アラン・グレン
評者:大谷暁生

- 2012/09/11[新着書評]
『ラブ・イズ・ア・ミックステープ』ロブ・シェフィールド
評者:日向郁

- 2012/09/10[新着書評]
『嵐のピクニック』本谷有希子
評者:長坂陽子

- 2012/09/07[新着書評]
『本当の経済の話をしよう』若田部昌澄、栗原裕一郎
評者:藤井勉

- 2012/09/05[新着書評]
『ひらいて』綿矢りさ
評者:長坂陽子

- 2012/09/04[新着書評]
『失脚/巫女の死 デュレンマット傑作選』フリードリヒ・デュレンマット
評者:藤井勉

- 2012/09/03[新着書評]
『かくも水深き不在』竹本健治
評者:蔓葉信博

- 2012/08/31[新着書評]
『わたしが眠りにつく前に』SJ・ワトソン
評者:長坂陽子

- 2012/08/28[新着書評]
『芸術実行犯』Chim↑Pom(チン↑ポム)
評者:相川藍

- 2012/08/27[新着書評]
『ぼくは勉強ができない』山田詠美
評者:姉崎あきか

- 2012/08/16[新着書評]
『オカルト 現れるモノ、隠れるモノ、見たいモノ』森達也
評者:長坂陽子

- 2012/08/10[新着書評]
『セックスなんか興味ない』きづきあきら サトウナンキ
評者:大谷暁生

- 2012/08/08[新着書評]
『深い疵』ネレ・ノイハウス
評者:挟名紅治

- 2012/08/07[新着書評]
【連載】 蔓葉信博「週末、たまにはビジネス書を」
第4回 小林直樹『ソーシャルリスク』 評者:蔓葉信博

- 2012/08/03[新着書評]
『はまむぎ』レーモン・クノー
評者:藤井勉

- 2012/08/02[新着書評]
『清須会議』三谷幸喜
評者:千三屋

- 2012/07/31[新着書評]
『岡崎京子の仕事集』岡崎京子(著)増渕俊之(編)
評者:相川藍

- 2012/07/28[新着書評]
『ことばの食卓』武田百合子
評者:杉江松恋

- 2012/07/18[新着書評]
『図説 死因百科』マイケル・ラルゴ
評者:大谷暁生

- 2012/07/13[新着書評]
『最果てアーケード』
小川洋子
評者:長坂陽子

- 2012/07/12[新着書評]
『なぜ戒名を自分でつけてもいいのか』橋爪大三郎
評者:千三屋

- 2012/07/05[新着書評]
『少年は残酷な弓を射る』(上・下)
ライオネル・シュライヴァー
評者:長坂陽子

- 2012/07/04[新着書評]
『未解決事件 グリコ・森永事件~捜査員300人の証言』NHKスペシャル取材班
評者:挟名紅治

- 2012/07/02[新着書評]
『女が嘘をつくとき』リュドミラ・ウリツカヤ
評者:藤井勉

- 2012/06/29[新着書評]
連載 蔓葉信博「週末、たまにはビジネス書を」
第3回 三浦展『第四の消費』 蔓葉信博

- 2012/06/27[新着書評]
『シフォン・リボン・シフォン』近藤史恵
評者:相川藍

- 2012/06/26[新着書評]
『湿地』アーナルデュル・インドリダソン
大谷暁生

- 2012/06/20[新着書評]
『彼女の存在、その破片』野中柊
長坂陽子

- 2012/06/15[新着書評]
『新人警官の掟』フェイ・ケラーマン
日向郁

- 2012/06/14[新着書評]
『俳優と超人形』ゴードン・クレイグ
千三屋

- 2012/06/13[新着書評]
『毒婦。 木嶋佳苗100日裁判傍聴記』北原みのり
長坂陽子

- 2012/06/12[新着書評]
『WOMBS』白井弓子
大谷暁生

- 2012/06/11[新着書評]
『21世紀の世界文学30冊を読む』都甲幸治
藤井勉

- 2012/06/08[新着書評]
『愛について』白岩玄
評者:相川藍

- 2012/06/06[新着書評]
『柔らかな犀の角ー山崎努の読書日記』山崎努
挟名紅治

- 2012/06/04[新着書評]
『夜をぶっとばせ』井上荒野
長坂陽子

- 2012/06/01[新着書評]
「七夜物語』川上弘美
長坂陽子

- 2012/05/23[新着書評]
「ピントがボケる音 OUT OF FOCUS, OUT OF SOUND』安田兼一
藤井勉

- 2012/05/21[新着書評]
「飼い慣らすことのできない幻獣たち」
『幻獣辞典』ホルヘ・ルイス・ボルヘス
藤田祥平

- 2012/05/16[新着書評]
連載「長坂陽子 ロマンスの神様願いを叶えて第18回」
「その名は自己満足」 長坂陽子

- 2012/03/30[新着書評]
連載「長坂陽子 ロマンスの神様願いを叶えて第17回」
「そのプライドが邪魔をする」 長坂陽子

- 2012/02/28[新着書評]
連載「長坂陽子 ロマンスの神様願いを叶えて第16回」
「恋のリスクマネジメント」 長坂陽子

- 2012/02/15[新着書評]
連載「長坂陽子 ロマンスの神様願いを叶えて第15回」
「非華奢女子の生きる道」 長坂陽子

- 2012/02/02[新着書評]
連載「長坂陽子 ロマンスの神様願いを叶えて第14回」
「パターン破りの効用」 長坂陽子

- 2012/01/31[新着書評]
『最高に美しい住宅をつくる方法』彦根明
評者:相川藍

- 2012/01/20[新着書評]
『ペット・サウンズ』ジム・フジーリ
評者:藤井勉

- 2012/01/17[新着書評]
連載「長坂陽子 ロマンスの神様願いを叶えて第13回」
胸だけ見ててもモテ期はこない 長坂陽子

- 2012/01/11[新着書評]
連載「長坂陽子 ロマンスの神様願いを叶えて第12回」
「恋で美しくなる」は本当か 長坂陽子

- 2012/01/10[新着書評]
「旧式のプライバシー」
『大阪の宿』水上滝太郎
藤田祥平
Internet Explorerをご利用の場合はバージョン6以上でご覧ください。
















