密やかな教育―<やおい・ボーイズラブ>前史

まだ「やおい」「BL(ボーイズラブ)」といった言葉が存在していなかった1970年代、美少年たちの性愛物語の創造に関わった仕掛け人の一人(増山法恵)は、自分たちの理想とした美と官能の世界を、「クナーベン・リーベ」と言い表します。「クナーベン・リーベ」すなわち「少年愛」、この何やら格調高そうな響きのドイツ語が、「ボーイズラブ」というカジュアルな和製英語に移り変わる「あいだ」に、はたして何が起こったのか。そのめくるめく激動の歴史を多彩な視点から物語る、めっぽう面白い<女子ども>文化論です。
60年代以降の男性知識人・文化人らによる「男性の身体の露出を通じて政治を語る」実践が、三島由紀夫の自死によって衰退を余儀なくされた後、そこで培われた美学と教養の体系に慣れ親しんだ女性たちによって、「男性身体の美と官能」を愛でる男同士の性愛物語が形作られてゆき、竹宮恵子の少女マンガ『風と木の詩』の連載開始(1976年)、そして雑誌『JUNE』の創刊(1978年)を重要なきっかけとして、80年代以降の本格的な商業的ジャンルとしての<やおい・BL>の成立と普及に至る。本書において示される歴史的展望を、以上のように大雑把にまとめてみることができるでしょう。複雑な社会・文化的状況をクリアに見通す幅広い視座に加えて、マンガ、文学、映画といった個々のテクストのメディア的特性を的確に押さえた精緻な読解、そして当事者たちに対するインタヴューをはじめとする地道な資料調査に基づいて、「女性がつくり楽しむ男性同士の性愛物語」の成り立ちを、具体的かつ体系的に把握してみせた点に、まず、本書の大きな意義があります。
萩尾望都、竹宮恵子、山岸涼子ら「花の24年組」による少女マンガの革命的な発展が、本書でも重点的に取り上げられるヘルマン・ヘッセの文学やヴィスコンティの映画など、ヨーロッパ発の「高級文化」や、稲垣足穂、三島由紀夫らの文学における「耽美」の美学の強い影響を受けていること。こうした事実は早くから気付かれ、さまざまな形で指摘されてもいます。しかし、そうした指摘が陥りがちだった断片的で漠然とした印象論も、あるいは「少女マンガにおける文学の影響」といった際にしばしば含意される、「高級文化」(成人男性の文化)から「低級文化」(<女子ども>の文化)への一方通行的な恩恵の授受という図式も、本書では周到に避けられています。
本書がヴィヴィッドに捉えてみせるのは、既存の「教養」を貪欲に取り入れつつ、それを大胆にカスタマイズすることで、より自分たちの理想に近い美と官能の世界を立ち上げてゆこうと試行錯誤する、若い作り手たちの熱気に満ちた営みです。ここには竹宮恵子をはじめとする個々の作家についてのすぐれた作家論も含まれていますが、さらにユニークかつ興味深いのが、「花の24年組」はじめ70年代少女マンガの野心的な描き手たちが集った「大泉サロン」、そして「70年代サブカルチャーの総花的雑誌」としての『JUNE』といった、主に女性からなる作り手と受け手のために開かれた、教育と創造の「場」についての記述です。
80年代以降、女性向けの商業ジャンルとしての「やおい・BL」が本格的に成立するにあたり、雑誌『JUNE』が一大拠点となったことは、今更言うまでもありません。しかし、初期『JUNE』誌上で、70 年代以前からの「男性身体の美と官能」をめぐる美学と教養の体系を継承する「教育」が実践されていたことを明らかにし、その「エンターテイメント教養」の場としての歴史的重要性を本格的に論じた点に、本書のユニークな画期性があります。
80年代以降の『JUNE』の主要連載のひとつ「小説道場」の主として、読者による投稿小説の添削指導を熱心に続け、多彩な顔ぶれの「門弟」達を育てたほか、初期『JUNE』誌上では、「フランス人小説家・ジュスティーヌ・セリエ」を名乗って耽美官能小説を執筆し、「仏文学専攻女子大生・あかぎはるな」を名乗って、『JUNE』読者にとっての必読書をまとめた「世界JUN(E)文学全集」を監修するなど、まさに八面六臂の「教育」活動を繰り広げた中島梓についての記述。あるいは、かつて「小説道場」の「門弟」の一人であった石原郁子が、耽美小説と映画批評の執筆を通じて、男性主体と異性愛主義を柱とする公的な制度の<外>で、性愛と官能に対する別様の視点と語り方の可能性を模索してゆく過程についての記述。いずれも早すぎる死をとげたこのふたりの書き手について書かれた文章の中でも、最も魅力的かつ感動的なものの一つといえるでしょう。
後半には竹宮恵子、『JUNE』の企画者である編集者の佐川俊彦、「大泉サロン」の主催者増山法恵の三氏に対するインタヴューが収録されていて、いずれも貴重な証言が満載の充実した内容です。わけても、竹宮恵子はじめ、「花の24年組」のプロデューサー/マネージャーというべき役割を務めた増山法恵氏に対するインタヴューが圧巻です。幼い頃から文学、映画、音楽に耽溺して育った若い女性が、少女マンガに「芸術」に匹敵する品質と地位を獲得させるという、その時点においては無謀ともいえる志を抱き、偶然に出会った才能ある友人たちに、自選の文学、映画作品を薦めて「教育」を施し、やがて同好の志を集めて「大泉サロン」を立ち上げ、万事において保守的な雑誌編集部と闘いをくり広げてゆく。その「友人」とは、竹宮恵子と萩尾望都であった――。という「24年組革命」の仕掛人の物語るエピソードの数々は、『プロジェクトX』の大半のエピソードが裸足で逃げ出す面白さです。
本書は、「女性がつくり楽しむ男性同士の性愛物語」の成立にかかわった人々の集いの場を、たんにノスタルジックなユートピアとして捉えているわけではありません。本書の終わりには、「作品はすべての人に開かれ、読まれ、解釈される。そして、賛辞も、批判も含めて、思いもよらなかったものが生まれいずる。この終わりなき繰り返しが文化とよばれる営みだ、と私は考える」(277)という文章が置かれています。「自分にも何かできるはず」という熱いパトスに突き動かされた人々が集まり、称賛さるべき、あるいは批判さるべき、ときには困惑と苦笑をさそう素っ頓狂なものも含みこんだ雑多な実践が、たえず生起してやまなかった教育と創造の場の記憶を継承する本書は、それ自体が「密やかな教育」の場として、現在もしくは未来の読者に向けて開かれています。
おすすめ本書評・紹介書籍
-
- 密やかな教育─〈やおい・ボーイズラブ〉前史
洛北出版 [サブカルチャー] 国内
2008.11 版型:B6
価格:2,730円(税込)
>>詳細を見る
新着情報
-

- 2013/08/16[新着書評]
『きことわ』朝吹真理子
評者:千三屋
-

- 2013/08/15[新着書評]
『テルマエ・ロマエⅥ』ヤマザキマリ/「1~3巻は大傑作、4~6巻は残念な出来」
評者:新藤純子
-

- 2013/06/19[新着書評]
『高円寺 古本酒場ものがたり』狩野俊
評者:千三屋

- 2013/05/12[新着書評]
『フィフティ・シェイズ・ダーカー(上・下)』ELジェイムズ
評者:日向郁

- 2013/04/04[新着書評]
『クラウド・アトラス』デイヴィッド・ミッチェル
評者:千三屋

- 2013/02/18[新着書評]
『はぶらし』近藤史恵
評者:日向郁

- 2013/01/31[新着書評]
『知的唯仏論』宮崎哲弥・呉智英
評者:千三屋

- 2013/01/18[新着書評]
『秋田寛のグラフィックデザイン』アキタ・デザイン・カン
評者:千三屋

- 2013/01/17[新着書評]
『空白を満たしなさい』平野啓一郎
評者:長坂陽子

- 2013/01/15[新着書評]
『箱根駅伝を歩く』泉麻人
評者:千三屋

- 2013/01/11[新着書評]
『世界が終わるわけではなく』ケイト・アトキンソン
評者:藤井勉

- 2012/12/19[新着書評]
『デザインの本の本』秋田寛
評者:千三屋

- 2012/11/28[新着書評]
『ニール・ヤング自伝I』ニール・ヤング
評者:藤井勉

- 2012/11/22[新着書評]
『日本人はなぜ「黒ブチ丸メガネ」なのか』友利昴
評者:新藤純子

- 2012/11/21[新着書評]
『私にふさわしいホテル』柚木麻子
評者:長坂陽子

- 2012/11/15[新着書評]
『格差と序列の心理学 平等主義のパラドクス』池上知子
評者:新藤純子
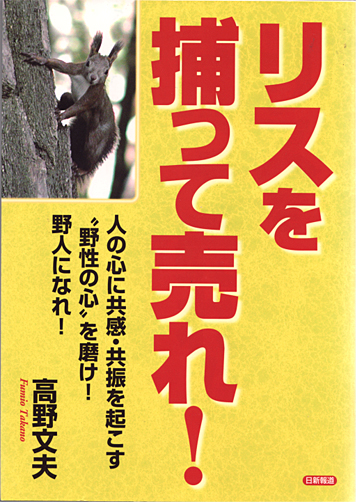
- 2012/11/09[イベントレポ]
兼業古本屋のできるまで。とみさわさん、なにをやってんすか

- 2012/11/08[新着書評]
『機龍警察 暗黒市場』月村了衛
評者:大谷暁生

- 2012/11/02[新着書評]
『なしくずしの死』L-F・セリーヌ
評者:藤田祥平

- 2012/10/31[新着書評]
『エコー・メイカー』リチャード・パワーズ
評者:藤井勉

- 2012/10/30[新着書評]
『文体練習』レーモン・クノー
評者:藤田祥平

- 2012/10/25[新着書評]
『生きのびるための建築』石山修武
評者:千三屋

- 2012/10/24[新着書評]
『占領都市 TOKYO YEAR ZERO Ⅱ』デイヴィッド・ピース
評者:大谷暁生

- 2012/10/19[新着書評]
『最後の授業 ぼくの命があるうちに』ランディ・パウシュ、ジェフリー・ザスロー
評者:日向郁

- 2012/10/18[新着書評]
『イタリア人と日本人、どっちがバカ?』ファブリツィオ・グラッセッリ
評者:相川藍

- 2012/10/17[イベントレポ]
ミステリー酒場スペシャル ローレンス・ブロック酒場Part1

- 2012/10/16[イベントレポ]
ブックレビューLIVE:杉江VS米光のどっちが売れるか!?

- 2012/10/15[イベントレポ]
ミステリ酒場スペシャル ローレンス・ブロック酒場三連発 PART2~泥棒バーニー、殺し屋ケラー編&ブロックおもてなし対策会議~

- 2012/10/15[新着書評]
『犬とハモニカ』江國香織
評者:長坂陽子

- 2012/10/10[新着書評]
『Papa told me cocohana ver.1 丘は花でいっぱい』榛野なな恵
評者:千三屋

- 2012/10/08[イベントレポ]
“その日”が来てからでは遅すぎる! あなたの知らないお葬式のすべて?ボッタクリの秘密から納得のエコ葬儀プランまで

- 2012/10/03[新着書評]
『青い脂』ウラジーミル・ソローキン
評者:藤井勉

- 2012/10/02[イベントレポ]
松本尚久さん、落語の楽しみ方を教えてください!

- 2012/10/01[新着書評]
『ヴァンパイア』岩井俊二
評者:長坂陽子

- 2012/09/25[新着書評]
『鬼談百景』小野不由美
評者:挟名紅治

- 2012/09/24[新着書評]
『ここは退屈迎えに来て』山内マリコ
評者:長坂陽子

- 2012/09/18[新着書評]
『最初の人間』アルベール・カミュ
評者:新藤純子

- 2012/09/14[新着書評]
『その日東京駅五時二十五分発』西川美和
評者:相川藍

- 2012/09/13[新着書評]
『無分別』オラシオ・カステジャーノス・モヤ
評者:藤井勉

- 2012/09/12[新着書評]
『鷲たちの盟約』(上下)アラン・グレン
評者:大谷暁生

- 2012/09/11[新着書評]
『ラブ・イズ・ア・ミックステープ』ロブ・シェフィールド
評者:日向郁

- 2012/09/10[新着書評]
『嵐のピクニック』本谷有希子
評者:長坂陽子

- 2012/09/07[新着書評]
『本当の経済の話をしよう』若田部昌澄、栗原裕一郎
評者:藤井勉

- 2012/09/05[新着書評]
『ひらいて』綿矢りさ
評者:長坂陽子

- 2012/09/04[新着書評]
『失脚/巫女の死 デュレンマット傑作選』フリードリヒ・デュレンマット
評者:藤井勉

- 2012/09/03[新着書評]
『かくも水深き不在』竹本健治
評者:蔓葉信博

- 2012/08/31[新着書評]
『わたしが眠りにつく前に』SJ・ワトソン
評者:長坂陽子

- 2012/08/28[新着書評]
『芸術実行犯』Chim↑Pom(チン↑ポム)
評者:相川藍

- 2012/08/27[新着書評]
『ぼくは勉強ができない』山田詠美
評者:姉崎あきか

- 2012/08/16[新着書評]
『オカルト 現れるモノ、隠れるモノ、見たいモノ』森達也
評者:長坂陽子

- 2012/08/10[新着書評]
『セックスなんか興味ない』きづきあきら サトウナンキ
評者:大谷暁生

- 2012/08/08[新着書評]
『深い疵』ネレ・ノイハウス
評者:挟名紅治

- 2012/08/07[新着書評]
【連載】 蔓葉信博「週末、たまにはビジネス書を」
第4回 小林直樹『ソーシャルリスク』 評者:蔓葉信博

- 2012/08/03[新着書評]
『はまむぎ』レーモン・クノー
評者:藤井勉

- 2012/08/02[新着書評]
『清須会議』三谷幸喜
評者:千三屋

- 2012/07/31[新着書評]
『岡崎京子の仕事集』岡崎京子(著)増渕俊之(編)
評者:相川藍

- 2012/07/28[新着書評]
『ことばの食卓』武田百合子
評者:杉江松恋

- 2012/07/18[新着書評]
『図説 死因百科』マイケル・ラルゴ
評者:大谷暁生

- 2012/07/13[新着書評]
『最果てアーケード』
小川洋子
評者:長坂陽子

- 2012/07/12[新着書評]
『なぜ戒名を自分でつけてもいいのか』橋爪大三郎
評者:千三屋

- 2012/07/05[新着書評]
『少年は残酷な弓を射る』(上・下)
ライオネル・シュライヴァー
評者:長坂陽子

- 2012/07/04[新着書評]
『未解決事件 グリコ・森永事件~捜査員300人の証言』NHKスペシャル取材班
評者:挟名紅治

- 2012/07/02[新着書評]
『女が嘘をつくとき』リュドミラ・ウリツカヤ
評者:藤井勉

- 2012/06/29[新着書評]
連載 蔓葉信博「週末、たまにはビジネス書を」
第3回 三浦展『第四の消費』 蔓葉信博

- 2012/06/27[新着書評]
『シフォン・リボン・シフォン』近藤史恵
評者:相川藍

- 2012/06/26[新着書評]
『湿地』アーナルデュル・インドリダソン
大谷暁生

- 2012/06/20[新着書評]
『彼女の存在、その破片』野中柊
長坂陽子

- 2012/06/15[新着書評]
『新人警官の掟』フェイ・ケラーマン
日向郁

- 2012/06/14[新着書評]
『俳優と超人形』ゴードン・クレイグ
千三屋

- 2012/06/13[新着書評]
『毒婦。 木嶋佳苗100日裁判傍聴記』北原みのり
長坂陽子

- 2012/06/12[新着書評]
『WOMBS』白井弓子
大谷暁生

- 2012/06/11[新着書評]
『21世紀の世界文学30冊を読む』都甲幸治
藤井勉

- 2012/06/08[新着書評]
『愛について』白岩玄
評者:相川藍

- 2012/06/06[新着書評]
『柔らかな犀の角ー山崎努の読書日記』山崎努
挟名紅治

- 2012/06/04[新着書評]
『夜をぶっとばせ』井上荒野
長坂陽子

- 2012/06/01[新着書評]
「七夜物語』川上弘美
長坂陽子

- 2012/05/23[新着書評]
「ピントがボケる音 OUT OF FOCUS, OUT OF SOUND』安田兼一
藤井勉

- 2012/05/21[新着書評]
「飼い慣らすことのできない幻獣たち」
『幻獣辞典』ホルヘ・ルイス・ボルヘス
藤田祥平

- 2012/05/16[新着書評]
連載「長坂陽子 ロマンスの神様願いを叶えて第18回」
「その名は自己満足」 長坂陽子

- 2012/03/30[新着書評]
連載「長坂陽子 ロマンスの神様願いを叶えて第17回」
「そのプライドが邪魔をする」 長坂陽子

- 2012/02/28[新着書評]
連載「長坂陽子 ロマンスの神様願いを叶えて第16回」
「恋のリスクマネジメント」 長坂陽子

- 2012/02/15[新着書評]
連載「長坂陽子 ロマンスの神様願いを叶えて第15回」
「非華奢女子の生きる道」 長坂陽子

- 2012/02/02[新着書評]
連載「長坂陽子 ロマンスの神様願いを叶えて第14回」
「パターン破りの効用」 長坂陽子

- 2012/01/31[新着書評]
『最高に美しい住宅をつくる方法』彦根明
評者:相川藍

- 2012/01/20[新着書評]
『ペット・サウンズ』ジム・フジーリ
評者:藤井勉

- 2012/01/17[新着書評]
連載「長坂陽子 ロマンスの神様願いを叶えて第13回」
胸だけ見ててもモテ期はこない 長坂陽子

- 2012/01/11[新着書評]
連載「長坂陽子 ロマンスの神様願いを叶えて第12回」
「恋で美しくなる」は本当か 長坂陽子

- 2012/01/10[新着書評]
「旧式のプライバシー」
『大阪の宿』水上滝太郎
藤田祥平
Internet Explorerをご利用の場合はバージョン6以上でご覧ください。
















