この短編集は二つのセクションから成る。『八岐の園』、『工匠集』という題名が付けられていて、それぞれの冒頭に二頁ほどの短い「プロローグ」が載っている。この書評では『八岐の園』部から三編を取り上げ、『八岐の園』全体を通して使われることばのひとつ、「無限」について、筆者の考えを交えつつ語る。この本に収められたすべての短編はおそろしく密度が高く、「レクラ」の惑星をかたどったショコラのように、二粒続けて食べると胃もたれがやってくる。筆者はなるたけ敷衍しつつ――溶かして牛乳と混ぜるように――語りたいと思う。
なお、『伝奇集』のいくつかの作品は、そもそもが要約であるかのように簡潔な文体で書かれているため、本文からの引用を多用することを、前もってお断りしておく。
長大な作品を物するのは、数分間で語り尽くせる着想を五百ページにわたって展開するのは、労のみ多くて功少ない狂気の沙汰である。よりましな方法は、それらの書物がすでに存在すると見せかけて、要約や注釈を差し出すことだ。〔…〕より論理的で、より無能で、より怠惰な筆者は、架空の書物にかんするノートを書く道をえらんだ。
これはプロローグからの引用である。ものすごく威勢の良い文言に続けて、自分を卑下する形容動詞をふたつ挿入する慎重さが憎い。同時に、続く作品への読者の期待を高く設定している。目次を見て短編集だと理解した読者は、この文言によって意図的に操作され、その手法を応用した短編を求める――果たしてどんな物語を読ませてくれるのだろうとうずうずしはじめる。そんな興奮した読者を引き受けるトップバッターが、「トレーン、ウクバール、オルビス・テルティウス」だ。
語り手の「わたし」は、友人を相手に議論していた。「語り手が事実を省略もしくは歪曲し、さまざまな矛盾をおかすために、少数の読者しか――ごく少数の読者しか――恐るべき、あるいは平凡な現実を推測しえない、一人称形式の小説の執筆についてである。」二人は、廊下の奥の鏡が気になった。友人は、「鏡と交合は人間の数を増殖するがゆえにいまわしい」というような、ウクバールの異端の教祖のことばを思い出した。そのことばを気に入った「わたし」が出所を尋ねると、『アングロ・アメリカ百科事典』のウクバールの項にのっている、と友人は答えた。さっそく二人はその百科事典を当たってみたが、思いつくかぎりのスペルを試しても、ウクバールについての項目は見つからなかった。翌日、その友人から電話がかかってきた。たったいま百科事典を開いて、問題の項目を見ているというのだ。友人が思い出して言ったのは、「交合と鏡はいまわしい」だった。正確には、「鏡と父性はいまわしい、宇宙を増殖し、拡散させるからである」と書かれているそうだ。「わたし」は友人を自宅に招き、一緒にその項目を確かめた。
二人は、四頁にわたるその項目を「すこし丁寧に」読んだ。繰り返し読んでいるうちに、彼らは「厳密な文章のかげに重大な曖昧さがひそんでいることに」気づいた。地理の部を読んでも、つまるところウクバールがどこにあるのか判らない。歴史上の人物として取り上げられているのは、隠喩のかたちで本文に組み入れられた魔術師ひとりきり。「記憶に値する点はただひとつ」と「わたし」はいう、「ウクバールの文学は幻想的であり、その叙事詩や伝説はまったく現実とかかわりを持たず、ムレイナスとトレーンという、ふたつの架空の地方にまつわるものである……。」
あらゆる物事の意味が掲載されているはずの百科事典に誤謬があるというテーマは、ふだんわれわれが何気なく手にしている辞典の信頼性に揺さぶりをかけてくる。すべての書かれたものは否応なくフィクション性を含むが、辞典だけはその意味が現実に即していなければならない。いわばすべての言葉の地盤である辞典、それが揺らぐ。
「文献に四冊が挙げられていた」という前置きに続く文章がミソだ。「三番目の本――サイラム・ハスラム著、『ウクバールと呼ばれる国の歴史』一八七四年版」。この「サイラム・ハスラム」という人物には訳注がつけられていて、そこにははっきり「架空の人物」と書かれているのである。「プロローグ」にあった「存在すると見せかけて、要約や注釈を差し出す」手法である。続けて挙げられている文献のひとつを書いたという「ヨハン・ファレンティン・アンドレー」という人物にも訳注がつけられていて、そこには「ドイツの詩人・風刺作家・神学者」と書かれている――実在したのである。架空の人物と実在の人物が並列されることによって、本当にその人物が架空のもの、あるいは実在のものなのかどうか、読者は混乱することになる(ただしこれは「訳注」なので、ボルヘスが加えた注でないことに注意されたし)。
二人はやっきになって、国立図書館で地図や目録や地理学協会の年鑑などをあたってみたが、徒労に終わった。ウクバールに足を踏み入れた人間は一人もいなかったのだ。
ここで一章が終わる。
二章では、南部鉄道の技師だったべつの友人が登場する。彼が動脈瘤破裂で死ぬ数日前、彼のところにブラジルからの書留小包が届いていた。中身は、大型の八つ折り判の書籍だった。彼はそれをバーに起きっぱなしにし、「わたし」がそれを見つけた。「そのページをめくり始めたとたんに、わたしは驚き、軽い目まいに襲われた」。なんとその本の扉には、英語で、「トレーンを扱った最初の百科事典第十一巻。Hlaer-Jangr」と書かれていたのである。「最初のページと色刷りの挿絵の一枚をおおっている薄葉紙に、「オルビス・テルティウス」という文字の入った、青い楕円形のスタンプが押されていた。」その内容はいかにも辞典らしく、一切が明確だったが、宗教臭さや嘘っぽさはなかった。
いささか唐突に、「トレーン」が学界に知れ渡る。「ネストル・イバーラ」という人物が論文のなかで、トレーン百科事典は十一巻の他には存在しないという主張をし、「エセキエル・マルティネス=エストラダとドリュ・ラ・ロシェルは、どことなく誇らしげな調子で、そのような疑惑に反論した」。ちょっと待て、トレーンは「わたし」が偶然に見つけた秘密の書物の話ではなかったか。いつのまに学界の問題になっているのだ。
この短編は一人称形式で書かれているため、「わたし」はこの急すぎる事態の推移についてなんの言及もしない。冒頭で「わたし」が語った「一人称形式の小説」の「事実の省略」ないしは「矛盾」を、ボルヘス自身が用いているのである。
(プロセスは大胆に省かれたものの)トレーンという世界が周知のものとなり、「トレーン学者の一世代」という言葉まで使われ、トレーンのことを皆が「素晴らしい新世界」などと持ち上げはじめる。トレーンは、さまざまな学問のプロフェッショナル達によって作り上げられた一個の宇宙であるということが「分かり」、「わたし」は人々の熱狂をよそに、むしろ「その宇宙観について語ってみたい」と述べ、語り始める。そもそもトレーンは、ウクバールという謎の国における文学の舞台だったはずなのだが……。
疑問はさておき、「わたし」によるトレーン講座は非常に面白い。トレーンの「南半球」(もう逐一突っ込むまい)における言葉の祖語には、名詞が存在しないという。かわりに、副詞的な意味をもつ接尾辞あるいは接頭辞で修飾される、非人称動詞が存在する。「一例だが、月に相当する単語はないが、スペイン語でなら月にするか月するに相当すると思われる動詞がある。月は河の上にのぼったは hlör u fang axaxaxas mlö 、つまり逐語的に訳せば、上方に、背後に、持続的に流れる、月した、といわれる。」主語、主体となる名詞が存在しないということ。これが後述する、あらゆる認識の主体が単一のものであるという、トレーンの住民に共通の観念論に繋がっていく。
話はトレーンの「北半球」の言語のことに移り、さらにその言語から生まれ出た様々な学問のことへと移る。多様な学派が出現し、学派同士の議論の推移が語られる。言語性から人々が普遍的に獲得するにいたった観念論が、無から物体を創出することを可能にした、という逸話が印象的だ。「何世紀にも渡る観念論の支配は、現実に影響せずにいなかった。〔…〕二人の人間が一本の鉛筆を探している。第一の人間がそれを見つけ、何にもいわない。第二の人間が、これに負けないくらい本物らしいが、しかし彼の期待にいっそうぴったりした第二の鉛筆を発見する。これらの第二の物体はフレニールと呼ばれ、形がくずれているが少々長めである。〔…〕トレーンにおいては事物はみずからを複製する。同様に、人々に忘れられると輪郭が薄れ、細部が消える傾きがある。乞食が来ているあいだはそこにあり、彼が死ぬと同時に消えた戸口は、その古典的な例である。」認識の主体は個々人にあるのではなく、つねに単一の、自分自身である。観測するものがいなければ、あらゆるものは存在しない、と住民達は無意識に信じている。だから事物を「探し当てる」のではなく、「複製する」と表現するわけだ。
われわれの観念と比べてみよう。われわれは、滝を見ていないときにも水が落ちていると考える。ある学者たちは、観測していないあいだは水が空中で静止しているかもしれないと考える。そしてトレーンの住人たちは、見られていない滝はそもそも存在していないと考えるのだ(もしかしたらトレーン世界内では、本当に存在していないのかもしれないが)。
ここで文章は途切れ、「一九四○年、サルト・オリエンタルにて」という文でいったん締めくくられる。それに続けて、「一九四七年の追記」という体で話が続く。「あれからじつに多くのことがあった……。」と思わせぶりな書き方である。
一九四一年、二章の始まりで死んでしまった友人の蔵書から、トレーンの秘密を完全に明らかにする手紙が見つかった。手紙によると、トレーンはそもそも十七世紀初頭に始まった、ある慈善団体のプロジェクトだったという(突っ込みたくてたまらない)。彼らはひとつの宇宙に関する百科事典を刊行することに決め、四十巻からなる『トレーン第一百科事典』の最後の巻が会員たちに配布された。
一九四二年、「わたし」はトレーンが現実に侵入しはじめていることに気がついた。ある公妃に贈られたコンパスの盤の文字は、トレーンのアルファベットのひとつだった。「わたし」がある場末の酒場に泊まる羽目になったとき、飲み過ぎて死んでしまったとある客のベルトから、「トレーンのある種の宗教における神聖の象徴」である「小さくて非常に重い円錐」が見つかった。
一九四四年ごろ、ある雑誌の調査部員が、メンフィスの図書館で『トレーン第一百科事典』の四十巻を発見した(あたかもフレニールの増殖のようだ)。「わたし」によると、すでにトレーンの祖語は学校に侵入して、さまざまな教科書の内容を修正してしまった。
最後に、「わたし」はこんなふうに結ぶ。
仮りにわれわれの予想が誤っていなければ、いまから百年後に、何者かが『トレーン第二次百科事典』の百巻を発見することになるだろう。そのとき、英語やフランス語、ただのスペイン語などは地上から消えるにちがいない。世界はトレーンとなるだろう。だが、わたしは気にしない。アドロゲーのホテルで静かな日々を送りながら、ブラウンの『壺葬論』のケベードふうの試訳――出版しようというつもりはないが――の校訂を続けるのだ。
言語があたらしい言語に取って代わられることの暗喩。最後に「わたし」が本を訳すつもりでいること、言語をべつの言語に置き換えるつもりでいること。話の中心が、いつのまにか「ウクバール」の存在から「トレーン」の世界にすり替えられていたこと。ある学派は、宇宙は広大なフラクタルの一部だと主張する。彼らの言を信用すると、ひとつの宇宙を創造するということは無限を創造することだといえる。これだけでも興味深い事柄はたくさんあるが、まだ話をするためのピースが足りないので(そもそもこれはたった二七ページの短編である)、すこし足早につぎの作品の紹介へ移らせていただこう。
「円環の廃墟」はプロローグで言われているように、一切が非現実的な三人称小説である。一人の男が、ある人間を注意深く夢見ることによって、その存在を現実に押し出そうとする、という筋書きの物語だ。なにもないところから物体を現実に顕現させる、というテーマは、「トレーン」の住民達が試みたフレニールの増殖に似ている。
男はどこからともなくやってきて、山火事で燃焼した神殿の廃墟に身を横たえた。よそ者を畏怖した近隣の住人達によって、食料や水が運ばれた。彼は仕事に取りかかるために眠った(字面だけを見ると笑える)。夢のなかの円形の階段教室で、学生たちに解剖学や宇宙形状学、魔法などを講義した。学生はみな熱心に聞いていた。あたかも彼らのうち一人を取り上げて、その現実に引きずりだすという男の野望を知っているかのようだった。
男は何回かの講義のあと、一人の学生を選び、他をみんな消してしまった。学生は男自身によく似た外見で、教えられたことを驚くほどよく覚えた。しかし男はとつぜん不眠に見舞われ、横になっても切れ切れの夢しか見られなくなり、学生の姿は散逸してしまった。男はたいへん苦しんだ。次に、脈打つ心臓からはじめて、骨や筋肉や皮膚や髪を隅々まで想像し、ひとつの人形を作った。苦心したものの、出来はひどいものだった。彼は絶望し、動物をかたどった、神殿の像の足下に身を投げ出して眠った。
その夢の中で、彼は像と相対した。そして像が地上において「火」と呼ばれている存在であることを知った。「火」もまた無から新しい人間を創り出そうと考えていた。像は彼に、河の下流にある神殿に彼の創り出した人間を送り込むことを命じた。「夢みていた男の夢のなかで、夢みられた人間が目覚めた」。火の礼拝の秘儀を教え込むのに二年を要した。彼はその人間を自分の息子だと考え、すこしずつ現実に慣れさせていった。送り出すにあたって、自分が幻であることを自覚しないよう、彼は息子の修業時代の記憶をすべて忘れさせた。
彼は自分の成功に満足したが、しだいに不安が募ってきた。あらゆる創造物のなかで、「火」だけが息子を幻だと知っている。「火」に焼かれないという特権に息子が気づき、そのことについて考え、自分が幻だと気づくのではないか。「人間ではなく、べつの人間の夢であること。これに比べられる屈辱、困惑があるだろうか!」男の瞑想は不安によって途切れた。神殿の周囲にあらゆる予兆が満ちた。南方の空が豹の歯茎めいた色を見せた。そして怯えた動物たちが走っていった。火の手はすぐに神殿まで伸び、男は死が訪れようとしていることを悟った。彼は炎のなかへと歩いて行ったが、炎は彼を噛むどころか、やさしく愛撫した。燃えさかる炎のなかで彼は、「おのれもまた幻にすぎないと、他者がおのれを夢見ているのだと悟った。」
一見すると「円環の廃墟」は、無限を解説した小説のように見える。あきらかにループもので、じじつ繰り返される無限の一部にフォーカスして描いたものである。しかし数学的には――文学に数学の公式を当てはめるのは無粋かもしれないが――無限数から有限数(描かれたいくつかの場面)を引く(フォーカスする)ことはできない。「無限」そのものを小説という形式に落とし込んで書こうとした結果がこの作品なのだと仮定すると、その試みは失敗といえる。公理に反するからだ。
この作品はむしろ、無限に循環する数列を、小説の形式で解説したものだと筆者は考える。Aのあとには必ずBが来て、Bのあとには必ずAがくる、という数列だ。「円環の廃墟」の構造も、Aで物語が始まり、Bで終わり、またAに戻る(厳密にはA'に戻り、B'に続く)という形である。AとBが無限に続くということを表現したいのなら、無限に続くという条件を描写すればよい。ボルヘスは、いかめしい数学記号とはべつの手段、物語を使って、無限に続くという条件を設定してのけたのだ。
以下は閑話である。
じつは筆者は、この文章を書くにあたって、知人の数学者に「無限に循環するABという数列を、数学的にまちがいなく記述するには、どうすればいいのだろう?」という質問をした。そういった数式を書き加えるつもりだったのだ。しかし彼は腕を組んで唸り、「じつは集合論においてはそのへんのスマートな記述法はまだ整備されていないのだ、ムニャムニャ」というようなことを言い、十五文字ほどの記号を並べたて、なんとかして四文字程度でスマートに記述できないものかと苦しみはじめた。筆者はむしろ、一見すると単純そうな条件をあらわす形式が整備されていないことに驚きを覚えた……彼が勉強不足なだけなのかもしれないが(Dくん、ゴメン)。いずれにせよ、彼に感謝の意を表すため、閑話として挿入した次第である。
話が数学的になってきたのにはわけがあり、それは筆者が「バベルの図書館」について書こうとしていたからだ。この短編は、膨大な蔵書が収められた図書館が舞台である。文章に好意を抱くひとはこの設定だけでたまらないだろう。そもそも、この短編を読むひとは前提として、小説を読むくらいに文章が好きなのである。ということは、この短編の読者に敵は生まれない。最初からすべての読者を味方につけるという、クレバーな戦略である。
本編は少々数学的である。幻想的でもあるが、それを語るための言葉の輪郭ははっきりとしている。さまざまな公理(そもそも「公理」という言葉がすでに数学的だ)がごく自然に設定されるために、読者は謎かけをされているように感じるものの、なにを問題としているのかはほとんど最後までわからない。混乱しながら読み進めていくうちに、いつのまにか問題の説明が済んでいて、解法が提示されて終わる、という意地悪な短編である。といっても、たとえば数IIの教科書のように、無慈悲に公理や解法が連発されるわけではない。むしろ様々な挿話を以て面白く装飾されているため、読者は十分に読む楽しみを得られる。
書き出しから引用する。
(他の者たちは図書館と呼んでいるが)宇宙は、真ん中に大きな換気孔があり、きわめて低い手すりで囲まれた、不定数の、おそらく無限数の六角形の回廊で成り立っている。どの六角形にも、それこそ際限なく、上の階と下の階が眺められる。回廊の配置は変化がない。一辺につき長い本棚が五段で、計二十段。それらが二辺をのぞいたすべてを埋めている。その高さは各階のそれであり、図書館員の通常の背丈をわずかに超えている。棚のない辺のひとつが狭いホールに通じ、このホールは、最初の回廊にそっくりなべつの回廊や、すべての回廊に通じている。ホールの右と左にふたつの小部屋がある。〔…〕その近くに螺旋階段があって、上と下のはるかかなたへと通じている。ホールに一枚の鏡がかかっていて、ものの姿を忠実に複写している。この鏡を見て人間たちは、よく、図書館は無限大ではないと推論する(実際にそうだとすれば、この幻の複写は、いったい何のためなのか?)。わたしはむしろ、その磨かれた表面こそは無限をかたどり、約束するものだと夢想したい……。
図書館の構造をつかむには、無限に大きい蜂の巣を想像すればよい。すべての六角形の中心に穴をあけ、上下左右の部屋に通じる道をつくれば、大体のモデルである。人間にはその図書館のなかを行き来する「司書」という肩書きが与えられている。語り手である「わたし」は、他の司書たちと同じように、かつては一冊の本を求めて遍歴を繰り返したが、いまは老境を迎えて死に支度を整えつつある。その一環として、ある問題に対して書かれた解答、というのがこの短編の体裁である。
「死ねば、手すりからわたしを投げてくれる慈悲ぶかい手にこと欠かないだろう。わたしの墓は計りがたい空間であるにちがいない。わたしの遺体はどこまでも沈んでゆき、無限の落下によって生じた風のなかで朽ち、消えてしまう」。いくつもの背表紙に囲まれて落下していくというモチーフは、ルイス・キャロルの『不思議の国のアリス』の、アリスが落ちていった井戸を彷彿とさせる。そういえばインタヴュー本『ボルヘスとの対話』(リチャード・バーギン著 晶文社)のなかで、ボルヘスは「(「不思議の国のアリス」について)すばらしい本です!」と答えていた……。
図書館といっても、この図書館に収められている本に意味のあるものはほとんどない。よしんばあったとしても、司書たちがそれをくみ取ることはまれだ。ほとんどの蔵書が二十五種の記号のランダムな組み合わせであり、ある本などは延々と繰り返されるMとCとVの三文字から成り立っている。
「わたし」は、「解答〔…〕の要約に先だって、いくつかの公理を思い出しておきたい」と前置きする。これらの公理はわかりやすい形で本文中に記されてはいるが、それぞれが散らばっているので、ここではまとめて紹介する。
【公理1】図書館は永遠を超えて存在する。
【公理2】正書法上の記号の数は二五である。
【公理3】広大な図書館に、同じ本は二冊ない。
これらの公理に加えて必要だと思われる情報がひとつある。「図書館の本はすべて四百十ページからなる。各ページは四十行、各行は約八十の黒い文字からなる」という箇所だ。
二つめの公理について付け加えると、図書館のあらゆる蔵書は、二十三のアルファベット、カンマ、ピリオドで書かれている。このことと三つ目の公理を踏まえると、二十五個の記号のあらゆる組み合わせが書かれた本があるが、同じ内容の本は二冊とない。つまり図書館の蔵書の総数は、ページと行と文字の数を掛け合わせた数に、記号の数である25をべき乗した数で、有限である(ただし、各行の文字数にばらつきがあるため、正確な数値はわからない)。
これらの公理に従うと、この図書館のどこかには「トレイン、ウクバール、オルビス・テルティウス」、「円環の廃墟」、またそれらを収録した『伝奇集』という本が存在することになる。付け加えていえば、この書評そのものも、図書館における正書法に乗っ取った形で図書館に収められている。きわめて膨大な数にのぼる蔵書のなかには、あらゆる本、すでに出版されたものはもちろん、百年後に出版されるものも存在しているのだ。語り手自身も、「この無用で饒舌な書簡もすでに、無数の六角形のひとつ〔…〕に存在している」と述べている。
三つ目の公理の発表は、図書館の者たちに希望を与えた。この公理によって、すべての人間の過去を弁明し、未来を保証するような本が存在することを証明できる。人々は血眼になってこの本を探し求めたが、誰もそれを見つけることはできなかった。落胆が図書館を覆い、血なまぐさい事件や本の消失などが起こった。「わたし」は言う、「それを求める者たちは、一人の人間が自分の本を、あるいは、自分の本の偽物を発見する可能性はゼロであることを考えようとしなかった」。
当時はまた、図書館の時間の起源の解明が期待された。もし現在使われている言葉がそれを解説するのに不十分だとしても、解説するための語彙や文法までをもふくんだ本が図書館のどこかにあるはずだ。公的な捜索係、調査官があらわれた。彼らは血眼になってその本を探したが、むだだった。他の連中は、いっそ無駄な本をすべて消滅させてしまえばいいと考えた。多数の本が通気孔に投げ込まれた。彼らの名前は呪詛の対象になった。「わたし」は言う、「彼らは「深紅の六角形」の本――普通のものより小型で、全能で、挿絵入りで、魔力をそなえた本――を手に入れたいという欲に動かされていたのだ。」(六角形ではなかったし、普通のものより小型で、全能かつ魔力をそなえているかどうかは判らないが、一八六五年に出版された『不思議の国のアリス』のファースト・エディションは挿絵入りで深紅の装丁だった。ルイス・キャロルが装丁係に宛てた手紙に、そうするよう指示していたことが記録にある)
「わたしが監督している多数の六角形の最良の本は、〔…〕『アクサクサクサス・ムレー』である。」 という一行が面白い。「トレーン……」のなかで語り手が用いた、トレーン語の一文に、"axaxaxas mlö"という言葉があった。筆者が手にしている本にはカタカナで表記されているため、断言はできないが、同一のものと見ていいだろう。すると、「バベルの図書館」の語り手が「支離滅裂に思われる」としたこの言葉の意味が、「トレーン……」を参照することで判ってくる。「つまり逐語的に訳せば、上方に、背後に、持続的に流れる、月した、といわれる」。『アブラクサクサス・ムレー』は、この四つの言葉のうちどれか二つを組み合わせた意味をもつタイトルで、たぶん、内容もトレーン語で書かれている(表紙と内容がべつの言語で書かれている本は、同じ言語で書かれている本よりも少ないはずだ)。
さらに、先に取り上げた二編と対応する箇所を挙げるため、引用する。
断言するが、図書館は無限である。観念論者たちは、六角形の部屋は絶対空間の、少なくとも空間についてのわれわれの直観の必然的形式である、と主張する。〔…〕(神秘主義者たちは、無我の境地に達すると円形の部屋が現われるが、そこには、四囲の壁をひとめぐりする切れ目のない背を持った、一冊の大きな本が置かれている、と主張する。しかし、彼らの証言は疑わしく、彼らのことばは曖昧である。その円環的な本はすなわち神なのだ。)さしあたり、古典的な格言を繰り返せばたりる。図書館は、その厳密な中心が任意の六角形であり、その円周は到達の不可能な球体である。
観念論にあまねく支配されているトレーンの住人が、もしこの図書館に迷い込んだら、このような主張をするということである。また、神秘主義者達が主張する「円環」的な本は、あきらかに「円環の廃墟」の概要に対応している。その本を読み始めると(本棚から引き抜くことが物理的にできるかどうかはおいて)、書かれたことは必ず起点に戻り、いつまでも終わらない。
「その円周は到達の不可能な球体である」とは、どういうことだろう? 図書館が無限に広いのなら、無限の距離を歩くことはできないため、到達できないというのはわかる。しかし、図書館の蔵書は有限で、どの本棚も隙間なく埋まっているのなら、必ずどこかで、本が足りなくなるはずなのだ。「わたし」が解答するとしていた問題は、ここにある。
さいごに「わたし」は、解答の提示にあたって、図書館が有限であると主張する人々に反論する。彼らは、六角形や本棚や階段が、見ていないうちに消えていると仮定している。「わたし」は、それは不合理なことだと切る。また、世界には限界がないと考える人々に対しても、「本の可能な数はかぎられていること」を忘れていると一刀両断する。そして「わたし」は古くからの問題、図書館は有限であるか無限であるかという問題に対し、以下のような解答を提出する。
図書館は無限であり周期的である。どの方向でもよい、永遠の旅人がそこを横切ったとすると、彼は数世紀後に、おなじ書物がおなじ無秩序さで繰り返し現われることを確認するだろう(繰り返されれば、無秩序も秩序に、「秩序」そのものになるはずだ)。この粋な希望のおかげで、わたしの孤独も華やぐのである。
図書館において人々が混乱したのは、その秩序の相があまりにも大きかったことが原因だったのだ……もちろんこれは「わたし」による一人称の語りのため、この解答が物語世界において正しいのかどうかは判らない。しかし、彼の語りを通して垣間見える図書館にどっぷりと浸かっていた読者は、解答を得て胸をなで下ろす。そもそもこの作品は論説文ではない。舞台も現実ではない。だからといってリアリティが欠如していい理由にはならないが、そもそも引用の不確かさを利用するほど猜疑的で巧妙なボルヘスが、正しいかどうか、などという些末な問題に腐心するだろうか? むしろ曖昧さを効果として取り入れ、幻想的であることを強調し、物語世界を薫り高いものにした筆致に、筆者は瞠目するのである……。
それぞれの短編に異なったかたちの無限が存在し、また互いに関連しているということは、読者はもう承知していらっしゃるだろう。筆者は「トレーン、ウクバール、オルビス・テルティウス」でフラクタル構造を引き合いに出した。他の二編についていうと、「円環の廃墟」はメビウスの輪、「バベルの図書館」はシンメトリーの趣がある。筆者は『伝奇集』のほかの作品においても、さまざまな類似や関連の気配をかぎ取ったが、それらを記述するとあまりにも長くなりすぎることと、怠惰なペン先とを理由に、残りの謎の探求は、この不出来な書評の奇特な読者に任せようと思う。濃厚なショコラの大粒は、まだあと十編以上も残っているのだから、独り占めするのは申し訳ない……と、惨めな修辞上の一致を試みてから、退散させていただく。すこしばかり、幸福な胃もたれがひどくなってきたのだ。
書評書籍
新着情報
-

- 2013/08/16[新着書評]
『きことわ』朝吹真理子
評者:千三屋
-

- 2013/08/15[新着書評]
『テルマエ・ロマエⅥ』ヤマザキマリ/「1~3巻は大傑作、4~6巻は残念な出来」
評者:新藤純子
-

- 2013/06/19[新着書評]
『高円寺 古本酒場ものがたり』狩野俊
評者:千三屋

- 2013/05/12[新着書評]
『フィフティ・シェイズ・ダーカー(上・下)』ELジェイムズ
評者:日向郁

- 2013/04/04[新着書評]
『クラウド・アトラス』デイヴィッド・ミッチェル
評者:千三屋

- 2013/02/18[新着書評]
『はぶらし』近藤史恵
評者:日向郁

- 2013/01/31[新着書評]
『知的唯仏論』宮崎哲弥・呉智英
評者:千三屋

- 2013/01/18[新着書評]
『秋田寛のグラフィックデザイン』アキタ・デザイン・カン
評者:千三屋

- 2013/01/17[新着書評]
『空白を満たしなさい』平野啓一郎
評者:長坂陽子

- 2013/01/15[新着書評]
『箱根駅伝を歩く』泉麻人
評者:千三屋

- 2013/01/11[新着書評]
『世界が終わるわけではなく』ケイト・アトキンソン
評者:藤井勉

- 2012/12/19[新着書評]
『デザインの本の本』秋田寛
評者:千三屋

- 2012/11/28[新着書評]
『ニール・ヤング自伝I』ニール・ヤング
評者:藤井勉

- 2012/11/22[新着書評]
『日本人はなぜ「黒ブチ丸メガネ」なのか』友利昴
評者:新藤純子

- 2012/11/21[新着書評]
『私にふさわしいホテル』柚木麻子
評者:長坂陽子

- 2012/11/15[新着書評]
『格差と序列の心理学 平等主義のパラドクス』池上知子
評者:新藤純子
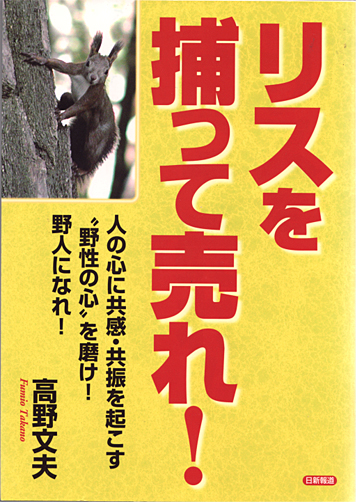
- 2012/11/09[イベントレポ]
兼業古本屋のできるまで。とみさわさん、なにをやってんすか

- 2012/11/08[新着書評]
『機龍警察 暗黒市場』月村了衛
評者:大谷暁生

- 2012/11/02[新着書評]
『なしくずしの死』L-F・セリーヌ
評者:藤田祥平

- 2012/10/31[新着書評]
『エコー・メイカー』リチャード・パワーズ
評者:藤井勉

- 2012/10/30[新着書評]
『文体練習』レーモン・クノー
評者:藤田祥平

- 2012/10/25[新着書評]
『生きのびるための建築』石山修武
評者:千三屋

- 2012/10/24[新着書評]
『占領都市 TOKYO YEAR ZERO Ⅱ』デイヴィッド・ピース
評者:大谷暁生

- 2012/10/19[新着書評]
『最後の授業 ぼくの命があるうちに』ランディ・パウシュ、ジェフリー・ザスロー
評者:日向郁

- 2012/10/18[新着書評]
『イタリア人と日本人、どっちがバカ?』ファブリツィオ・グラッセッリ
評者:相川藍

- 2012/10/17[イベントレポ]
ミステリー酒場スペシャル ローレンス・ブロック酒場Part1

- 2012/10/16[イベントレポ]
ブックレビューLIVE:杉江VS米光のどっちが売れるか!?

- 2012/10/15[イベントレポ]
ミステリ酒場スペシャル ローレンス・ブロック酒場三連発 PART2~泥棒バーニー、殺し屋ケラー編&ブロックおもてなし対策会議~

- 2012/10/15[新着書評]
『犬とハモニカ』江國香織
評者:長坂陽子

- 2012/10/10[新着書評]
『Papa told me cocohana ver.1 丘は花でいっぱい』榛野なな恵
評者:千三屋

- 2012/10/08[イベントレポ]
“その日”が来てからでは遅すぎる! あなたの知らないお葬式のすべて?ボッタクリの秘密から納得のエコ葬儀プランまで

- 2012/10/03[新着書評]
『青い脂』ウラジーミル・ソローキン
評者:藤井勉

- 2012/10/02[イベントレポ]
松本尚久さん、落語の楽しみ方を教えてください!

- 2012/10/01[新着書評]
『ヴァンパイア』岩井俊二
評者:長坂陽子

- 2012/09/25[新着書評]
『鬼談百景』小野不由美
評者:挟名紅治

- 2012/09/24[新着書評]
『ここは退屈迎えに来て』山内マリコ
評者:長坂陽子

- 2012/09/18[新着書評]
『最初の人間』アルベール・カミュ
評者:新藤純子

- 2012/09/14[新着書評]
『その日東京駅五時二十五分発』西川美和
評者:相川藍

- 2012/09/13[新着書評]
『無分別』オラシオ・カステジャーノス・モヤ
評者:藤井勉

- 2012/09/12[新着書評]
『鷲たちの盟約』(上下)アラン・グレン
評者:大谷暁生

- 2012/09/11[新着書評]
『ラブ・イズ・ア・ミックステープ』ロブ・シェフィールド
評者:日向郁

- 2012/09/10[新着書評]
『嵐のピクニック』本谷有希子
評者:長坂陽子

- 2012/09/07[新着書評]
『本当の経済の話をしよう』若田部昌澄、栗原裕一郎
評者:藤井勉

- 2012/09/05[新着書評]
『ひらいて』綿矢りさ
評者:長坂陽子

- 2012/09/04[新着書評]
『失脚/巫女の死 デュレンマット傑作選』フリードリヒ・デュレンマット
評者:藤井勉

- 2012/09/03[新着書評]
『かくも水深き不在』竹本健治
評者:蔓葉信博

- 2012/08/31[新着書評]
『わたしが眠りにつく前に』SJ・ワトソン
評者:長坂陽子

- 2012/08/28[新着書評]
『芸術実行犯』Chim↑Pom(チン↑ポム)
評者:相川藍

- 2012/08/27[新着書評]
『ぼくは勉強ができない』山田詠美
評者:姉崎あきか

- 2012/08/16[新着書評]
『オカルト 現れるモノ、隠れるモノ、見たいモノ』森達也
評者:長坂陽子

- 2012/08/10[新着書評]
『セックスなんか興味ない』きづきあきら サトウナンキ
評者:大谷暁生

- 2012/08/08[新着書評]
『深い疵』ネレ・ノイハウス
評者:挟名紅治

- 2012/08/07[新着書評]
【連載】 蔓葉信博「週末、たまにはビジネス書を」
第4回 小林直樹『ソーシャルリスク』 評者:蔓葉信博

- 2012/08/03[新着書評]
『はまむぎ』レーモン・クノー
評者:藤井勉

- 2012/08/02[新着書評]
『清須会議』三谷幸喜
評者:千三屋

- 2012/07/31[新着書評]
『岡崎京子の仕事集』岡崎京子(著)増渕俊之(編)
評者:相川藍

- 2012/07/28[新着書評]
『ことばの食卓』武田百合子
評者:杉江松恋

- 2012/07/18[新着書評]
『図説 死因百科』マイケル・ラルゴ
評者:大谷暁生

- 2012/07/13[新着書評]
『最果てアーケード』
小川洋子
評者:長坂陽子

- 2012/07/12[新着書評]
『なぜ戒名を自分でつけてもいいのか』橋爪大三郎
評者:千三屋

- 2012/07/05[新着書評]
『少年は残酷な弓を射る』(上・下)
ライオネル・シュライヴァー
評者:長坂陽子

- 2012/07/04[新着書評]
『未解決事件 グリコ・森永事件~捜査員300人の証言』NHKスペシャル取材班
評者:挟名紅治

- 2012/07/02[新着書評]
『女が嘘をつくとき』リュドミラ・ウリツカヤ
評者:藤井勉

- 2012/06/29[新着書評]
連載 蔓葉信博「週末、たまにはビジネス書を」
第3回 三浦展『第四の消費』 蔓葉信博

- 2012/06/27[新着書評]
『シフォン・リボン・シフォン』近藤史恵
評者:相川藍

- 2012/06/26[新着書評]
『湿地』アーナルデュル・インドリダソン
大谷暁生

- 2012/06/20[新着書評]
『彼女の存在、その破片』野中柊
長坂陽子

- 2012/06/15[新着書評]
『新人警官の掟』フェイ・ケラーマン
日向郁

- 2012/06/14[新着書評]
『俳優と超人形』ゴードン・クレイグ
千三屋

- 2012/06/13[新着書評]
『毒婦。 木嶋佳苗100日裁判傍聴記』北原みのり
長坂陽子

- 2012/06/12[新着書評]
『WOMBS』白井弓子
大谷暁生

- 2012/06/11[新着書評]
『21世紀の世界文学30冊を読む』都甲幸治
藤井勉

- 2012/06/08[新着書評]
『愛について』白岩玄
評者:相川藍

- 2012/06/06[新着書評]
『柔らかな犀の角ー山崎努の読書日記』山崎努
挟名紅治

- 2012/06/04[新着書評]
『夜をぶっとばせ』井上荒野
長坂陽子

- 2012/06/01[新着書評]
「七夜物語』川上弘美
長坂陽子

- 2012/05/23[新着書評]
「ピントがボケる音 OUT OF FOCUS, OUT OF SOUND』安田兼一
藤井勉

- 2012/05/21[新着書評]
「飼い慣らすことのできない幻獣たち」
『幻獣辞典』ホルヘ・ルイス・ボルヘス
藤田祥平

- 2012/05/16[新着書評]
連載「長坂陽子 ロマンスの神様願いを叶えて第18回」
「その名は自己満足」 長坂陽子

- 2012/03/30[新着書評]
連載「長坂陽子 ロマンスの神様願いを叶えて第17回」
「そのプライドが邪魔をする」 長坂陽子

- 2012/02/28[新着書評]
連載「長坂陽子 ロマンスの神様願いを叶えて第16回」
「恋のリスクマネジメント」 長坂陽子

- 2012/02/15[新着書評]
連載「長坂陽子 ロマンスの神様願いを叶えて第15回」
「非華奢女子の生きる道」 長坂陽子

- 2012/02/02[新着書評]
連載「長坂陽子 ロマンスの神様願いを叶えて第14回」
「パターン破りの効用」 長坂陽子

- 2012/01/31[新着書評]
『最高に美しい住宅をつくる方法』彦根明
評者:相川藍

- 2012/01/20[新着書評]
『ペット・サウンズ』ジム・フジーリ
評者:藤井勉

- 2012/01/17[新着書評]
連載「長坂陽子 ロマンスの神様願いを叶えて第13回」
胸だけ見ててもモテ期はこない 長坂陽子

- 2012/01/11[新着書評]
連載「長坂陽子 ロマンスの神様願いを叶えて第12回」
「恋で美しくなる」は本当か 長坂陽子

- 2012/01/10[新着書評]
「旧式のプライバシー」
『大阪の宿』水上滝太郎
藤田祥平
Internet Explorerをご利用の場合はバージョン6以上でご覧ください。

















