Invitation

先日の芥川賞・直木賞発表の日、日経新聞の夕刊に保坂和志のコラムが掲載されていた。彼は小説を書きたい人に「書いてあることは裏読みしたり、比喩的に解釈したりせずに、真に受けろ」とアドバイスしているそうだ。真に受けることで、自分の価値観・世界観が変わるという。
なるほど、小説家にはそういうピュアな感受性が必要なのだなと思う。たとえ騙されても傷ついても、世の中のあらゆる事象を真に受けることで、成長できるということか。いや万が一、間違ったことや曲がったものを真に受けたとしても、血を流すのは間違ったことや曲がったもののほうであるはずだ。つまりピュアさは武器になる。
8人の女性作家によるアンソロジーである本書においては、江國香織、小川洋子、川上弘美による最初の3編に、このようなピュアな強さが感じられる。続く桐野夏生、小池真理子、髙樹のぶ子の3編は、<あやまち>や<しがらみ>や<あきらめ>といった痛みのニュアンスを踏まえた上で、パワフルに世の中と折り合いをつけていく現実的な小説だ。最後の2編、髙村薫と林真理子の作品には、さらに<ウソ>や<演技>といった大人の複雑な心情がからむ。
本書の並び順は作家名のあいうえお順だが、偶然にも、順番に読むことで、女性の感覚の奥深さや怖さが次第にあばかれる構成になっているのだ。それぞれの作品の魅力を表す言葉として、受容力、理解力、妄想力、憑依力、自立力、執着力、造形力、現役力というキーワードを当てはめてみた。
1. 受容力
『蛾』江國香織
夫に出ていかれた房子の「まるで保護者のいない子供」のような暮らしぶり。周囲のネガティブな状況をすべて自分で引き受けてしまう女、引き受けさせられてしまう女の話だ。つまり彼女は<つけこまれる女>であり、その素直さは『Invitation』の幕開けにふさわしい。パトリシア・ハイスミスばりに淡々と描かれる不気味な日常と「自分だけが世界からはみだしている」ことへの恐怖。房子のピュアさには毅然とした美しさすら感じられる。
2. 理解力
『巨人の接待』小川洋子
世界的な人気作家の来日騒動。巨人と呼ばれるその作家は、バルカン半島の小国の内陸部丘陵地帯に点在する村々だけで通用する地域語しか使わない。来日した巨人は何を話し、どんな印象を人々に与えるのか。そしてその文学の本質は? 巨人研究の第一人者に代わり急遽通訳をすることになった「私」と、正確に訳せといらだつ編集長、そして「私」にだけ心を開く巨人。言葉を訳さないことも、通訳の重要な仕事なのだろう。
3. 妄想力
『天にまします吾らが父ヨ、世界人類ガ、幸福デ、ありますヨウニ』川上弘美
「二十数年前に、ちょっとの間だけ、恋人みたいな関係だった」関谷くんへの思いと、その後のいきさつを一人語りする小説家の「わたし」。二人の関係は、いくつもの選択肢の中で盛り上がったり盛り下がったりする。結ばれたいと思った人とは結ばれたほうがいいのか、それとも一人相撲の妄想として楽しみ続けるのが賢明なのか。彼女にとっていちばん怖いのは、恋愛に傷つきすぎて、妄想を抱けなくなってしまうことなのだった。
4. 憑依力
『告白』桐野夏生
薩摩の煙草商人の息子ヤジローは、ある罪を犯し、ポルトガル船で日本を脱出する。ゴアに着き、ほっとしたのも束の間、ヤジローは日本語を話す貧相な老人に出会ってしまう。「日本人ではない何者かになりたかった」彼は、次第に日本語による語りの魅力に絡め取られてゆく。私たちは自由である一方、どこへ行っても自国の歴史や言葉の記憶から逃れられないのである。その連帯感の心地よさと鬱陶しさといったら。
5. 自立力
『捨てる』小池真理子
夫に黙って部屋を出てゆく女の寂しさと清々しさ。引っ越しを請け負う若い男の描写が心に残る。この男、魅力的で頼りになるが、女との接点はそれ以上でもなく以下でもない。「気持ちよく捨てちゃってね、と言おうとして、女は喉を塞がれたようになった。捨ててもらうのは青いゴミ袋の中身ではなく、自分自身であるような気がした」。だが、彼女の未来は明るいと思う。捨てるものさえあれば、その推進力で、女は前に進めるのだ。
6. 執着力
『夕陽と珊瑚』髙樹のぶ子
痴呆性高齢者のグループホームを舞台にしたミステリアスな作品。短大を卒業してヘルパー2級をとった由美の介護の日々が描写されるが、担当となった新入りの入居者ミツ子の恋の秘密が発覚し、物語は一転する。由美は、ミツ子がその名を口にした男に連絡をとり、生涯の最後に会いたがっている女性がいることを伝えるのだった。嘘みたいな話なのに、これが本当の介護かもしれないとまで思わせる力があり、痛快のひとこと。
7. 造形力
『カワイイ、アナタ』髙村薫
「小生がまだ二十代だったころに、ある先輩から聞いた話」だが、その話は、先輩がある男(山田某)から聞いたもの。つまりこれは、ある男(山田某)→先輩→小生という流れで語り継がれた話である。先輩の話は驚くほど詳細だが「詳細だったのはいったい山田某の話なのか、それともそれを聞いた先輩の記憶なのか」不明。また「ここに何らかの事件を直接疑わせる事実はない。強いていえば、すべてが疑わしいだけであり、疑わしいわりには話が詳細すぎるのが、何より疑わしいというだけ」である。物語の曖昧さと強さに関するミステリー。
8. 現役力
『リハーサル』林真理子
孫がもうすぐ生まれる52歳の未知果には、近藤という愛人がいる。「五十二歳の未知果は五十三歳になり、次の年は五十四歳になり、そしてすぐに六十歳の時がやってくる。そこからは女の暗黒時代が始まるはずであった。もう恋やセックス、などというものは頭から消して、ひたすら楽しく老いることだけを考えなくてはならないみじめな歳月。が、近藤を失くしたら、その暗黒は明日から始まる。未知果はそれを恐れているのだ」。狡さやふしだらさを超越し、切実な女心をとらえた一編。リハーサルというタイトルの真意が強烈!
おすすめ本書評・紹介書籍
-
- Invitation
文藝春秋 [小説] 国内
2010.01 版型:B6
価格:1,470円(税込)
>>詳細を見る
新着情報
-

- 2013/08/16[新着書評]
『きことわ』朝吹真理子
評者:千三屋
-

- 2013/08/15[新着書評]
『テルマエ・ロマエⅥ』ヤマザキマリ/「1~3巻は大傑作、4~6巻は残念な出来」
評者:新藤純子
-

- 2013/06/19[新着書評]
『高円寺 古本酒場ものがたり』狩野俊
評者:千三屋

- 2013/05/12[新着書評]
『フィフティ・シェイズ・ダーカー(上・下)』ELジェイムズ
評者:日向郁

- 2013/04/04[新着書評]
『クラウド・アトラス』デイヴィッド・ミッチェル
評者:千三屋

- 2013/02/18[新着書評]
『はぶらし』近藤史恵
評者:日向郁

- 2013/01/31[新着書評]
『知的唯仏論』宮崎哲弥・呉智英
評者:千三屋

- 2013/01/18[新着書評]
『秋田寛のグラフィックデザイン』アキタ・デザイン・カン
評者:千三屋

- 2013/01/17[新着書評]
『空白を満たしなさい』平野啓一郎
評者:長坂陽子

- 2013/01/15[新着書評]
『箱根駅伝を歩く』泉麻人
評者:千三屋

- 2013/01/11[新着書評]
『世界が終わるわけではなく』ケイト・アトキンソン
評者:藤井勉

- 2012/12/19[新着書評]
『デザインの本の本』秋田寛
評者:千三屋

- 2012/11/28[新着書評]
『ニール・ヤング自伝I』ニール・ヤング
評者:藤井勉

- 2012/11/22[新着書評]
『日本人はなぜ「黒ブチ丸メガネ」なのか』友利昴
評者:新藤純子

- 2012/11/21[新着書評]
『私にふさわしいホテル』柚木麻子
評者:長坂陽子

- 2012/11/15[新着書評]
『格差と序列の心理学 平等主義のパラドクス』池上知子
評者:新藤純子
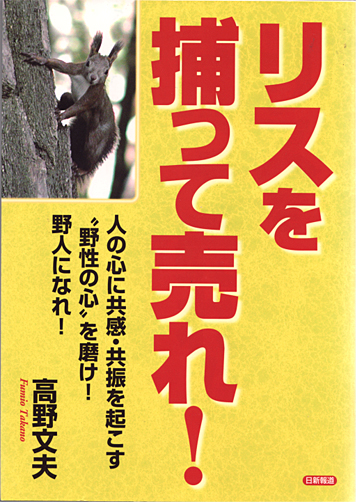
- 2012/11/09[イベントレポ]
兼業古本屋のできるまで。とみさわさん、なにをやってんすか

- 2012/11/08[新着書評]
『機龍警察 暗黒市場』月村了衛
評者:大谷暁生

- 2012/11/02[新着書評]
『なしくずしの死』L-F・セリーヌ
評者:藤田祥平

- 2012/10/31[新着書評]
『エコー・メイカー』リチャード・パワーズ
評者:藤井勉

- 2012/10/30[新着書評]
『文体練習』レーモン・クノー
評者:藤田祥平

- 2012/10/25[新着書評]
『生きのびるための建築』石山修武
評者:千三屋

- 2012/10/24[新着書評]
『占領都市 TOKYO YEAR ZERO Ⅱ』デイヴィッド・ピース
評者:大谷暁生

- 2012/10/19[新着書評]
『最後の授業 ぼくの命があるうちに』ランディ・パウシュ、ジェフリー・ザスロー
評者:日向郁

- 2012/10/18[新着書評]
『イタリア人と日本人、どっちがバカ?』ファブリツィオ・グラッセッリ
評者:相川藍

- 2012/10/17[イベントレポ]
ミステリー酒場スペシャル ローレンス・ブロック酒場Part1

- 2012/10/16[イベントレポ]
ブックレビューLIVE:杉江VS米光のどっちが売れるか!?

- 2012/10/15[イベントレポ]
ミステリ酒場スペシャル ローレンス・ブロック酒場三連発 PART2~泥棒バーニー、殺し屋ケラー編&ブロックおもてなし対策会議~

- 2012/10/15[新着書評]
『犬とハモニカ』江國香織
評者:長坂陽子

- 2012/10/10[新着書評]
『Papa told me cocohana ver.1 丘は花でいっぱい』榛野なな恵
評者:千三屋

- 2012/10/08[イベントレポ]
“その日”が来てからでは遅すぎる! あなたの知らないお葬式のすべて?ボッタクリの秘密から納得のエコ葬儀プランまで

- 2012/10/03[新着書評]
『青い脂』ウラジーミル・ソローキン
評者:藤井勉

- 2012/10/02[イベントレポ]
松本尚久さん、落語の楽しみ方を教えてください!

- 2012/10/01[新着書評]
『ヴァンパイア』岩井俊二
評者:長坂陽子

- 2012/09/25[新着書評]
『鬼談百景』小野不由美
評者:挟名紅治

- 2012/09/24[新着書評]
『ここは退屈迎えに来て』山内マリコ
評者:長坂陽子

- 2012/09/18[新着書評]
『最初の人間』アルベール・カミュ
評者:新藤純子

- 2012/09/14[新着書評]
『その日東京駅五時二十五分発』西川美和
評者:相川藍

- 2012/09/13[新着書評]
『無分別』オラシオ・カステジャーノス・モヤ
評者:藤井勉

- 2012/09/12[新着書評]
『鷲たちの盟約』(上下)アラン・グレン
評者:大谷暁生

- 2012/09/11[新着書評]
『ラブ・イズ・ア・ミックステープ』ロブ・シェフィールド
評者:日向郁

- 2012/09/10[新着書評]
『嵐のピクニック』本谷有希子
評者:長坂陽子

- 2012/09/07[新着書評]
『本当の経済の話をしよう』若田部昌澄、栗原裕一郎
評者:藤井勉

- 2012/09/05[新着書評]
『ひらいて』綿矢りさ
評者:長坂陽子

- 2012/09/04[新着書評]
『失脚/巫女の死 デュレンマット傑作選』フリードリヒ・デュレンマット
評者:藤井勉

- 2012/09/03[新着書評]
『かくも水深き不在』竹本健治
評者:蔓葉信博

- 2012/08/31[新着書評]
『わたしが眠りにつく前に』SJ・ワトソン
評者:長坂陽子

- 2012/08/28[新着書評]
『芸術実行犯』Chim↑Pom(チン↑ポム)
評者:相川藍

- 2012/08/27[新着書評]
『ぼくは勉強ができない』山田詠美
評者:姉崎あきか

- 2012/08/16[新着書評]
『オカルト 現れるモノ、隠れるモノ、見たいモノ』森達也
評者:長坂陽子

- 2012/08/10[新着書評]
『セックスなんか興味ない』きづきあきら サトウナンキ
評者:大谷暁生

- 2012/08/08[新着書評]
『深い疵』ネレ・ノイハウス
評者:挟名紅治

- 2012/08/07[新着書評]
【連載】 蔓葉信博「週末、たまにはビジネス書を」
第4回 小林直樹『ソーシャルリスク』 評者:蔓葉信博

- 2012/08/03[新着書評]
『はまむぎ』レーモン・クノー
評者:藤井勉

- 2012/08/02[新着書評]
『清須会議』三谷幸喜
評者:千三屋

- 2012/07/31[新着書評]
『岡崎京子の仕事集』岡崎京子(著)増渕俊之(編)
評者:相川藍

- 2012/07/28[新着書評]
『ことばの食卓』武田百合子
評者:杉江松恋

- 2012/07/18[新着書評]
『図説 死因百科』マイケル・ラルゴ
評者:大谷暁生

- 2012/07/13[新着書評]
『最果てアーケード』
小川洋子
評者:長坂陽子

- 2012/07/12[新着書評]
『なぜ戒名を自分でつけてもいいのか』橋爪大三郎
評者:千三屋

- 2012/07/05[新着書評]
『少年は残酷な弓を射る』(上・下)
ライオネル・シュライヴァー
評者:長坂陽子

- 2012/07/04[新着書評]
『未解決事件 グリコ・森永事件~捜査員300人の証言』NHKスペシャル取材班
評者:挟名紅治

- 2012/07/02[新着書評]
『女が嘘をつくとき』リュドミラ・ウリツカヤ
評者:藤井勉

- 2012/06/29[新着書評]
連載 蔓葉信博「週末、たまにはビジネス書を」
第3回 三浦展『第四の消費』 蔓葉信博

- 2012/06/27[新着書評]
『シフォン・リボン・シフォン』近藤史恵
評者:相川藍

- 2012/06/26[新着書評]
『湿地』アーナルデュル・インドリダソン
大谷暁生

- 2012/06/20[新着書評]
『彼女の存在、その破片』野中柊
長坂陽子

- 2012/06/15[新着書評]
『新人警官の掟』フェイ・ケラーマン
日向郁

- 2012/06/14[新着書評]
『俳優と超人形』ゴードン・クレイグ
千三屋

- 2012/06/13[新着書評]
『毒婦。 木嶋佳苗100日裁判傍聴記』北原みのり
長坂陽子

- 2012/06/12[新着書評]
『WOMBS』白井弓子
大谷暁生

- 2012/06/11[新着書評]
『21世紀の世界文学30冊を読む』都甲幸治
藤井勉

- 2012/06/08[新着書評]
『愛について』白岩玄
評者:相川藍

- 2012/06/06[新着書評]
『柔らかな犀の角ー山崎努の読書日記』山崎努
挟名紅治

- 2012/06/04[新着書評]
『夜をぶっとばせ』井上荒野
長坂陽子

- 2012/06/01[新着書評]
「七夜物語』川上弘美
長坂陽子

- 2012/05/23[新着書評]
「ピントがボケる音 OUT OF FOCUS, OUT OF SOUND』安田兼一
藤井勉

- 2012/05/21[新着書評]
「飼い慣らすことのできない幻獣たち」
『幻獣辞典』ホルヘ・ルイス・ボルヘス
藤田祥平

- 2012/05/16[新着書評]
連載「長坂陽子 ロマンスの神様願いを叶えて第18回」
「その名は自己満足」 長坂陽子

- 2012/03/30[新着書評]
連載「長坂陽子 ロマンスの神様願いを叶えて第17回」
「そのプライドが邪魔をする」 長坂陽子

- 2012/02/28[新着書評]
連載「長坂陽子 ロマンスの神様願いを叶えて第16回」
「恋のリスクマネジメント」 長坂陽子

- 2012/02/15[新着書評]
連載「長坂陽子 ロマンスの神様願いを叶えて第15回」
「非華奢女子の生きる道」 長坂陽子

- 2012/02/02[新着書評]
連載「長坂陽子 ロマンスの神様願いを叶えて第14回」
「パターン破りの効用」 長坂陽子

- 2012/01/31[新着書評]
『最高に美しい住宅をつくる方法』彦根明
評者:相川藍

- 2012/01/20[新着書評]
『ペット・サウンズ』ジム・フジーリ
評者:藤井勉

- 2012/01/17[新着書評]
連載「長坂陽子 ロマンスの神様願いを叶えて第13回」
胸だけ見ててもモテ期はこない 長坂陽子

- 2012/01/11[新着書評]
連載「長坂陽子 ロマンスの神様願いを叶えて第12回」
「恋で美しくなる」は本当か 長坂陽子

- 2012/01/10[新着書評]
「旧式のプライバシー」
『大阪の宿』水上滝太郎
藤田祥平
Internet Explorerをご利用の場合はバージョン6以上でご覧ください。
















