ブラック・ジャック/火の鳥/MWほか

去年は生誕80年、今年2009年は没後20年ということで、映画、アニメーション、テレビドラマと、手塚治虫作品のメディアミックス展開がまたしても活況を呈しています。しかし、たんなる「顔に向こう傷のある格好いいヒーロー」ではないブラック・ジャック、「お茶目でキュートなマスコットキャラ」ではないピノコ、「かわいい擬人化動物キャラ」ではないレオ、「よいこのヒーロー」ではないアトムetc……に出会い、巻頭から全力投球で繰り出されるトラウマ描写の数々に胸をえぐられる体験は、やはり原作マンガからしか得られません。
というわけで、今回は、愛と平和とエコとヒューマニズムは一旦置いておくことにして、地獄のトラウマ再生装置としての手塚マンガについて。
手塚治虫の語る物語は、多くの場合、巨大災害や大量殺戮など、強烈なトラウマをもたらさずにはおかないカタストロフィの「後」から始まります。
1948年に発表された長編第二作の『地底国の怪人』(講談社手塚治虫漫画全集253巻)の扉ページをめくると、見開き2ページの大ゴマをぶち抜いて、火を噴きながら墜落してゆく旅客機がいきなり出現します。従来のこども向けマンガに出てくる飛行機や車や汽車や船が、途中に多少のスリルが待ち受けているとしても、最後には無事の帰還が保証された愉快な冒険の旅にこどもたちを連れていってくれる、楽しくて安全な「のりもの」と決まっていた時代、最初の見開きでいきなり盛大に墜落して死体の山を積んでしまう手塚治虫の飛行機が、驚天動地のショックを与えたことは、60年過ぎた現在でも想像に難くありません。
『地底国の怪人』では、冒頭の飛行機墜落、そして乗客のひとりだった主人公ジョン君の父親の死に加えて、マッドサイエンティストな博士たちがいたいけな子ウサギを捕まえて、どう見ても拷問でしかない「実験」を数ページにわたってくり広げた結果、人間並みの知能を有するウサギ怪人「ミイちゃん」に改造してしまうという、これまたショッキングな事件が続きます。以後、人々に「ウサギのおばけ」と忌み嫌われ、排斥されながらも、「ぼくは人間だい」と信じて奮闘するミイちゃんの健気さが、ラストの悲劇に至るまで、読者の涙を誘います。
かわいい擬人化動物キャラクター自体は、この作品の発表されるはるか以前から、アニメやマンガの世界にはごくありふれた存在でした。しかし、それを「トラウマ的な出来事を体験した結果、ある種の《怪物》と化してしまった存在」として新たに捉えなおした点に、デビュー間もない手塚治虫の、今もなお新鮮な独創性が発揮されています。
驚くべき多彩さを誇る手塚治虫の膨大な作品群には、しかし、ある強いモチーフの反復を見出すことができます。それは、物語の始まりと同時に到来する凄惨なカタストロフィを辛うじて生き延びつつ、癒しようのない深いトラウマを負った主人公の存在です。たとえば、『ジャングル大帝』(講談社手塚治虫漫画全集1~3巻ほか)のレオは、父パンジャが虐殺され、毛皮だけが残された後に生まれた「二代目のジャングル大帝」ですし、『鉄腕アトム』(秋田書店1〜21巻、別巻1・2巻ほか)のアトムは、事故死した後にロボットとして復活し、そして父に捨てられた「死んだはずの子供」でした。
手塚治虫作品の主人公たちの負うトラウマは、しばしば物理的な痕跡としてその肉体に刻み込まれることになります。『どろろ』の、出生時に妖怪に奪われた48の身体器官を奪い返すために旅を続ける剣豪・百鬼丸は、まさに手塚治虫ならではの尋常ならざる設定のヒーローですし、『ブラック・ジャック』のブラック・ジャックは、少年時代に母親とともに不発弾の爆発に巻き込まれ、焼け爛れた全身の皮膚を移植手術で補われて死の淵から生還したという前歴をもち(第115話「不発弾」/講談社手塚治虫漫画全集DX版405巻ほか)、その助手ないしはマスコットのピノコにしても、初登場エピソードは、双子の姉の体にできた「畸形嚢腫」の内部にバラバラの状態で収まっていたところを、ブラック・ジャックに摘出され、幼女の形に組み立てられるという凄惨なものでした(第12話「畸形嚢腫」/講談社手塚治虫漫画全集DX版414巻ほか)。
癒しがたいトラウマを残さずにはおかないカタストロフィから物語を始めることへの手塚治虫のこだわりを、別の側面から示すものとして、「大量殺戮をかろうじて生き延びた創作者」のモチーフを扱う一連の作品をあげることができるでしょう。『ブラック・ジャック』の第86話「絵が死んでいる!」(講談社手塚治虫漫画全集DX版408巻ほか)では、南洋の平和な島を突如壊滅させた核実験から唯一生き延びた画家が、放射線障害による断末魔の苦しみの中で、核爆発のもたらした地獄絵図を描き残そうとします。このエピソードの原型ともいえる短編「ドオベルマン」(講談社手塚治虫漫画全集80巻『SFファンシーフリー』)では、ある滅亡した惑星の住民によって、「かれらの歴史画を描き残す」ために選ばれた画家ドオベルマンが、文明の誕生から最終戦争、そして滅亡に至る過程を憑かれたようにキャンバスに描きつづけた果てに、精根尽きて息絶えてゆきます。
この「大量殺戮を生き延びた創作者」のモチーフをさらに壮大に展開した作品が、『火の鳥 2 未来編』、そして『MW』であるといえるでしょう。この両作品においては、大量殺戮から唯一生き延びた者たちの目的は、「絵画」という代替物を創作することではなく、「カタストロフィによって失われた対象」、あるいは「カタストロフィ」それ自体を創作することへとスケールアップすることになります。
『火の鳥 2 未来編』(朝日新聞出版ほか)では、最終核戦争によって地球上のあらゆる生命が死に絶えた後、火の鳥に永遠の生命を与えられてひとり生き残った主人公・山之辺マサトが、耐えがたい長い孤独の歳月を通じて、失われた生命の再生を目的にさまざまな試行錯誤を重ねます。しかし、マサトの涙ぐましい努力の結果としてもたらされるのは、不完全な生命の複製が誕生しては、たちまち悲惨な最期をとげるという、地獄のような反復でしかありません。『火の鳥』といえば「生命讃歌」ということになっていて、『未来編』にもそれらしきハッピーエンドが用意されてはいるのですが、しかし、今もなお強烈な読後感~トラウマを残すのは、過大な責務を負わされ、グロテスクなできそこないの複製しか生み出すことができないにもかかわらず、なおも徒労を続けざるをえない孤独な創作者の絶望の深さです。
一方、『MW』(講談社手塚治虫漫画全集301~303巻ほか)の主人公・結城美知夫は、幼い頃、米軍基地のある孤島にて、住民全員を殺戮した毒ガス漏出事故に巻き込まれ、成長した後は、自らの手でその毒ガス「MW」を大量複製し、自分自身の死とともに全世界を滅亡させるという究極の目的のために、手段を選ばない犯罪を重ねてゆきます。バイセクシュアルの女装の達人にして、残忍な殺人者という、手塚治虫作品の主人公たちの中でもとりわけエキセントリックな人物である結城もまた、自己の凄惨な体験のトラウマを「作品」化するという望みに憑かれた「創作者」であり、その意味において、きわめて手塚治虫的なヒーローのひとりなのです。
大量殺戮をひとり生き延びたという孤独なトラウマを、創作という作業を介して、複数の他者に共有させるという不可能な望みに憑かれた「創作者」たち。手塚治虫本人が、そうした「創作者」のひとりであることは、自身が動員学徒として体験した大阪大空襲の凄惨な記憶を(虚構をまじえつつ)物語る短編「紙の砦」を読めばおのずと明らかです。
若き日の手塚治虫が「大寒鉄郎(おおさむてつろう)」として主人公をつとめる自伝的短編「紙の砦」「すきっ腹のブルース」をはじめ、戦争体験に基づく作品群を収録した祥伝社新書『手塚治虫「戦争漫画」傑作選』1・2は、総動員戦と敗戦というカタストロフィの後に本格的な創作活動を開始し、「肉体的な痕跡としての、あるいは創作物としての過去のトラウマのよみがえり」というモチーフに憑かれつづけた手塚治虫という作家を考えるにあたって、重要な意義をもつアンソロジーといえるでしょう。
前掲書『手塚治虫「戦争漫画」傑作選』2に収録された短編「カノン」の、30年前と変わらぬ姿の死者たちに、「あの日家に帰れたのはカノンだけ、ずるい」と屈託なく語りかけられて絶句する、ただ一人生き残ってしまった平凡な中年男の孤独は、地球上に唯一生き残った生命体として、数十億年にわたる不毛な歳月の流れに耐えることを余儀なくされる『火の鳥 未来編』の山之辺マサトの壮大な孤独よりも、もしかしたらより残酷なものといえるのかもしれません。癒しがたい孤独なトラウマを「作品」として反復し、そこに否応なしに他者を巻き込んでゆくという地獄のような営みを通じてこそ、解放への希望が生まれるという逆説の力強さに、「戦後の物語マンガ」の始祖としての手塚治虫の矜持がみなぎっています。
おすすめ本書評・紹介書籍
-
- 手塚治虫漫画全集 253 地底国の怪人
講談社 [マンガ・アニメ] 国内
1982.09 版型:コミック
価格:541円(税込)
>>詳細を見る
-
- 手塚治虫漫画全集 1 ジャングル大帝 1
講談社 [マンガ・アニメ] 国内
1977.06 版型:コミック
価格:561円(税込)
>>詳細を見る
-
- 鉄腕アトム 1
秋田書店 /Sunday comics [マンガ・アニメ] 国内
1999.06 版型:コミック
価格:440円(税込)
>>詳細を見る
-
- 手塚治虫漫画全集 405 DX版 ブラック・ジャック 5
講談社 [マンガ・アニメ] 国内
2004.09 版型:コミック
価格:693円(税込)
>>詳細を見る
-
- 手塚治虫漫画全集 408 DX版 ブラック・ジャック 8
講談社 [マンガ・アニメ] 国内
2004.10 版型:コミック
価格:693円(税込)
>>詳細を見る
-
- 手塚治虫漫画全集 414 DX版 ブラック・ジャック 14
講談社 [マンガ・アニメ] 国内
2004.12 版型:コミック
価格:693円(税込)
>>詳細を見る
-
- 手塚治虫漫画全集 80 SFファンシーフリー
講談社 [マンガ・アニメ] 国内
1979.01 版型:コミック
価格:591円(税込)
>>詳細を見る
-
- 手塚治虫漫画全集 301 MW 1
講談社 [マンガ・アニメ] 国内
1993.01 版型:コミック
価格:591円(税込)
>>詳細を見る
-
- 手塚治虫漫画全集 302 MW 2
講談社 [マンガ・アニメ] 国内
1993.02 版型:コミック
価格:591円(税込)
>>詳細を見る
-
- 手塚治虫漫画全集 303 MW 3
講談社 [マンガ・アニメ] 国内
1993.03 版型:コミック
価格:561円(税込)
>>詳細を見る
-
- 手塚治虫「戦争漫画」傑作選
祥伝社 /祥伝社新書 [マンガ・アニメ] 国内
2007.08 版型:新書
価格:788円(税込)
>>詳細を見る
-
- 手塚治虫「戦争漫画」傑作選 2
祥伝社 /祥伝社新書 [マンガ・アニメ] 国内
2007.09 版型:新書
価格:788円(税込)
>>詳細を見る
新着情報
-

- 2013/08/16[新着書評]
『きことわ』朝吹真理子
評者:千三屋
-

- 2013/08/15[新着書評]
『テルマエ・ロマエⅥ』ヤマザキマリ/「1~3巻は大傑作、4~6巻は残念な出来」
評者:新藤純子
-

- 2013/06/19[新着書評]
『高円寺 古本酒場ものがたり』狩野俊
評者:千三屋

- 2013/05/12[新着書評]
『フィフティ・シェイズ・ダーカー(上・下)』ELジェイムズ
評者:日向郁

- 2013/04/04[新着書評]
『クラウド・アトラス』デイヴィッド・ミッチェル
評者:千三屋

- 2013/02/18[新着書評]
『はぶらし』近藤史恵
評者:日向郁

- 2013/01/31[新着書評]
『知的唯仏論』宮崎哲弥・呉智英
評者:千三屋

- 2013/01/18[新着書評]
『秋田寛のグラフィックデザイン』アキタ・デザイン・カン
評者:千三屋

- 2013/01/17[新着書評]
『空白を満たしなさい』平野啓一郎
評者:長坂陽子

- 2013/01/15[新着書評]
『箱根駅伝を歩く』泉麻人
評者:千三屋

- 2013/01/11[新着書評]
『世界が終わるわけではなく』ケイト・アトキンソン
評者:藤井勉

- 2012/12/19[新着書評]
『デザインの本の本』秋田寛
評者:千三屋

- 2012/11/28[新着書評]
『ニール・ヤング自伝I』ニール・ヤング
評者:藤井勉

- 2012/11/22[新着書評]
『日本人はなぜ「黒ブチ丸メガネ」なのか』友利昴
評者:新藤純子

- 2012/11/21[新着書評]
『私にふさわしいホテル』柚木麻子
評者:長坂陽子

- 2012/11/15[新着書評]
『格差と序列の心理学 平等主義のパラドクス』池上知子
評者:新藤純子
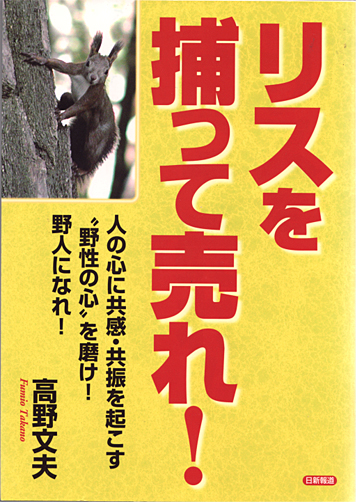
- 2012/11/09[イベントレポ]
兼業古本屋のできるまで。とみさわさん、なにをやってんすか

- 2012/11/08[新着書評]
『機龍警察 暗黒市場』月村了衛
評者:大谷暁生

- 2012/11/02[新着書評]
『なしくずしの死』L-F・セリーヌ
評者:藤田祥平

- 2012/10/31[新着書評]
『エコー・メイカー』リチャード・パワーズ
評者:藤井勉

- 2012/10/30[新着書評]
『文体練習』レーモン・クノー
評者:藤田祥平

- 2012/10/25[新着書評]
『生きのびるための建築』石山修武
評者:千三屋

- 2012/10/24[新着書評]
『占領都市 TOKYO YEAR ZERO Ⅱ』デイヴィッド・ピース
評者:大谷暁生

- 2012/10/19[新着書評]
『最後の授業 ぼくの命があるうちに』ランディ・パウシュ、ジェフリー・ザスロー
評者:日向郁

- 2012/10/18[新着書評]
『イタリア人と日本人、どっちがバカ?』ファブリツィオ・グラッセッリ
評者:相川藍

- 2012/10/17[イベントレポ]
ミステリー酒場スペシャル ローレンス・ブロック酒場Part1

- 2012/10/16[イベントレポ]
ブックレビューLIVE:杉江VS米光のどっちが売れるか!?

- 2012/10/15[イベントレポ]
ミステリ酒場スペシャル ローレンス・ブロック酒場三連発 PART2~泥棒バーニー、殺し屋ケラー編&ブロックおもてなし対策会議~

- 2012/10/15[新着書評]
『犬とハモニカ』江國香織
評者:長坂陽子

- 2012/10/10[新着書評]
『Papa told me cocohana ver.1 丘は花でいっぱい』榛野なな恵
評者:千三屋

- 2012/10/08[イベントレポ]
“その日”が来てからでは遅すぎる! あなたの知らないお葬式のすべて?ボッタクリの秘密から納得のエコ葬儀プランまで

- 2012/10/03[新着書評]
『青い脂』ウラジーミル・ソローキン
評者:藤井勉

- 2012/10/02[イベントレポ]
松本尚久さん、落語の楽しみ方を教えてください!

- 2012/10/01[新着書評]
『ヴァンパイア』岩井俊二
評者:長坂陽子

- 2012/09/25[新着書評]
『鬼談百景』小野不由美
評者:挟名紅治

- 2012/09/24[新着書評]
『ここは退屈迎えに来て』山内マリコ
評者:長坂陽子

- 2012/09/18[新着書評]
『最初の人間』アルベール・カミュ
評者:新藤純子

- 2012/09/14[新着書評]
『その日東京駅五時二十五分発』西川美和
評者:相川藍

- 2012/09/13[新着書評]
『無分別』オラシオ・カステジャーノス・モヤ
評者:藤井勉

- 2012/09/12[新着書評]
『鷲たちの盟約』(上下)アラン・グレン
評者:大谷暁生

- 2012/09/11[新着書評]
『ラブ・イズ・ア・ミックステープ』ロブ・シェフィールド
評者:日向郁

- 2012/09/10[新着書評]
『嵐のピクニック』本谷有希子
評者:長坂陽子

- 2012/09/07[新着書評]
『本当の経済の話をしよう』若田部昌澄、栗原裕一郎
評者:藤井勉

- 2012/09/05[新着書評]
『ひらいて』綿矢りさ
評者:長坂陽子

- 2012/09/04[新着書評]
『失脚/巫女の死 デュレンマット傑作選』フリードリヒ・デュレンマット
評者:藤井勉

- 2012/09/03[新着書評]
『かくも水深き不在』竹本健治
評者:蔓葉信博

- 2012/08/31[新着書評]
『わたしが眠りにつく前に』SJ・ワトソン
評者:長坂陽子

- 2012/08/28[新着書評]
『芸術実行犯』Chim↑Pom(チン↑ポム)
評者:相川藍

- 2012/08/27[新着書評]
『ぼくは勉強ができない』山田詠美
評者:姉崎あきか

- 2012/08/16[新着書評]
『オカルト 現れるモノ、隠れるモノ、見たいモノ』森達也
評者:長坂陽子

- 2012/08/10[新着書評]
『セックスなんか興味ない』きづきあきら サトウナンキ
評者:大谷暁生

- 2012/08/08[新着書評]
『深い疵』ネレ・ノイハウス
評者:挟名紅治

- 2012/08/07[新着書評]
【連載】 蔓葉信博「週末、たまにはビジネス書を」
第4回 小林直樹『ソーシャルリスク』 評者:蔓葉信博

- 2012/08/03[新着書評]
『はまむぎ』レーモン・クノー
評者:藤井勉

- 2012/08/02[新着書評]
『清須会議』三谷幸喜
評者:千三屋

- 2012/07/31[新着書評]
『岡崎京子の仕事集』岡崎京子(著)増渕俊之(編)
評者:相川藍

- 2012/07/28[新着書評]
『ことばの食卓』武田百合子
評者:杉江松恋

- 2012/07/18[新着書評]
『図説 死因百科』マイケル・ラルゴ
評者:大谷暁生

- 2012/07/13[新着書評]
『最果てアーケード』
小川洋子
評者:長坂陽子

- 2012/07/12[新着書評]
『なぜ戒名を自分でつけてもいいのか』橋爪大三郎
評者:千三屋

- 2012/07/05[新着書評]
『少年は残酷な弓を射る』(上・下)
ライオネル・シュライヴァー
評者:長坂陽子

- 2012/07/04[新着書評]
『未解決事件 グリコ・森永事件~捜査員300人の証言』NHKスペシャル取材班
評者:挟名紅治

- 2012/07/02[新着書評]
『女が嘘をつくとき』リュドミラ・ウリツカヤ
評者:藤井勉

- 2012/06/29[新着書評]
連載 蔓葉信博「週末、たまにはビジネス書を」
第3回 三浦展『第四の消費』 蔓葉信博

- 2012/06/27[新着書評]
『シフォン・リボン・シフォン』近藤史恵
評者:相川藍

- 2012/06/26[新着書評]
『湿地』アーナルデュル・インドリダソン
大谷暁生

- 2012/06/20[新着書評]
『彼女の存在、その破片』野中柊
長坂陽子

- 2012/06/15[新着書評]
『新人警官の掟』フェイ・ケラーマン
日向郁

- 2012/06/14[新着書評]
『俳優と超人形』ゴードン・クレイグ
千三屋

- 2012/06/13[新着書評]
『毒婦。 木嶋佳苗100日裁判傍聴記』北原みのり
長坂陽子

- 2012/06/12[新着書評]
『WOMBS』白井弓子
大谷暁生

- 2012/06/11[新着書評]
『21世紀の世界文学30冊を読む』都甲幸治
藤井勉

- 2012/06/08[新着書評]
『愛について』白岩玄
評者:相川藍

- 2012/06/06[新着書評]
『柔らかな犀の角ー山崎努の読書日記』山崎努
挟名紅治

- 2012/06/04[新着書評]
『夜をぶっとばせ』井上荒野
長坂陽子

- 2012/06/01[新着書評]
「七夜物語』川上弘美
長坂陽子

- 2012/05/23[新着書評]
「ピントがボケる音 OUT OF FOCUS, OUT OF SOUND』安田兼一
藤井勉

- 2012/05/21[新着書評]
「飼い慣らすことのできない幻獣たち」
『幻獣辞典』ホルヘ・ルイス・ボルヘス
藤田祥平

- 2012/05/16[新着書評]
連載「長坂陽子 ロマンスの神様願いを叶えて第18回」
「その名は自己満足」 長坂陽子

- 2012/03/30[新着書評]
連載「長坂陽子 ロマンスの神様願いを叶えて第17回」
「そのプライドが邪魔をする」 長坂陽子

- 2012/02/28[新着書評]
連載「長坂陽子 ロマンスの神様願いを叶えて第16回」
「恋のリスクマネジメント」 長坂陽子

- 2012/02/15[新着書評]
連載「長坂陽子 ロマンスの神様願いを叶えて第15回」
「非華奢女子の生きる道」 長坂陽子

- 2012/02/02[新着書評]
連載「長坂陽子 ロマンスの神様願いを叶えて第14回」
「パターン破りの効用」 長坂陽子

- 2012/01/31[新着書評]
『最高に美しい住宅をつくる方法』彦根明
評者:相川藍

- 2012/01/20[新着書評]
『ペット・サウンズ』ジム・フジーリ
評者:藤井勉

- 2012/01/17[新着書評]
連載「長坂陽子 ロマンスの神様願いを叶えて第13回」
胸だけ見ててもモテ期はこない 長坂陽子

- 2012/01/11[新着書評]
連載「長坂陽子 ロマンスの神様願いを叶えて第12回」
「恋で美しくなる」は本当か 長坂陽子

- 2012/01/10[新着書評]
「旧式のプライバシー」
『大阪の宿』水上滝太郎
藤田祥平
Internet Explorerをご利用の場合はバージョン6以上でご覧ください。
















