甲斐庄楠音画集―ロマンチック・エロチスト
筋金入りのナルシストによる複雑きわまりない個性と欲望のありよう…没後30年目にして初の画集!
著 甲斐庄楠音 監 島田康寛求龍堂 [画集・写真集] 国内
2009.03 版型:B5
>>書籍情報のページへ

肩からずり落ちた紫の着物の前をしどけなくはだけて、赤い裏地と火焔の裾模様の黄橙色の襦袢を見せ、両手をだらりと垂らして、ぼうっと微笑みながらこちらに視線を向けている青白い顔の女。岩井志麻子の短編集『ぼっけえ きょうてえ』の表紙にも使われた、妖気みなぎる美人画『横櫛』(大正5年/1916年頃)の作者の名は甲斐庄楠音(かいのしょう ただおと)。京の旧家に生まれ、京都市立美術工芸学校(現京都市立芸術大学)の卒業制作として描いた『横櫛』で認められ、大正期の京都画壇で活躍した後、昭和16年(1941年)以降は活動の拠点を映画界に移し、全盛期の日本映画の名作の数々の風俗・衣装考証を担当するという、異色の経歴をもつ日本画家の、没後30年目に刊行された最初の画集です。表紙に使われている『島原の女(京の女)』(大正9年/1920年)の、額際の赤らんだ地肌の感触も生々しく、白粉の香がじかに漂ってきそうな花魁の顔を一目見るだけで、その先に広がる尋常ではない世界の予感が迫ってきます。
今となってはモノクロ図版でしか見ることができない失われた代表作『女と風船(蝶々)』(大正15年/1926年)の、豊かな胸をはだけて放心したようにうずくまる女の重たげな肢体と、その傍らに糸をすっと垂らして浮かんでいる、はち切れそうにまるくつややかな風船の、なんともいえずアンバランスな調和に、甲斐庄楠音の絵画のエッセンスが凝縮されているといえるかもしれません。この『女と風船』は、当時の京都画壇の重鎮土田麦遷に、「穢い絵は会場を穢くする」と評され、同年の第五回国画創作協会展への陳列を拒否されたといわれる作品です。この出来事は、甲斐庄楠音にとって終生のトラウマになると共に、やはり終生にわたって貫かれる「穢いが生きて居る」という美学の原点ともなったようです。
本書に収録された甲斐庄楠音の代表的な美人画の数々は、すっきりと粋な江戸前の美人画とはかけ離れ、ときには不快感や嫌悪感すれすれの反応をかきたてますが、そこが独特の官能性に通じてもいます。髪と衣装と肉体の重さに今にも崩れおちそうな風情で立ち、あるいは座り、ときにはそうした鬱陶しい重さに抗うように激しく舞う女たちの姿からたちのぼる鬼気。傾倒したレオナルド・ダ・ヴィンチの人物像の面影を宿してほほえむ花魁の、厚い白粉に塗りこめられた蒼白の顔。いずれも一目見たらいつまでも憑いて離れない不可思議な魅惑をたたえた顔と肢体をもつ女たちです。
そして、尋常でないことにかけたら、作中の女たちの存在感にひけをとらないのが、甲斐庄楠音その人の経歴と人柄です。実家の甲斐荘家は楠正成の後裔にあたり、養子として甲斐庄家に入った父は京都西本願寺の連枝の出、御所侍の娘として幼いころから御所に出入りしていた母は、孝明天皇の日常生活をかいま見、上洛した徳川慶喜の男ぶりに胸をときめかせたこともあるという、まさに極めつけの「京の名家」の生まれ。本書には、皇女和宮の恩賜の品々の想い出を物語る「皇女和宮の羽子板」をはじめ、本人の筆によるいくつかのエッセイが収録されており、幕末の記憶をいまだ濃くとどめた明治期の京都の旧家の暮らしぶりが生々しく伝わってきます。
和宮恩賜の羽子板や晴着をこよなく愛する幼児だった楠音は、長じた後も好んで人形遊びと女装を続けることになります。自作の美人画の人物を模倣して、女装あるいは裸身でポーズを取り、その姿を写真に撮っては愛でる筋金入りのナルシストでもあり、代表作のひとつ『青衣の女』のモデルだった女性を思慕しつづけるとともに、多くの同性の恋人をもった両性愛者でもあったという、そのユニークな多面性の一端をかいま見せてくれる数々の写真と、スケッチブック、スクラップブックの抜粋は、作品それ自体に勝るとも劣らない興味深さです。
煙管を手にした花魁姿、大きなリボンを頭に飾ってフランス人形を膝にのせた西洋の令嬢風の姿、同性の友人と一緒に女装して寄り添い、あるいは芝居の中の恋人同士を演じている姿……。本書に収録された甲斐庄楠音のセルフポートレイトの数々には、「大正期には木原敏江の少女マンガの世界が現実に存在していたのか!」という驚きがあります。わけても、一見すると家族写真ふうの集団の間に、日本髪を結った娘姿の楠音が、手をついた横座りで何気なく紛れ込んでいる一枚の、「儀式」と「芝居」のアンバランスな共存ぶりが、なんとも印象的です。
そして、遺品として残された60冊に及ぶスクラップブックからの抜粋を見れば、自作に関する新聞雑誌記事の切り抜き、古今東西の名画の複製写真、大正期から昭和40年代に至る映画のスチルや男女のスターのブロマイド、歌舞伎の舞台写真、スポーツ選手の競技写真から、いかがわしげなヌード写真、本人やモデル女性の写真に至るまで、雑多な資料がぎっしりと貼りつけられ、めくるめくような趣味のカオスを構成しています。
というわけで、絵画作品、写真、スクラップブック、エッセイと見てゆくことで、甲斐庄楠音という特異な芸術家の複雑きわまりない個性と欲望のありようを、多方面から確認できる充実の画集。こうした人物を生んだ近代の京都という都市の奥行きの深さにも興味が尽きないところです。
甲斐庄楠音は、昭和16年に『元禄忠臣蔵 前編』(溝口健二監督)の衣装考証を担当したことを機に本格的に映画界入りし、以後、溝口健二監督とのコラボレーションを長年にわたって続けたほか、溝口作品以外にも、内田吐夢監督『大菩薩峠』(昭和32年/1957年)、伊藤大輔監督『反逆児』(昭和36年/1961年)など、日本映画史に名を残す数々の重要な作品に、風俗・衣装考証家として参加しています。それだけに、本書に関して欲をいえば、映画の仕事に関する記述・図版も充実させてほしかった感があります。溝口健二監督作品、わけても米アカデミー賞衣装部門にノミネートされた『雨月物語』(昭和28年/1953年)の風俗考証の仕事はあまりにも有名ですが、松竹京都撮影所のカラー作品『絵島生島』(大庭秀雄監督、昭和30年/1955年)の大奥女中たちの衣装の配色の優美さや、東映京都撮影所『旗本退屈男』の市川右太衛門がとっかえひっかえ身にまとうきらびやかな衣装の数々など、甲斐庄楠音の手になる印象的な映画の衣装には枚挙のいとまがありません。
本書の中に、映画に関する記述は比較的少ないとはいえ、たとえば『横櫛』の女人像は、『雨月物語』の京マチ子が、片方の肩だけに引っかけてずり落とした小袖の裾を引いて、森雅之を死霊の世界へと誘う、いじらしくも恐ろしい艶姿を髣髴とさせます。あるいは、スケッチブックに描かれたいくつかの若い男性の肢体のデッサンと、現在は絶版の評伝『女人讃歌―甲斐庄楠音の生涯』(栗田勇著、新潮社、1987年)に掲載されている、甲斐庄楠音が森雅之の裸の背中に魔除けの梵字を筆で書いている『雨月物語』撮影現場のスナップ写真には、相通じるほのかな熱気と官能が漂っているかもしれません。
おすすめ本書評・紹介書籍
-
- ロマンチック・エロチスト─甲斐庄楠音画集
求龍堂 [画集・写真集] 国内
2009.03 版型:B5
価格:5,460円(税込)
>>詳細を見る
新着情報
-

- 2013/08/16[新着書評]
『きことわ』朝吹真理子
評者:千三屋
-

- 2013/08/15[新着書評]
『テルマエ・ロマエⅥ』ヤマザキマリ/「1~3巻は大傑作、4~6巻は残念な出来」
評者:新藤純子
-

- 2013/06/19[新着書評]
『高円寺 古本酒場ものがたり』狩野俊
評者:千三屋

- 2013/05/12[新着書評]
『フィフティ・シェイズ・ダーカー(上・下)』ELジェイムズ
評者:日向郁

- 2013/04/04[新着書評]
『クラウド・アトラス』デイヴィッド・ミッチェル
評者:千三屋

- 2013/02/18[新着書評]
『はぶらし』近藤史恵
評者:日向郁

- 2013/01/31[新着書評]
『知的唯仏論』宮崎哲弥・呉智英
評者:千三屋

- 2013/01/18[新着書評]
『秋田寛のグラフィックデザイン』アキタ・デザイン・カン
評者:千三屋

- 2013/01/17[新着書評]
『空白を満たしなさい』平野啓一郎
評者:長坂陽子

- 2013/01/15[新着書評]
『箱根駅伝を歩く』泉麻人
評者:千三屋

- 2013/01/11[新着書評]
『世界が終わるわけではなく』ケイト・アトキンソン
評者:藤井勉

- 2012/12/19[新着書評]
『デザインの本の本』秋田寛
評者:千三屋

- 2012/11/28[新着書評]
『ニール・ヤング自伝I』ニール・ヤング
評者:藤井勉

- 2012/11/22[新着書評]
『日本人はなぜ「黒ブチ丸メガネ」なのか』友利昴
評者:新藤純子

- 2012/11/21[新着書評]
『私にふさわしいホテル』柚木麻子
評者:長坂陽子

- 2012/11/15[新着書評]
『格差と序列の心理学 平等主義のパラドクス』池上知子
評者:新藤純子
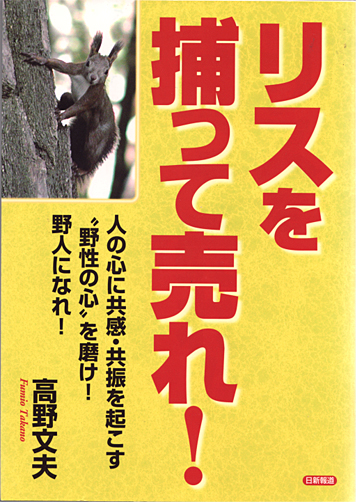
- 2012/11/09[イベントレポ]
兼業古本屋のできるまで。とみさわさん、なにをやってんすか

- 2012/11/08[新着書評]
『機龍警察 暗黒市場』月村了衛
評者:大谷暁生

- 2012/11/02[新着書評]
『なしくずしの死』L-F・セリーヌ
評者:藤田祥平

- 2012/10/31[新着書評]
『エコー・メイカー』リチャード・パワーズ
評者:藤井勉

- 2012/10/30[新着書評]
『文体練習』レーモン・クノー
評者:藤田祥平

- 2012/10/25[新着書評]
『生きのびるための建築』石山修武
評者:千三屋

- 2012/10/24[新着書評]
『占領都市 TOKYO YEAR ZERO Ⅱ』デイヴィッド・ピース
評者:大谷暁生

- 2012/10/19[新着書評]
『最後の授業 ぼくの命があるうちに』ランディ・パウシュ、ジェフリー・ザスロー
評者:日向郁

- 2012/10/18[新着書評]
『イタリア人と日本人、どっちがバカ?』ファブリツィオ・グラッセッリ
評者:相川藍

- 2012/10/17[イベントレポ]
ミステリー酒場スペシャル ローレンス・ブロック酒場Part1

- 2012/10/16[イベントレポ]
ブックレビューLIVE:杉江VS米光のどっちが売れるか!?

- 2012/10/15[イベントレポ]
ミステリ酒場スペシャル ローレンス・ブロック酒場三連発 PART2~泥棒バーニー、殺し屋ケラー編&ブロックおもてなし対策会議~

- 2012/10/15[新着書評]
『犬とハモニカ』江國香織
評者:長坂陽子

- 2012/10/10[新着書評]
『Papa told me cocohana ver.1 丘は花でいっぱい』榛野なな恵
評者:千三屋

- 2012/10/08[イベントレポ]
“その日”が来てからでは遅すぎる! あなたの知らないお葬式のすべて?ボッタクリの秘密から納得のエコ葬儀プランまで

- 2012/10/03[新着書評]
『青い脂』ウラジーミル・ソローキン
評者:藤井勉

- 2012/10/02[イベントレポ]
松本尚久さん、落語の楽しみ方を教えてください!

- 2012/10/01[新着書評]
『ヴァンパイア』岩井俊二
評者:長坂陽子

- 2012/09/25[新着書評]
『鬼談百景』小野不由美
評者:挟名紅治

- 2012/09/24[新着書評]
『ここは退屈迎えに来て』山内マリコ
評者:長坂陽子

- 2012/09/18[新着書評]
『最初の人間』アルベール・カミュ
評者:新藤純子

- 2012/09/14[新着書評]
『その日東京駅五時二十五分発』西川美和
評者:相川藍

- 2012/09/13[新着書評]
『無分別』オラシオ・カステジャーノス・モヤ
評者:藤井勉

- 2012/09/12[新着書評]
『鷲たちの盟約』(上下)アラン・グレン
評者:大谷暁生

- 2012/09/11[新着書評]
『ラブ・イズ・ア・ミックステープ』ロブ・シェフィールド
評者:日向郁

- 2012/09/10[新着書評]
『嵐のピクニック』本谷有希子
評者:長坂陽子

- 2012/09/07[新着書評]
『本当の経済の話をしよう』若田部昌澄、栗原裕一郎
評者:藤井勉

- 2012/09/05[新着書評]
『ひらいて』綿矢りさ
評者:長坂陽子

- 2012/09/04[新着書評]
『失脚/巫女の死 デュレンマット傑作選』フリードリヒ・デュレンマット
評者:藤井勉

- 2012/09/03[新着書評]
『かくも水深き不在』竹本健治
評者:蔓葉信博

- 2012/08/31[新着書評]
『わたしが眠りにつく前に』SJ・ワトソン
評者:長坂陽子

- 2012/08/28[新着書評]
『芸術実行犯』Chim↑Pom(チン↑ポム)
評者:相川藍

- 2012/08/27[新着書評]
『ぼくは勉強ができない』山田詠美
評者:姉崎あきか

- 2012/08/16[新着書評]
『オカルト 現れるモノ、隠れるモノ、見たいモノ』森達也
評者:長坂陽子

- 2012/08/10[新着書評]
『セックスなんか興味ない』きづきあきら サトウナンキ
評者:大谷暁生

- 2012/08/08[新着書評]
『深い疵』ネレ・ノイハウス
評者:挟名紅治

- 2012/08/07[新着書評]
【連載】 蔓葉信博「週末、たまにはビジネス書を」
第4回 小林直樹『ソーシャルリスク』 評者:蔓葉信博

- 2012/08/03[新着書評]
『はまむぎ』レーモン・クノー
評者:藤井勉

- 2012/08/02[新着書評]
『清須会議』三谷幸喜
評者:千三屋

- 2012/07/31[新着書評]
『岡崎京子の仕事集』岡崎京子(著)増渕俊之(編)
評者:相川藍

- 2012/07/28[新着書評]
『ことばの食卓』武田百合子
評者:杉江松恋

- 2012/07/18[新着書評]
『図説 死因百科』マイケル・ラルゴ
評者:大谷暁生

- 2012/07/13[新着書評]
『最果てアーケード』
小川洋子
評者:長坂陽子

- 2012/07/12[新着書評]
『なぜ戒名を自分でつけてもいいのか』橋爪大三郎
評者:千三屋

- 2012/07/05[新着書評]
『少年は残酷な弓を射る』(上・下)
ライオネル・シュライヴァー
評者:長坂陽子

- 2012/07/04[新着書評]
『未解決事件 グリコ・森永事件~捜査員300人の証言』NHKスペシャル取材班
評者:挟名紅治

- 2012/07/02[新着書評]
『女が嘘をつくとき』リュドミラ・ウリツカヤ
評者:藤井勉

- 2012/06/29[新着書評]
連載 蔓葉信博「週末、たまにはビジネス書を」
第3回 三浦展『第四の消費』 蔓葉信博

- 2012/06/27[新着書評]
『シフォン・リボン・シフォン』近藤史恵
評者:相川藍

- 2012/06/26[新着書評]
『湿地』アーナルデュル・インドリダソン
大谷暁生

- 2012/06/20[新着書評]
『彼女の存在、その破片』野中柊
長坂陽子

- 2012/06/15[新着書評]
『新人警官の掟』フェイ・ケラーマン
日向郁

- 2012/06/14[新着書評]
『俳優と超人形』ゴードン・クレイグ
千三屋

- 2012/06/13[新着書評]
『毒婦。 木嶋佳苗100日裁判傍聴記』北原みのり
長坂陽子

- 2012/06/12[新着書評]
『WOMBS』白井弓子
大谷暁生

- 2012/06/11[新着書評]
『21世紀の世界文学30冊を読む』都甲幸治
藤井勉

- 2012/06/08[新着書評]
『愛について』白岩玄
評者:相川藍

- 2012/06/06[新着書評]
『柔らかな犀の角ー山崎努の読書日記』山崎努
挟名紅治

- 2012/06/04[新着書評]
『夜をぶっとばせ』井上荒野
長坂陽子

- 2012/06/01[新着書評]
「七夜物語』川上弘美
長坂陽子

- 2012/05/23[新着書評]
「ピントがボケる音 OUT OF FOCUS, OUT OF SOUND』安田兼一
藤井勉

- 2012/05/21[新着書評]
「飼い慣らすことのできない幻獣たち」
『幻獣辞典』ホルヘ・ルイス・ボルヘス
藤田祥平

- 2012/05/16[新着書評]
連載「長坂陽子 ロマンスの神様願いを叶えて第18回」
「その名は自己満足」 長坂陽子

- 2012/03/30[新着書評]
連載「長坂陽子 ロマンスの神様願いを叶えて第17回」
「そのプライドが邪魔をする」 長坂陽子

- 2012/02/28[新着書評]
連載「長坂陽子 ロマンスの神様願いを叶えて第16回」
「恋のリスクマネジメント」 長坂陽子

- 2012/02/15[新着書評]
連載「長坂陽子 ロマンスの神様願いを叶えて第15回」
「非華奢女子の生きる道」 長坂陽子

- 2012/02/02[新着書評]
連載「長坂陽子 ロマンスの神様願いを叶えて第14回」
「パターン破りの効用」 長坂陽子

- 2012/01/31[新着書評]
『最高に美しい住宅をつくる方法』彦根明
評者:相川藍

- 2012/01/20[新着書評]
『ペット・サウンズ』ジム・フジーリ
評者:藤井勉

- 2012/01/17[新着書評]
連載「長坂陽子 ロマンスの神様願いを叶えて第13回」
胸だけ見ててもモテ期はこない 長坂陽子

- 2012/01/11[新着書評]
連載「長坂陽子 ロマンスの神様願いを叶えて第12回」
「恋で美しくなる」は本当か 長坂陽子

- 2012/01/10[新着書評]
「旧式のプライバシー」
『大阪の宿』水上滝太郎
藤田祥平
Internet Explorerをご利用の場合はバージョン6以上でご覧ください。
















